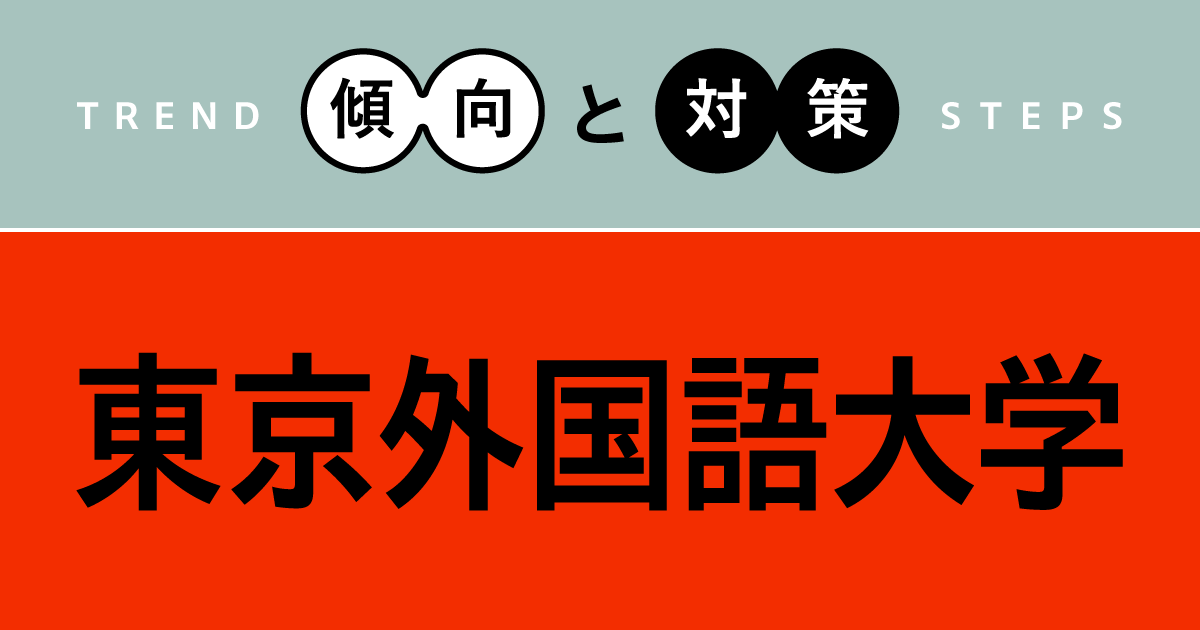
傾向と対策(前期日程)
2023年度までの前期日程の入試問題を分析しました。さらに詳しい最新の分析は「大学赤本シリーズ」をご覧ください。
【目次】
【英語】
傾向
※2019~2023年度の分析
速読即解が前提条件 記述式の設問とリスニングがポイント
| 出題形式 | 合計5題(読解2題、リスニング2題、リスニングと英作文の融合問題1題)
※2020年度までは例年大問6題(読解3題、リスニング2題、リスニングと英作文の融合問題1題) |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 ※2020年度までは150分 |
| 解答形式 | 記述式の設問が中心。読解問題の空所補充、リスニング問題の内容説明は選択式となっている。 |
出題内容
読解問題
- 1題の英文の長さは400〜1200語程度。2021年度以降は大問2題で合計2000語弱。
- 論説文が中心で、自然科学、政治・社会、人類学など内容は多岐にわたるが、文章自体のレベルは標準的である。
- 大問ごとに設問の種類が絞り込まれている。
- 字数制限つきの内容説明、記述量は1問につき30〜100字。
- 単語の空所補充(語形変化を含む)
- 長めの語句・文の空所補充 ※2020年度以前で出題
リスニング問題
- 2題ともに内容説明、いずれも放送される英文は比較的長い。
- 話の流れと設問の順序はほぼ一致している。
- 英作文問題と合わせて出題される大問は2回流されるが、それ以外の放送は1回限り。
英作文問題
- リスニングと合わせて出題されている。
- 例年、リスニングによる講義の内容の要約と、関連する課題についての意見論述の2問が課されている(2021年度は要約のみの出題であった)。
- 指定語数は要約、意見論述ともに200語程度。
難易度
- 全体的に難度は高い。
対策
①読解問題:「読む」こと自体に抵抗感がないようにしておこう。
- 英文の読解量を増やすには、学校のリーディング教材を1課通しで読む、他大学の過去問を片っ端から読むなど、工夫すれば妥当なレベルの文章は身のまわりに多くある。
- 一読ですぐに意味が把握できなかった箇所については、文構造や使われている文法事項などを十分に分析して、基本的な英語力を高めておく。
- 設問の要求や条件を満たす文章をまとめる力を培い、内容説明の記述力をつける。
- 過去問をできるだけ多く、古いものまでさかのぼって練習する。
- 他大学で出された英文でも、段落を要約してみる、指示語の内容を書いてみる。
- 過去問演習の際には、〈解答例〉と照らし合わせて、自分の答案を添削し、客観的に評価できるようにする。
②リスニング問題:日常的に英語を聞くよう努力する
- 読解の問題集にも、CDがついているものやダウンロードで音声が聴けるものがあるので耳を鳴らすのに活用する。
☞オススメ参考書『大学入試 絶対できる英語リスニング』(教学社)
- 聞くだけでなく、読解英文などを積極的に音読し、自分でも音声を発することを同時に行っておくこと。
③英作文問題:リスニングとの融合問題
- 講義内容に関する図版や要点のノートが問題冊子に印刷されているので、それにあらかじめ目を通して骨子となるキーワードを少しでも多く拾えるように備える。
- 意見論述は、何をどう述べるか、最初に全体の構想をおおまかに決めておく。
- 英語の論説のパターンとしては、まず自分の立場(賛否など)を表明し、その理由や具体例を挙げるのが定石である。
- 書いた英文は十分に見直して、自分のミスが発見できるようにする。
- 主語と動詞の数の一致、文型、名詞の単数・複数や冠詞、時制などの文法的な面で失点しないようにする。























































