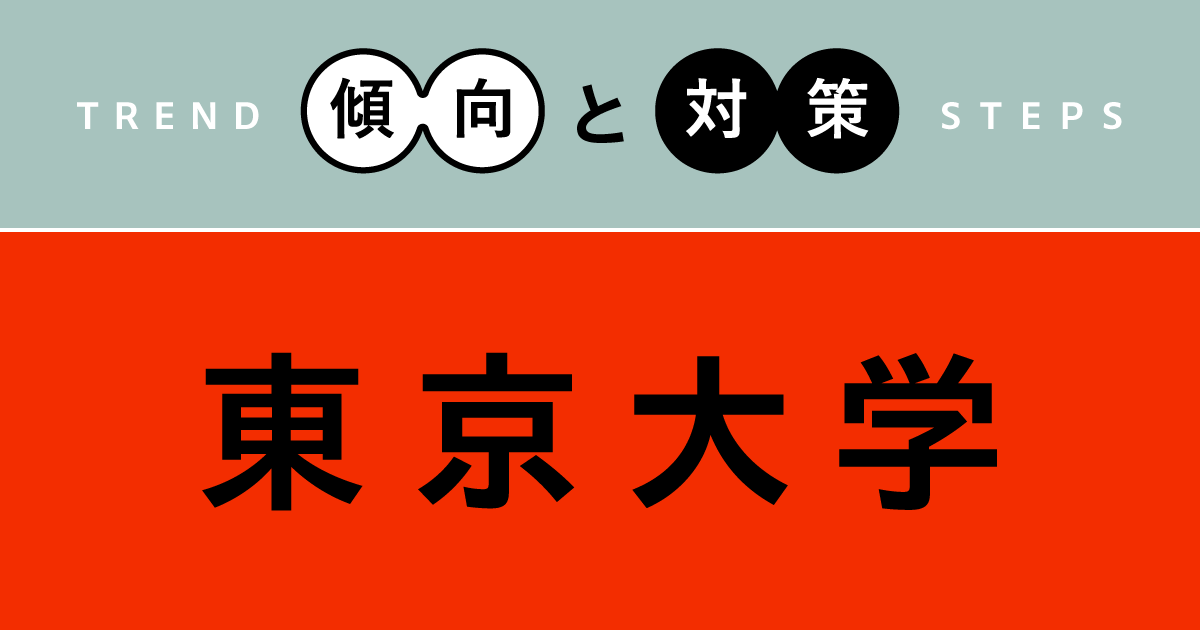
傾向と対策(前期日程)
2023年度までの前期日程の入試問題を分析しました。さらに詳しい最新の分析は「大学赤本シリーズ」をご覧ください。
【目次】
【英語】
傾向
処理の素早さがポイント! 速読即解+即表現の総合力が必要
| 出題形式 | 大問5題(読解、英作文、リスニング、文法・語彙) |
|---|---|
| 試験時間 | 120分。聞き取り試験は例年、試験開始後45分を経過した頃から約30分間、問題が放送される。 |
| 解答形式 | 要約・英作文・英文和訳の本格的な記述が中心。選択問題ではマークシート法が採用されている。 |
出題内容
(1)読解問題
- 要約問題:〔1〕(A)として毎年出題。英文自体は300〜400語程度。要約の制限字数は70〜80字。随筆的なものも含めて論説文中心。
- 文脈把握問題:例年、〔1〕(B)では文章の流れ・論旨・場面の展開を読み取る力を見る問題が出題。出題内容としては、空所補充、語句整序など。
- 英文和訳:例年、〔4〕(B)が独立した英文和訳問題となっている。与えられる文章の長さ、和訳箇所の数、和訳部分の量は年度により異なる。
- 読解総合問題:〔5〕は例年読解総合問題である。英文の長さは年度によって異なるが、〔1〕と〔5〕の合計は例年2000〜2200語程度。題材として、論説系よりも・伝記・物語・随筆といった文学系のものが多い。設問は、意味内容、適切な語句の補充といった各箇所の細かい理解を求めるものが多い。
(2)英作文問題
- テーマ英作文・意見論述:与えられたテーマについて60〜80語程度で書くものや、意見や理由を求められる問題が出題。
- 要約問題:〔1〕でも求められる要点把握力がベースで、それを英語で表現する力がプラスされることになる。
- 和文英訳:〔2〕(B)で出題されている。短い文章の部分訳。
(3)文法・語彙問題
- 文章中の誤りの箇所が問われた。主に5つの段落に5カ所ずつ下線が入っており、誤りを含むものを各段落から一つずつ選ぶ形式。
(4)リスニング問題
- 例年、(A)・(B)・(C)の3パートからの出題が続いている。放送内容は大きく分けて、講義形式のものと、会話形式のものとがある。設問内容は、内容説明と内容真偽、文章の表題など。
難易度
- 問題分量の多さという点だけでも、難度はかなり高い。
- とにかく時間との戦いとなるだろう。設問には、かなり難度の高いものが含まれることもあり、そうした問題に時間を取られすぎると、とうてい時間内に解き終わることはできない。リスニングも読み上げられる英文が非常に長く、日頃から対策を積んでおかないと対応できないものである。
対策
読解問題
①語彙の充実…標準的な語句を完全消化することを目標に。
- 単語集に載っている代表的な訳語が全部言えるというレベルから、さらにその語の持つ意味の広がりまでつかんでおく。
- 辞書を丁寧に読む。訳語のチェックだけでなく用例も見て、その語がどのような使われ方をするのか、どのようなニュアンスかをつかむようにする。
☞オススメ参考書『東大の英単語』(教学社)
- テーマ別に類義語の使い分けやニュアンスに言及してあり、わかりやすい。
- 東大の過去問の文章を使った確認問題もある。
②文脈把握力を養う:常に全体の構成に目を配るようにしよう。
- 要約問題:筆者の主張をつかむには、具体例など、枝葉にあたる部分を取り除いてみるとよい。ただし、残りを単純につなぎ合わせただけでは、要約としては不十分である。各部分の全体に対する役割を理解し、要点を再構築することを心がける。
☞オススメ参考書『東大の英語 要約問題 UNLIMITED』(教学社)
- 英文和訳問題:一連の文章の一部が問題になっていることが多い。下線部以外のところもきちんと読み、全体の流れ、筆者の主張を理解したうえで解答すること。
また、内容は理解できるものの、わかりやすい日本語にまとめるのが難しい場合もあり、日本語の語彙力や文章作成能力も高めておく必要がある。
- 読解総合問題:1000語程度のものは一気に読めるよう、普段から訓練しておく。
文章の種類は、文学系のもの(物語・伝記・随筆など)が中心。具体的な場面やその時の人物の気持ちなどを生き生きと思い描けることが重要。
英作文問題
(1)テーマ英作文・意見論述
- 設問内容が多様、どのようなものでも素早く対応できるように過去問を十分に研究しておく。
- 根拠・理由を挙げて「賛否」を論じるテーマの場合は、異なった視点から考える練習にもなるので、両方の立場で書いてみるとよい。
- 大阪大学や、早稲田大学法学部・国際教養学部といった他大学の過去問の利用もオススメ。
(2)要約問題
- 指定語数はぎりぎりのことが多く、それに収まるようにする基本的な力は〔1〕(A)と同じである。〔1〕(A)の解答を作成したら、それを英語で表現してみる、ということで対策できる。
(3)和文英訳
- 標準的な構文や語法を十分使いこなせることは、他の形式の英作文でも必要なことなので、市販の問題集の例文などを徹底的にマスターする。
☞オススメ参考書『東大の英語25カ年』(教学社)
文法・語彙
- 問われる文法事項は基本的なものばかりではあるが、完全に理解できていないと解答できないものも多い。
- 英文に接する際は「なんとなく」単語から意味を推測して読んでしまわないよう日頃から意識する。
- 誤り指摘対策として、文型の把握、修飾関係など、文中のすべての語について文法機能がしっかり把握できるよう訓練を積む。
☞オススメ参考書『大学入試すぐわかる英文法』(教学社)
リスニング問題
試験時のpoint!
- 「リスニング放送の前に問題冊子の設問文や選択肢に目を通す」
- 各パートそれぞれの放送内容の場面設定が簡単に書かれていることが多いので、それも見落とさないこと。
- 設問を読めば、どんな内容の講義や会話かある程度推測でき、聞き取る必要のあるポイントもつかめる。
- リスニング放送が開始される4,5分前になったら、これらの準備を始められるようにしておく。
- 放送は2回
- 最初の1回は大きな流れをつかむよう心がけ、数値などはできるだけメモを取る。
- 2回目は1回目で聞き取った内容を確認すると同時に、聞き取りにくかったところに集中して、細部までとらえるようにする。
☞オススメ参考書『東大の英語リスニング20カ年』(教学社)
【数学・理科】
傾向
論理的思考力・考察力、計算力・処理力を要する問題が出題
| 出題形式 | 6題 |
|---|---|
| 試験時間 | 150分 |
| 解答形式 | 全問記述式。解答過程も記述するもの。 |
出題内容
- 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(数列、ベクトル)
頻出項目
- 微・積分法、図形と方程式(点の存在範囲・曲線の通過範囲を含む)、数列、極限、整数、空間図形
出題内容
①整数の扱いを含む問題
- ほぼ毎年出題されている。どの年度も大体、やや難〜難レベル。
②数列の問題
- 何らかの形でほぼ毎年出題されている。近年難度が高い問題が続いている。
- 多項式の係数についての発想力と処理力。数列の漸化式を用いた論証力と記述力など。
③空間図形の問題
- この7年はほぼ毎年出題されている。処理力を要求するものが多い。難度は高い。
- 最近は回転体の体積の問題、切断面についての誘導のついた出題、回転体に関する誘導のない問題、線分の存在範囲の体積など。
④極限の問題
- ほとんどが諸分野の問題で求めた式の値の極限を問う形。区分求積の形での出題もあった。
⑤三角関数に関する問題
- 三角関数そのものを題材にするというよりも、図形と方程式、微・積分法等の他分野に分類される問題での処理で用いられることが多い。
- 三角方程式の解の個数について、対数関数との合成関数の増減の証明問題と定積分の計算問題など。
⑥複素数平面
- この7年間では2017〜2019・2021年度に出題。2018・2019年度はいずれもやや難のレベル。
⑦確率・場合の数
- 場合分けを徹底する訓練や推移図から規則性を見出す訓練が必要。
- 漸化式によらない出題や、漸化式の処理とからませた出題など。難度も高い。
- 文科でも必須項目なので、念のため文科の過去問も解くとよい。
難易度
- 2022・2023年度は難化。
- 年度により変化は若干みられるが、粘り強い論理的思考力・論証力、図形的考察力、高度な計算処理能力を要する点では一貫している。過去問演習などを通じて高度な数学的思考力・計算力・表現力を身につけておきたい。また、いずれの難易度でも特に計算ミスによる失点は極力避けたい。
対策
① 粘り強い思考と論理的な根拠記述
- 東大の数学に必要なのは「発想力・計算力・場合分け・論証力」。
- 記述にあたっては、論理的な思考を端的に表現するように心がけなければならないが、立式の根拠記述などポイントになる理由付けは、簡潔でもよいから省かずに記述すること。
② 場合分けと計算力
- 領域、確率、場合の数、整数などの分野 ⇒思考を整理する上で、場合分けの良し悪しが決定的なはたらきをすることが多い。見逃している場合がないか、最終的にどうまとめるかも含めて、普段から意識的に学習することが大事。
- 積分計算や数列、確率などでは計算ミスが致命的になることも多い。 ⇒1行ごとに計算を素早くチェックする。 代入する数値や分数計算、符号での誤りがないか確かめる。 特別な値で結果を検証する等、常に心がける。
- 複雑な計算をやり抜く根気を養う。
③ 基礎事項を軽視しない。
- 通常の授業で取り扱われる定義、証明、基礎的な操作、公式の適用などを絶対に軽視しない。 ⇒それとともに過去問に多く接することにより、それらの基礎事項を総合的に理解しながら定着させていくことも重要。 その過程で、よく使われているアイデアも身につけることができる。
【数学・文科】
傾向
論理的思考力が問われる問題と
方針の立てやすい素直な問題の組み合わせ
| 出題形式 | 大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 100分 |
| 解答形式 | 全問記述式 |
出題内容
- 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列、ベクトル)
頻出項目
- 微・積分法、図形と方程式(点の存在範囲・曲線や線分の通過範囲を含む)
- 数列、整数、確率・場合の数
出題内容
① 関数のグラフ、領域、点の存在範囲、曲線や線分の通過範囲
- ほぼ毎年出題されている。処理能力と場合分けの力が試される。
② 確率・場合の数
- 確率…場合を尽くして調べ上げる力、推移図から規則性を見出す力。
- 場合の数…数え上げの巧拙が問われる。
- 標準〜やや難の問題が多い。
③ 数列、整数
- 整数においての基礎である整除(約数、倍数、素数・互いに素)の理論に関する論証や、数列と整数の融合問題の処理はきわめて重要である。
④ 図形と方程式
- 放物線と3次関数のグラフと直線・円の問題が頻出。
- ベクトル自体の問題は少ないが、解法において利用できることがある。
難易度
- 年度によって難易度の変動はあるが、易、標準、やや難、難が組み合わさったセットである。2023年度はほとんどがやや易〜標準レベルであった。
- 年度により多少の幅や変化があっても、計算ミスで大きな差が生じるので、難易度によらず正しい数値計算の練習はとても大切である。
対策
① 粘り強い思考と論理的な根拠記述
- 東大の数学に必要なのは「発想力・計算力・場合分け・論証力」。
- 記述にあたっては、論理的な思考を端的に表現するように心がけなければならないが、立式の根拠記述などポイントになる理由付けは、簡潔でもよいから省かずに記述すること。
- 特別な発想を要する問題では差が出ないので、通常の学習を大切にして、標準を少し超えるレベルの問題を確実に解けるよう演習を積むことが大切である。
② 場合分けと計算力
- 領域、確率、場合の数、整数などの分野
- 思考を整理する上で、場合分けの良し悪しが決定的なはたらきをすることが多い。見逃している場合がないか、最終的にどうまとめるかも含めて、普段から意識的に学習することが大事。
- 積分計算や漸化式、確率などでは計算ミスが致命的になることも多い。
- 1行ごとに計算を素早くチェックする。
- 代入する数値や分数計算、符号での誤りがないか確かめる。
- 特別な値で結果を検証する等、常に心がける。
③ 基礎事項を軽視しない。
- 通常の授業で取り扱われる定義、証明、基礎的な操作、公式の適用などを絶対に軽視しない。
- それとともに過去問に多く接することにより、それらの基礎事項を総合的に理解しながら定着させていくことも重要。その過程で、よく使われているアイデアも身につけることができる。
【物理】
傾向
無理な難問ではないが思考力・数理能力を要する
物理現象を深く理解し、特徴を把握しよう
| 出題形式 | 大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 例年、理科2科目で150分 |
| 解答形式 | 計算問題は最終結果だけではなく、途中の過程まで記述する解答形式がほとんど。論述を要する設問、グラフを選択する問題、空所補充形式、数値計算の問題など。 |
出題範囲
- 物理基礎・物理
出題内容
- 高校の物理の2大分野である力学と電磁気からの出題の割合が大きい。
- 複数の分野を融合させた総合的な問題が多い。
- 個々の設問は頻出の標準的なものでも、その組み合わせ方や題材を扱う切り口に工夫がこらされたり、受験生があまり見慣れない題材が用いられたりしている場合も多い。
- 設問は文字式の計算問題が中心。近似計算をしたり、数学的な処理能力が求められたりすることもよくある。また、適切な図やグラフを選ぶ問題がよく出題されている。
難易度
- 年度により難易度や問題量にばらつきがある。2023年度はこの数年の中でもっとも難易度の高い問題であったと思われる。
- 全体として、高校の物理の範囲を逸脱することなく、無理な難題は出題されていないが、見慣れない設定で、その場で考えさせる問題も多い。難易の傾斜も考慮され、ときに誘導的な問題文になるが、いずれにしても応用的な思考力や総合的な数理能力を要求する問題となっている。
対策
① 教科書を中心に基本事項の徹底的な理解を
- 教科書で扱われている程度の事項はきちんと学習し、公式を導く過程や物理量の定義などの理解を十分にしておく。
- その上で、程度の高い参考書をざっと読んでおくとよい。
② 目的をもった問題演習を
- まずは教科書傍用や標準的な程度の問題集を完全にこなし、その上で、応用力や思考力を養うための問題集に取り組む。
☞オススメ参考書
『物理〔物理基礎・物理〕標準問題精講』(旺文社)
『理論物理への道標<上・下>』(河合出版)
※いたずらに数をこなすのではなく、問題の背景や計算結果の持つ意味を考えてみるなど、一歩踏み込んで掘り下げるような勉強も必要!
- 別の解法を考えるような練習もする。
③ 計算力の養成
- 途中の経過まで記述する解答形式が大半。
- 問題練習の際は、面倒がらずに、計算過程をしめしながら、自分の手で計算する。
- 近似計算に慣れる。
- 教科書の計算例(単振り子、ヤングの実験、ニュートンリングなど)、赤本の過去の問題などで、近似式の使い方をよく見ておく。
④ 出題傾向・出題形式に合わせた練習をする
- 論述問題対策…考察理由を簡潔な文章に書き表すような練習をふだんからしておく。
☞オススメ参考書『東大の物理25カ年』(教学社)
- 適切な図やグラフを選ぶ問題…実際に自分で図やグラフを描く。
試験時間に対して設問の分量は多めであり、問題全体の見通しを立てて、素早く解く能力が必要である。
【化学】
傾向
有機の構造決定が頻出 酸化還元・化学平衡の応用力を
| 出題形式 | 大問3題(各大問が中問2問で構成されており、実質6題の分量で出題) |
|---|---|
| 試験時間 | 例年、理科2科目で150分 |
| 解答形式 | 記述式と論述式による設問が主体。計算問題は答えに至る過程を示すことが要求されることも多い。論述問題は理由説明を求めることが多く、ときに現象説明が求められることもある。 |
出題範囲
- 化学基礎・化学
頻出項目
- 理論分野
- 全体的に理論分野からの出題が多く、テーマを決めた総合問題で応用力が試される。
- 酸化還元反応、熱化学、反応速度と化学平衡、気体の法則、結晶構造、溶液の性質など
- 無機分野
- 理論分野と絡めて出題されることもあるので注意が必要。
- イオン分析と錯イオンの構造、気体の発生と性質、無機工業分野などの出題はメインというよりはサブとしての取り扱いが多いが、基本から標準的な設問。実験操作・装置は教科書記載レベル。
- 有機分野
- 有機化合物の構造決定に関する出題が多く、組成式、分子量測定から分子式を求め、各種検出反応を通して構造を決定する。このとき、構造異性体のみならず、幾可異性体、鏡像異性体を考慮することが多い。
- 炭素間二重結合をもたない環式化合物の立体異性体、鎖式および環式化合物の鏡像異性体・L体とD体の構造などについて深みのある学習が必要。
- 単糖類・アミノ酸から多糖類・タンパク質およびDNA・RNAなどの天然有機化合物、さらに特異な高分子化合物からの出題は難度が高い。
難易度
- 難問もあるが、一つ一つは高校で学習した知識で対応できるだろう。有機・理論分野での出題は標準的だが、ときにやや難の出題もみられる。
- 問題量、試験時間、解答内容を考慮すると、時間的余裕はない。最初に全体を見わたして、手をつけやすい問題から解いていくなどの工夫が求められる。高校の教科書では取り扱われていない内容が出題されることも多く、それだけに幅広い科学的知識と緻密な考察力が問われる。応用力を養成するためにも、常に「なぜそうなるのか」を考えながら問題演習に当たろう。
対策
①理論分野:教科書を土台に理解を深める。
- 見慣れない題材を取り上げた問題は、知識重視よりも問題文の熟読・読解を中心に考えて問題に当たる。
- 酸化還元や化学平衡の分野では実験データの読み取りや化学変化の予測を含めて、筋道の通った答案づくりをめざそう。
- 酸化剤や還元剤の半反応式、化学平衡と質量作用の法則を原理面からとらえて、応用問題に当たるようにする。
- 化学反応式・計算式に工夫。
- [1][2]の解答欄が1題あたり実質B5判程度であり、そこへ途中計算式や化学反応式などを記述することになる。常日頃から解答に至る筋道と要点をつかんだ答案作成に気を配り、設問ごとに化学反応式、未知数と計算式、解答と単位の3点が明確になるように意識する。
- 赤本での解答の分量などを参考にして、答案づくりの対策をする。
②無機分野
- 図説などを多用する。
- 各種結晶構造や金属イオン分析、要素の昇華実験、アンモニア錯イオンの構造などは視覚的・立体的にとらえられる特徴がある。
- 各種電池、気体発生装置、無機単体や化合物などは実験図や模式図を参考にして知識を確実なものにする。
- 新素材、環境問題に関心を持つ。
- 大気汚染と二酸化炭素、排ガスとしての硫黄酸化物SOx、窒素酸化物NOx、クリーンエネルギーとしての水素合成・水素吸蔵合金などが近年、環境面から注視されている。
- アモルファス、セラミックス、機能性高分子などの新素材分野にも関心を持っておきたい。
③有機分野
- 未知物質の構造決定は頻出
- 異性体と構造決定の出題がよく見られる。
- 各種検出反応は、反応の仕組みをとらえた上で理解する。
- 不斉炭素原子数と鏡像異性体の数や左旋性(L体)、右旋性(D体)の立体構造もしっかり理解しておきたい。
- 高分子化合物は重要
- 特に天然高分子化合物についてはよく取り上げられており、内容的にも難度の高いものがみられる。 ⇒近年、アミノ酸やタンパク質関連の研究でノーベル賞受賞者が続いたことから脚光を浴びている分野でもある。
- DNA、RNA関連分野である糖類、アミノ酸類、リン酸および油脂などは内容的にかなり深い理解が要求される。 ⇒教科書・参考書のほか、ニュースなどで話題になっている発見や研究についても興味をもって目を通すようにしておく。
【生物】
傾向
データ解析と未知のものに対する柔軟な発想を!
思考力・的確な表現力が求められる
| 出題形式 | 大問3題(実質的には5~7題程度の出題量) |
|---|---|
| 試験時間 | 例年、理科2科目で150分 |
| 解答形式 | 空所補充問題、下線部についての知識事項を問う選択問題、下線部の内容や意義を説明する論述問題、原因を追究する論述問題が中心。論述問題の総論述量は2023年度は20字以内の字数指定のあるものを加え、24〜28行程度。他に、グラフの作成が求められる描図問題、計算問題(途中の計算過程は求められず、計算の結果のみを記す問題が中心)。 |
出題範囲
- 生物基礎・生物
頻出分野
- 遺伝情報…バイオテクノロジーなどの最新遺伝子分析を題材とする問題で、いずれも思考力を要求するものが出題されている。
- 細胞、代謝
- 体内環境、動物の反応…体内の濃度調節(イオン、血糖量など)は頻出。
- 植物の反応
- 生態、進化・系統
出題内容
① 実験考察問題:オリジナリティの高い問題で、他大学に類題をみることは少ない。
- 実験設定
- 実験操作の意味づけ
- 仮説の検証
- 実験結果の予測
- 与えられた実験結果やデータからの考察
- 新たな実験設定
などがあり、実験データをつなぎ合わせて背後に潜むメカニズムを推測し、ストーリーを構築することが要求される。
② 計算問題
- 柔軟な発想と論理性を問うものが出題されている。
- 結果のみを記述するものが多い。
- 直接計算結果を求めるものではないが、解答にあたり計算が必要な問題もある。
- 典型的な問題や、リード文で定義した条件に基づいて計算する問題。
難易度
- 知識そのものは高校の教科書をよく踏まえたレベルの問題であることが多く良問。教科書に記載のない内容の場合は、リード文中にその言葉の定義をきちんと述べてあるが、取り上げられたテーマのほとんどが、受験生にとっては初見のものであり、かつ非常に長いリード文を読むことが要求されることを考慮すると、やはり難問といえるだろう。
- ただし、時間をかけて問題を熟読すれば、解法のヒントとなる文章が必ずと言っていいほどきちんと記載されているので、考える習慣のついている受験生は解答できるような問題となっている。
対策
① リード文対策
- ポイントとして、以下の二つに分けられる。
- 「掘り下げなくても解答できるもの」
- Ⅰのリード文(〔文1〕)の大半がこのパターンに当てはまる。基礎事項の確認という意味合いで出題されているので、まずは軽く読みこなせばよい。
- 「じっくり読まないと解答できないもの」
- Ⅱ以降のリード文(〔文2〕以降)で多く見られる。
- ここでは、途中で重要な語句だとわかったら、メモを取ったり、アンダーラインを引いたりして注意しておく。
- 「掘り下げなくても解答できるもの」
- 実験の目的などを把握しておく。
- 設問の内容をあらかじめ見ておき、何について問われているか知っておく。
② 論述対策を早くから行う。
- 実験考察問題の解答様式は、多くが1〜3行程度で記述する論述式。
- 何を省き、何を記述するかということを自分なりに判断して書く。
- 作成した解答を信頼のおける先生に添削してもらうことが効果的。
- 定評のある論述問題集などを活用する。
③ 過去問で実験考察問題対策を
- 東大の考察問題は他大学に類を見ない独創性に富む問題からなるため、参考にできる問題は少ない。
☞オススメ参考書:難関校過去問シリーズ『東大の生物 25カ年』(教学社)
どのような問題が出題されているのかを実感としてつかむ。
1回目…時間を気にせずに十分時間をかける。
2回目…ある程度時間を設定して解答してみる。
point!
重要なのは、ただ解くだけではなく、必ず解答例・解説を読み込んで、どのように考えて正解を導き出しているかを理解しておくこと。
④ 科学的な思考方法を身につけ、理解を深めておく。
- 科学的思考とは…与えられたグラフや表などから、論理を展開するのに必要な情報を導き出し、生命現象と結びつけ矛盾しない解釈を行うこと。さらに、必要に応じて、仮説を自分で立て、検証することも重要な作業。
【地学】
傾向
説明文・図からの考察問題主体、計算量も多い
全体を見通し、できる問題から確実に解く
| 出題形式 | 大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 例年、理科2科目で150分 |
| 解答形式 | 計算・論述法がかなりのウエートを占めているのは従来どおり。
計算問題は毎年出題。論述も多く分量の指定は1〜5行程度の行指定が多い。1行は35字。他に、読図に関する出題、描図問題など。 |
出題範囲
- 地学基礎・地学
- 内容的には、地学の知識を問うだけでなく、数学・物理・化学的手法を用いて考察させる問題もあり、特に数学、物理についての基礎的な知識が必要なことが多い。
難易度
- 全体的に難度は高い。
- 例年、問題量が多く、問題解答にあたっては、問題に難易差があるので、最初にどの問題から取り組むかよく見きわめることが重要。計算問題は重要で、量的にも多い。有効数字や単位にも気をつけてミスをしないことが大切。
- 初めて見るであろう題材を扱う問題も多く、全体的に難度は高い。さらに問題文が長いため、より難しく感じる問題もあるが、問題文をしっかり読み、落ち着いて考えれば解答の道筋が見えてくる。思考力・理解力を総合的に問う良問が多い。
対策
①基礎知識の充実
- 個別的な知識の集積だけでは対応しにくい問題も多い。関連性を重視し、数学・物理・化学的にも裏付けし、1つずつ論理的に納得しながら知識を確実なものにする。
- 教科書を中心に資料集なども利用し、読図や描図をしながら体系的に学習する。
- 論述対策:原因・関連性・探究方法・相違などについて30〜200字程度でまとめる練習をする。
- 計算問題対策:対数や三角関数の計算、有効数字の扱いなど。
- 宇宙や地球科学関係のテレビ番組や記事に注意する。新書などに目を通す。
- 日頃から幅広く興味をもち、偏りなく学習して、知識の幅を広げておく。
②出題項目と学習のpoint!
- 宇宙…毎年、大問1題が計算問題を伴って出題される。
- 太陽放射と地球への影響については必ず整理して理解しておく。
- 惑星現象、会合周期、ケプラーの法則、恒星の光度、HR図、連星、変光星、銀河系、ハッブルの法則などはその内容とともに、典型的な計算問題も習熟しておくこと。
- 対数関数の知識が必要な計算問題も出題されるので、十分練習しておく。
- 恒星の一生や宇宙の進化などについてもまとめておく。⇒恒星に関しては質量や内部構造の変化、元素の形成などとも関連づけて理解する。
- 全体として、物理の基礎学習が必要。特に基礎的な力学はぜひ学習しておきたい。
- 大気・海洋
- 毎年出題されている。図の読解が必要な出題も多く、計算問題も複雑なものが多い。
- 内容は、海水の熱輸送、波、二酸化炭素の輸送、水収支、海水位の変化、海洋と大気の相互作用など多彩。転向力・エネルギー収支・凝結・起潮力など量的に扱う分野は計算問題も含めた習熟が必要。
- 高層天気図と地上天気図の関連。
- グローバルな気象(例:酸性雨やエルニーニョ、ラニーニャ等)については教科書の記述だけでなく、地球環境についての一般図書などで知識・教養を深める。特に大気と海洋の相互作用は重要。
- 地球
- 地球の内部構造や状態、地球の大きさ、地震活動と地震波解析、重力異常、地殻熱流量、地球の誕生過程、他の惑星との比較などについて⇒関連性・相違・探究方法などに留意しながら学習しておく。
- 鉱物・岩石
- 代表的な岩石については分布の特徴・産状・成因・組織・鉱物組成・化学組成など、造岩鉱物については、化学組成・多形・固溶体、結晶の化学的・物理的性質などをまとめておく。
- 図の見方や地学的意義の把握、化学計算、分析値に基づく計算などにも習熟しておく。
- 探究活動が重視される関係で、実験・観察に関する問題もみられる。
- 地質・地史
- 図表などを用いた出題が多く、地質図・地質断面図・ルートマップの読解や描図練習を十分にしておくこと。
- 地質図作成の知識も身につけておく。
- 不整合・示準化石・示相化石などについてはその地学的意義をよく理解しておく。
- 絶対年代の測定法についても理解しておく。 ⇒探究活動が重視される現在の理科の特徴が出題に反映されやすい分野でもあり、地質調査などについても十分学習しておく必要がある。
- 先カンブリア時代の地史に関しても、近年教科書の記載内容が増えているので要注意。
- 自然現象に対する幅広い知識と洞察力だけでなく、図表の分析・読解力、応用力、計算力、表現力などが試されている。教科書の内容をそのまま出題するのではなく、考える力を見る問題が多い。
【日本史】
傾向
設問の意図を深く読み取る力が求められる
簡潔な表現力・文章力を鍛錬しよう
| 出題形式 | 大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 世界史・地理のいずれかと2科目で150分 |
| 解答形式 | 例年、全て記述問題。解答用紙は地歴共通で、1行30字マス目。
制限字数は、大問1題あたり5〜6行程度。総字数は、630〜660字。 |
出題内容
- 〔1〕古代・〔2〕中世・〔3〕近世・〔4〕近現代というのが原則。史料問題は問題文や設問の中で引用されることもある。史料は現代語訳したものが用いられることが多い。
- 〔古代〕律令体制と文化史・外交史に関する出題が圧倒的に多い。特に、律令国家の地方行政や官僚制、軍事性のあり方を通じて、大化前代・律令国家形成期・展開期・摂関政治期を考察させる問題がよく見られる。
- 〔中世〕鎌倉幕府の成立・展開や御家人制・惣領制、室町時代の特色である国人一揆・惣村・自治都市・戦国大名などの出題が多い。文化史では、仏教の動向や文化の特徴を問う出題が目立つ。
- 〔近世〕政治史では、幕藩体制の構造とその展開、そこにみられる支配秩序が繰り返し問われている。社会経済史では村請制に基づく村の自治と支配、内外の動向と絡めた経済発展が良く問われている。文化史は、対外関係や経済発展の在り方と関連、学問の発展について。
- 〔近代〕政治史では、明治憲法体制の構造とその展開は頻出テーマである。外交史は、対欧米・対アジアの姿勢が共通の問題意識としてしばしば認められ、内政・軍事・経済と関連付けての学習が必要。経済・産業史は、産業革命、大戦景気、恐慌の連続、井上財政と高橋財政、戦時経済といった時期ごとの特徴をグラフや史料から読み取る出題。
- 〔現代〕新憲法・農地改革・教育改革など戦後改革。1960年代までは確実に学習しておきたい。
難易度
- 論述という形式については、いくつかの小問に分けるなど書きやすくする工夫がなされており、近年は教科書レベルのまとめやすい問題が目立っている。
- ときおりユニークなテーマもみられ、問われている内容もしばしば高度なものに及ぶが、必ず資料文などにヒントが用意されているので、それらを吟味してキーワードを探り、慎重に出題意図を考えれば、おのずと解答の方向性がみえてくるはずである。
対策
①教科書が基本
- 細かい事項の暗記に努める必要はなく、歴史の大きな流れを把握することに重点を置き、歴史の重層的な構造について理解を深める。
- 主題別にまとめたり、似たものを対比させたりするとよい。
- 教科書における各章の導入部やトピックス的な部分にも注意。
★東大入試においても「教科書が基本」。山川出版社の『詳説日本史』『新日本史』の執筆陣には東大の教員らが名を連ねている。この2冊を用意した上で、各時代の特色の変化、いわゆる「流れ」をつかむために読み込むことが大事。
②論述の練習
- 全問字数(行数)指定、字数制限が厳しい。
- 小問ごとに解答を書き分けるにも工夫が必要。
- まずは市販の問題集で論述問題を解いてみる。
- その上で、赤本に掲載されている過去問はすべて解き、東大の日本史の雰囲気と解答方法に慣れておく。
- 問題の設定から注意深く意図を読み取り、与えられた資料を十分に生かした解答を作ることを心がける。
- 先生に添削・講評してもらい、なおかつ本書の解説を熟読し、もう一度解き直す。
☞オススメ参考書『東大の日本史25カ年』(教学社)
③ 広い視点の涵養…東大の日本史のポイントは『新たな視点に気づくこと』
- 学習の際に常に問題意識を持ち、素朴な疑問から発想を広げ、史実に有機的に関連させていく姿勢が期待されている。
- 読書などによって広い視点を涵養してしておくと役に立つ。
☞オススメ:岩波新書・中公新書・講談社現代新書などの新書類、「日本史リブレット」シリーズ(山川出版社)
東大の教員によって書かれたものにチャレンジするのもよい。
★新たな視点…
歴史にはさまざまな視点があり、歴史学は日々進歩しているが、教科書にそれらを盛り込むのはなかなか難しい。東大では、教科書が十分に書き切れなかった、そうした視点を好んで出題する。
そのため、資料文・史料文・年表・系図・グラフ・指定語句などがヒントとして与えられており、それらを適切に活用すれば教科書的な知識と理解で解答できるように工夫されている。
【世界史】
傾向
〔1〕はグローバルな視点で考察する論述問題
〔2〕〔3〕は手堅く得点することが必須
| 出題形式 | 例年、大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 日本史・地理のいずれかと2科目で150分 |
| 解答形式 | 〔1〕は長文論述(字数は600〜660字、使用語句が指定されている)。 〔2〕は30~120字の小論述、小論述数問、記述問題が数問
〔3〕は記述主体、語句を記述する問題がほとんど。 ※小論述を含めた全体での字数は、930〜1080字と年度によりかなりの増減がある。 |
出題内容
- 教科書でいうと、満遍なく、どこからでも出題される可能性がある。
難易度
- 教科書や用語集のレベルを超えた出題はほとんどない。
- 長文論述問題はスケールの大きいテーマが設定され、幅広い知識と正確な理解が求められるため難問といってよい。
- 小論述・記述問題は、大半は教科書・用語集の知識で対応できる標準レベル。
- 小論述・記述問題で確実に得点し、長文論述問題でどれくらい得点を上乗せできるかが合格の決め手になるだろう。
対策
①教科書の精読から始める
- 教科書に記された事項を正しく理解することこそ学習の土台となる。
教科書の精読とは…
1つの歴史事項に出合ったら、それが教科書のどこに記されているかがすぐわかり、歴史の流れの中でどのように位置づけられるかがすぐ思い描けるくらい読み込むことである。
※本文だけでなく、脚注や地図、図版・写真の視覚資料にも注意。そのようなところにこそ、問われるポイントが潜んでいることも多い。
その上で、よくわからない箇所(「なぜそういえるのか」「どういう意味なのか」など)に出合ったら、それを用語集や資料集・参考書を利用して調べていく。
⇒知識は増大し、長文論述や小論述にも対応できる力も身につくはずである。
☞東大向きの地域交流や社会経済史への言及が充実している『世界史B』(東京書籍)や『世界史B』(実教出版)を併用したり、『世界史用語集』(山川出版社)などの用語集で自分の使用している教科書では取り上げられていないような歴史事項を確認・理解する。
②長文論述対策:テーマにおいて大きく分けて次の2つのパターンがある。
(1)一国(一地域)を対象とした論述問題対策
- 問題の指定語句を手がかりに、教科書のあちこちで記されている当該国(当該地域)に関する部分を導き出し、それを設問に沿って連結させる。指定語句を時系列に沿って並べ、それぞれの語句から推測される状況を想起し、文章化する。
- 教科書などから設問に対応した部分を導き出せる力の育成が必要。 例えば…ポーランド、朝鮮といった国の通史の学習は、教科書でとびとびに記述されている部分を自分で探して簡単な年表を作ってみる。
☞オススメ参考書『各国別世界史ノート』(山川出版社)
(2)グローバルな視点を必要とする論述対策
- 論述対象となる国家(地域)が複数であることから、地域と時代をどうやって構成するかについて、指定語句を「分類」し、論述の構図を決めてから文章を書くとよい。
- 設問の要求と指定語句を「分析」した上で論述しなければならない。
- 指定語句を「時代ごと」または「地域ごと」にまとめてみると書くべき内容や構成が見えてくることが多い。
③ 小論述・記述問題対策
- 教科書・用語集レベルを超えて出題されることはほとんどない。対策①の教科書の精読を全範囲(教科書の最初から最後まで)にわたって行う。
- 教科書や用語集でつい読みとばしがちな部分にも問われるポイントが潜んでいることもあるので、その点を意識して学習する。
- 重要事項や事件の原因・経過・結果などを常に30字(ないしその倍数60字・90字・120字など)でまとめる練習をしておく。
④ 赤本シリーズの活用
- 過去問を解く
- 長文論述問題において「何を書いてよいのか」思い当たらない場合は、まず教科書などで調べる。そしてその後、教科書などを伏せて書いてみる。
- 答案作成後、小論述・記述問題は模範解答を見て、できなかった箇所を教科書などでチェックしておく。
- 長文論述問題については解答例と見比べ、抜け落ちている箇所、説明不足の箇所を発見し、教科書などでその部分を確認する。
- 自分の答案を先生などに添削してもらう。
- その後、もう一度、長文論述問題を見直し、出題者の意図、何が問われているかを再確認する。
- 赤本シリーズを利用して類似の問題にあたる。
- 京大・一橋大・名古屋大・九州大など。
☞オススメ参考書『東大の世界史25カ年』(教学社)
【地理】
傾向
資料の分析による地理事象の理解力を問う
短文論述に対応できる要点把握力の強化が必要
| 出題形式 | 大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 日本史・世界史のいずれかと2科目で150分 |
| 解答形式 | 論述法が小問の多くを占め、制限字数は60字を中心に30〜90字。
記述法(地名や用語を答える)、選択法(資料類の読み取りに多い)。 |
出題内容
- 正確な知識をもとにした思考力を問う問題や、各種資料を読み取る力が試される。また、自然と人間の関係についての問題は頻出。現代の地理的課題を問う問題も目立つ。日本に関する問題は必出。論述問題では簡潔さが求められる。
難易度
- ここ数年間を平均してみると標準ないしやや難のレベル。
- 一見難しそうにみえても、学習した知識をもとに地理的に考えれば十分に正答が得られる問題なので、「覚えていないのでお手上げ」なのではなく「考えれば簡単」という面もある。求められているのは、地理的な判断力や思考力、さらには地域の現状と将来を見通す洞察力なのである。
対策
① 基本事項を確実に自分のものにする。
- 教科書を確実にマスターするとともに、地名の位置や地理事象の分布を地図帳で押さえておく。
- 『地理用語集』(山川出版社)…用語の意味や事例を確認
- 『新編 地理資料』(東京法令出版)他の副読本…知識の幅を広げる。
② 地理的思考力を養う。
- 「地理事象の特徴を知る」「事象の分布とそれが生じた背景を考える」「事象間の相互関連性や地域による共通点と相違点をさぐる」などに力点を置いた学習を心がける。
- 自然環境と人間活動の関係を考える。
- 地形、気候だけだなく、植生、土壌、水環境などを幅広く学習する。
- 現代的諸問題への理解を広げる。
- 世界各地の地理的諸問題について、どこで、何が、どのようにみられるか、その理由は何かなどに気をつけておく。いわゆる時事的な事柄にも注目する。
- 生活に関連する事項に注目する。
- 都市や人口、食糧問題、人々の暮らしなど、人間生活に関わる事項に注目する。
- 政治や経済、社会の変化が地域の特色としていかに表れるか、地域の特色が暮らしにどう反映されているかに焦点が当てられることが多い。
③地域別の特色をまとめる。
- 日本に関する問題は、必ず出されると考えておいたほうがよい。
- 自然環境をはじめ、産業・人口・都市の問題が多い。
- 経済や社会の年代による変化もよく出されるので、各年代を知るキーワードをもとに流れを理解しておく。
- 地域別や都市・農村別、大都市圏と地方圏、都心と郊外などの区分をしてみる。
- 地域単位のまとめをする。
- 設問や小問に地誌的内容が出されたり、地域を決めて系統的な項目が出題されることが多い。
- 特色のある地域については、自然環境や民族の動向、産業の特色、ヒト・モノの動きなどを整理しておく。
- 発展途上国・地域に注目
- 資源問題のように国際関係と関わるもの、食糧問題や人口・民族問題など地域事情と関係するものの両方に気をつけたい。
- 特に注意したいのはアジア諸国で、なかでも中国は、経済発展の実態とその社会的影響の面から学習を深めておく。
④統計・地図・グラフなどに強くなる。
- 地域の特徴を考えさせる材料として出されるので、数値などを覚えるのではなく、全体的な傾向から地域や地理事象の特色を読み取れるようにしておくことが大切。
- 地図については、常に地図帳を手元に置き、世界地図や大陸・主要な島などの地図が頭の中で描けるようにしておくほか、地名の位置や地理事象の分布を確認する。
- 地形図については、等高線から地形がイメージできるようにするなど、読図の練習をする。
⑤コンパクトな論述の練習…まずは30字程度の短文でまとめができるようにする。
- 使用語句が指定されている場合もあるので、2〜4個程度のキーワードを決めてから書いていく練習をする。
- 地理事象を説明する、その分布や要因をまとめる、地域ごとの特色やいくつかの地域の共通点・相違点を述べてみる。統計表や地図などから読み取った事柄を文章にしてみるなどが効果的。
⑥過去問に学ぶ。
- 同じ内容が繰り返し出題されることはほとんどないが、よく似た事象が間隔をあけて出されることや、テーマや出題姿勢、出題形式に類似性が見られることがある。
- テーマを別の視点でとらえ直すため、また論述問題などの形式に慣れるために、過去問に学ぶ意味は大きい。
- 資料類の読み取り練習には、これまでに出題された統計表やグラフなどに目を通し、問題を解いてみるのが効果的である。
☞オススメ参考書『東大の地理25カ年』(教学社)
【国語】
傾向
現代文は自分の言葉も必要となる 古文・漢文は標準的な良問
| 出題形式 | 理科:現代文1題、古文1題、漢文1題の計3題
文科:現代文2題、古文1題、漢文1題の計4題 ※〔1〕現代文〔2〕古文〔3〕漢文は共通問題。〔4〕現代文は文科のみの出題 |
|---|---|
| 試験時間 | 理科:100分、文科:150分 |
| 解答形式 | 全問記述式 |
出題内容
- 現代文〔1〕
- <本文>例年、抽象度の高い論理的文章が出題されている。
- <設問>論旨をきちんと把握できているかどうかを問う説明問題が中心。本文全体の趣旨(諭旨)をふまえて100字以上120字以内でまとめる設問が定着している。漢字の書き取り(音・訓含め)も例年3問ずつ出題されている。
- 現代文〔4〕
- <本文>感性的文章と論理的文章の両方が出題されているが、2014年度以降は随筆が連続している。
- <設問>〔1〕と同じく説明問題が中心。感性的な文章では比喩表現の具体的な説明や筆者の表現意図を問うものが目につく。
- 古文
- <本文>標準的な文章が出題される。出典は中古と中世が中心。ジャンルは、物語系の作品が多い。
- <設問>口語訳を中心に本文全体の主旨や部分の理解を説明問題で問う、典型的な記述型読解問題。
- 前後の文脈をふまえた人物の心情を説明する問題がよく出題されている。
- 和歌に関しては、修辞そのものを問う問題は少なく、詠まれた状況や詠み手の心情に即した解釈を問うものが主体。
- 漢文
- <本文>史伝や経書、思想、文章、説話などの出題が多い。
- <設問>例年の傾向として口語訳中心の問題構成。口語訳の延長として、心情や状況などの具体的な説明も求められる。解答欄の大きさから推定して、ポイントを絞った要約力が問われている。
難易度
- 現代文:年度により難易度にやや揺れがあるが、かなりの読解力と知識・教養が必要。時間配分は〔1〕が40分、〔4〕が30分がひとつの目安。
- 古文・漢文:標準的な問題。時間配分は〔2〕が35分、〔3〕が30分が目安。
対策
〔現代文〕
①論理的思考力
- 人文科学・社会科学・自然科学など各分野の評論文を幅広く読んでおく。教科書以外にも、新聞の社説や論文、文芸雑誌、新書や文庫、単行本など。
②豊かな感性の育成
- 論理的思考力とともに感性の豊かさ、鋭さを養う。
- 教科書や新書・文庫などを利用して韻文や随筆、小説などに数多くふれる。
③表現力の養成
point!
以下に注意して問題集や赤本で訓練する。設問で問われやすい箇所である。
- 抽象的表現を具体的表現に
- 比喩表現を普通の表現に
- 本文のキーワードとなる語句の意味を具体的に
- 反語など修辞を使った表現を率直・簡明な表現に
- 省略された意図を明らかに
- 倒置された因果関係を本来の順番どおりに
④ 表現力の正確さ
!実際に文章を書いてみた後で、必ずチェックしよう!
- 誤字・脱字がないか
- 主語と述語、修飾語と被修飾語が正しく対応しているか
- 副詞や助詞などの使い方が間違っていないか
- 読点のつけ方が適切か
※古典も同様にチェックすること。
〔古文〕
①基礎的知識:単語と文法をマスターすること!
【単語】 ① 陳述の副詞 ② 古今異義語 ③ 多義語 ④ 慣用表現
【文法】 ① 助詞・助動詞 ② 敬語 ③ 紛らわしい語の識別
※以上の知識を、読解の前提として身につけなければならない。
②古典常識
- 設問は、内容読解に終始しており、適切な注がついてはいるが、古文の世界観や一般的宗教観、風俗、暦、有識故実などの古典常識についての一定レベルの教養は必要。
- 現代語訳または小説化されたものなどで一度なじんでおくのもよい。
③口語訳・内容説明
- 口語訳:基本的には正確な逐語訳をする
- 内容説明:傍線部を文脈を補って説明する。
- 必要に応じて、指示内容や省略された主語・目的語・述語を補う。現代語の表現として自然な言葉になるように注意。自分が読み手になっても理解できる文を作るよう心がける。
〔漢文〕
①基礎の充実で確かな読解
- 主語を補いつつ本文の流れを正確に押さえる読解力が問われる。
- 難解な文章は出題されないから、まず教科書の復習を中心にする。
- 訓読に慣れ、漢文を正確に素早く読めるようにする。
- 訓読の基本法則、再読文字、返読文字、助字、基本句形、多義(多読)語を確実にマスターする。
- 内容の理解に関しては、疑問、反語、抑揚、感嘆、否定の表現に注意。
- 漢文の背景となる思想や歴史などの知識を学んでおくと、読解の助けになる。
②口語訳:日本語として意味の通じる訳文を書く練習をする。
- 漢文はたとえ話や比喩表現が多く、また文章が簡潔なので、解答では適宜言葉を補って訳す必要がある。
解答用紙
- 解答用紙の指定の枠内に記入する方式。説明問題の1行の長さは13.5㎝程度、幅は各行とも約9mmとなっている。1行の枠内に2行以上書いたり、枠をはみ出したりしないこと。逆に空白が多すぎるのも望ましくない。解答分量は1問につき1〜2行。「ことばを補って」「わかりやすく説明」「平易な現代語に」などと示されている設問では、スペースを考えるとポイントを絞ってまとめるのに苦労するかもしれない。























































