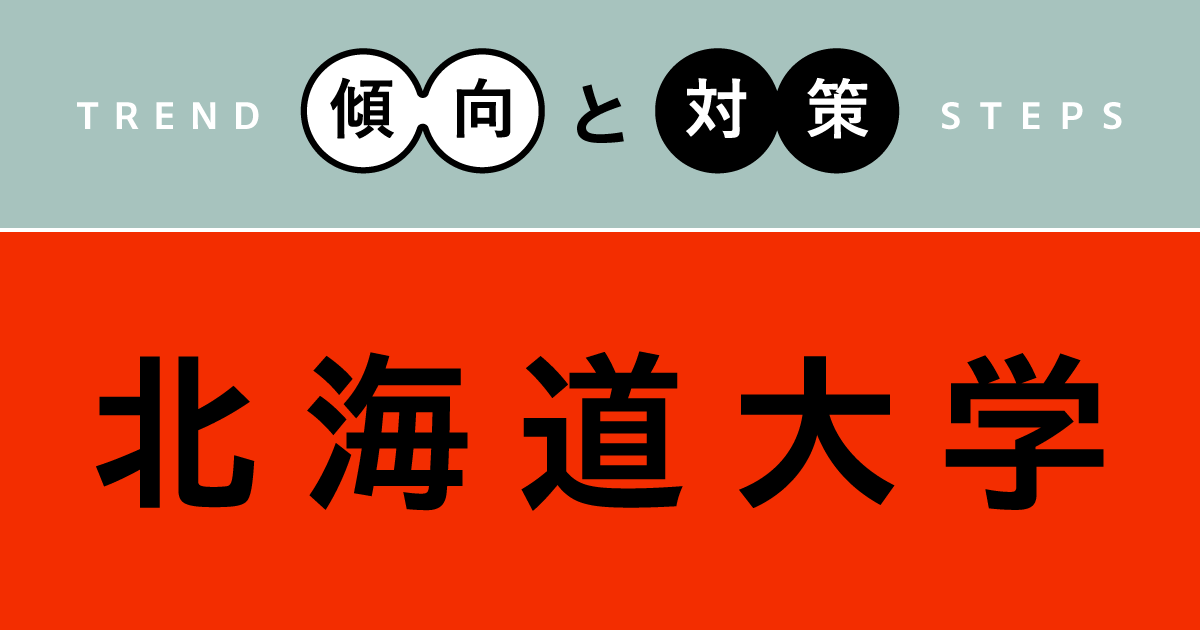
傾向と対策(前期日程)
2023年度までの前期日程の入試問題を分析しました。さらに詳しい最新の分析は「大学赤本シリーズ」をご覧ください。
【目次】
【英語】
傾向
読解を中心に総合力を問う、プラス英作文の力がモノを言う!
| 出題形式 | 大問4題(読解2題、読解・英作文1題、会話文1題) |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 記述式(英文和訳、内容説明、意見論述など)、選択式(同意表現、内容説明、内容真偽、空所補充など) |
出題内容
①読解問題
- 社会・文化・科学などに関する評論文、随想的な文章など、幅広い分野の英文が取り上げられている。
- 設問では、文脈を考慮した内容理解が問われる傾向にある。
- 読解英文の分量は、2023年度は2題合せて1600語を超えている。
②読解・英作文問題
- 英文を読み、それに関する内容説明や段落の要約文の完成及び意見論述という構成。
- 内容説明は、本文の内容に合うように英文を完成させる空所補充形式。
③会話文問題
- 会話文の内容を要約した英文の空所を選択肢から補充するという問題。
- 例年は、12の空所に対して24個の選択肢が一括して与えられる形式。
難易度
- 試験時間に比べて読解英文の量が多く、意見論述に少し手間取ると思われることから時間配分がポイント。ただ、読解英文の難易度自体は標準的で国公立大二次試験の問題としてはそれほど高くない。
対策
①まずは語彙力! コツコツと繰り返し単語・熟語を覚えよう
- 読解練習の中で出てきた単語・熟語をノートに整理して覚えていく。
☞オススメ参考書『システム英単語』(駿台文庫)
②長めの長文(800語程度)を、ポイントを押さえながら読み進める練習を
- 試験時間が限られているので、精読の速度を上げていくことも重要。
☞オススメ参考書『大学入試 ぐんぐん読める英語長文〔STANDARD〕』(教学社)
point!
- よくわからない語句や表現に出くわしても文脈から推測できる読解力を身につけること
- 指示語が何を指示しているのかに注意を怠らないこと
- 倒置構文や省略のある文には特に注意すること
☞オススメ参考書『大学入試 ひと目でわかる英文読解』(教学社)
③記述力・表現力の養成
- 英文和訳・内容説明など、記述式の問題が多く出題されるので、解答を適切な日本語でまとめる練習をする。
- 自分で解答を書く練習をし、出来上がった解答は必ず読み返し、日本語としておかしいところはないかチェックする。
④英作文に習熟する
- 文法・構文の知識を確実に身につける(これは読解や会話文の問題への対策としても重要)。教科書や参考書に掲載の重要例文のまるごと暗記も有効。
⑤意見論述は実際に書く練習を積み重ねることが大切!
point!
- 英語にしやすい日本語で考える。
- 理由や利点・欠点などの「具体的な根拠」を明確にする
- 自信のある語彙・構文を使って表現する
⑤会話文問題はかなりの長文
- 内容的にも時事的テーマを含んでおり、会話より議論に近いものがある。
- 長い会話文の読解にも挑戦し、会話や議論の展開の仕方、それぞれの人物の主張の論点やその変化についても正確に把握できるよう、練習しておきたい。
- 語法と品詞運用の力も問われるので、空所を含む文の構造から、空所にはどの品詞の語を入れるべきかを判断する練習を積む。
【日本史】
傾向
簡潔にまとめる論述力で差がつく
史料が多出、読解力・分析力が試される!
| 出題形式 | 大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 記述・論述問題中心、2021〜2023年度は選択問題も出題されている。 |
- 論述問題は例年比重が大きく、10問以上出題されている。1問当たり20〜90字程度。また、字数制限のない形式でも出されている。
出題内容
時代別
- 各時代が網羅されており、各大問が複数の時代にわたることもある。全体的に近現代重視の傾向。
分野別
- 北海道大学の立地と関係の深い北海道や北方領土に関連する問題が多数見られる。また、北海道と同様、独自の歴史を持つ沖縄(琉球)の歴史も頻出。
- ほかに、頻出テーマとして
- 幕末の対外関係と開港の影響
- 地方統治に関する諸問題
- 東西市・官位に関する問題など律令体制について
- 平安初期の律令地方支配の崩壊や近代の社会主義など
- 全体的に、歴史の流れを展望する政治分野を中心に、外交・経済も視野に入れた総合問題の形式が通例である。
- 文化史は、差のつく分野。特に仏教などの宗教史や儒学・洋学などの学問史に注意。
史料問題
- 大問の半分以上は史料を利用した問題。
-
難易度
難易度は全体としては標準的なレベル。教科書本文程度の内容で構成されており、難しい場合でも脚注レベルと考えてよい。 - 史料問題では読解力と分析力が必要。90分という試験時間で数多くの論述問題を簡潔にまとめる必要があるので、決して易しいとはいえない。短時間で要点をまとめる論述力が要求される。記述問題との時間配分の工夫も必要。
対策
①教科書の学習が基本、 教科書の徹底整理を
- 特に太字で表記されている重要事項については、前後の文章から歴史的位置づけをしっかりとらえ、できれば用語集などの説明文を読んで理解を深めておく。
- 近現代史が重視されている傾向を踏まえ、塾や予備校の近現代史の講座の積極的利用もオススメ。
②政治史・外交史・経済史・文化史の整理と分野間の連係理解
- それぞれの分野ごとに整理した上で、違う分野の内容を見比べながら勉強してみる。
- 各分野を通史的に見通す力と、同時代のいろいろな分野を総合的に見る力があいまって、しっかりした歴史的な理解が形成され、そうした力が、論述対策の仕上げにもなるだろう。
③論述対策! とにかく文章を書くことから始めよう。
- 例年必ず出されており、対策は必須! 短文のものからある程度まとまった内容(を論述させるものまで、多様な論述力が要求される。
- 字数が少ない場合 ⇒ 簡潔かつ的確にまとめとめる力
- 長文の場合 ⇒ 文章の構成なども考えた表現力
- 日頃からオリジナルノート等をつくり、まとめる練習をしておく。
- 特に著名な事件・法令・条約などについてはその背景・内容・結果などを字数にこだわらず、簡潔にまとめる習慣をつけておこう。
④史料文の読解力養成!
- 教科書に載っている基本史料や史料集など、とにかく多くの史料を読んでおこう。初見史料が出題されても、設問内容と史料の読解から、出題意図を正確に抽出することができるはずである。
- 史料集の解説文は教科書とは違った角度からわかりやすく書かれており、論述対策にもなるので、史料とともに熟読がオススメ。
⑤特有の北海道史に注意しよう!
- 例年、北海道に関連の深い東北・蝦夷地、北方領土、日露関係史などの出題がみられる。
- 琉球(沖縄)史も頻出。
- 時代ごとに北海道に関連する内容を抽出して整理するのも有効。
⑥過去問の演習
- 過去に出題された内容に類似したものが出題されやすく、問題のレベルを知るためにも「赤本」を利用して過去の問題を解いてみよう。
- その際は、学校の先生などに問題の分析や論述の表現などについて、具体的に添削指導してもらうと効果的。教科書のどのような点に着目して読めばよいか、実感できるようになるはず。
【世界史】
傾向
中国史・イスラーム世界・欧米中心の出題
論述対策を重視しよう!
| 出題形式 | 大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 記述法と論述法が主体。 |
- 論述問題は例年10題以上出題されている。字数指定がなく、解答欄に収まる範囲で書く形式。1問当たり2〜3行程度のものが多い。
出題内容
- 欧米地域:従来は古代ローマ史と中世ヨーロッパが頻出されており、また近世〜現代の欧米諸国史が目立ち、幅広く出題される傾向にある。
- アジア地域:中国史は例年出題されており、イスラーム世界の出題も多い。
- 時代別:古代から現代まで満遍なく出題。欧米地域では古代・中世だけでなく近現代史(南北アメリカ)も重視されている。また、欧米・アジアとも、20世紀の現代史が重視され、第二次世界大戦後も頻出。
- 分野別:政治史と社会経済史が中心であるが、宗教史・民族史・地域史・文化史(政治思想・哲学・文芸・学問)にも注意を払っておく必要がある。
難易度
- 記述問題:教科書に準拠した易~標準レベル。論述問題:標準~やや難。
- 論述問題の分量が多いので、90分の試験時間の配分に留意したい。記述問題から着手し、論述問題にできるかぎり時間をかけるようにしたい。
対策
①教科書・用語集・参考書の活用
- まず、古代から現代まで教科書をしっかり精読しておくことが大切。
☞オススメ参考書『世界史用語集』や『山川 世界史小辞典』(いずれも山川出版社)
※記述・論述法が主体なので、これらを活用し、歴史事項を張り下げた学習を心がける。
- 論述法では歴史事項の経緯や因果関係の詳細が問われる。
☞オススメ参考書『詳説 世界史研究』(山川出版社)/『チャート式シリーズ 新世界史』(数研出版)
※重要事項が体系的に整理されており、論述対策にも役立つ。
②地域別・テーマ別学習
- 古代ローマ史・中世ヨーロッパ史・近現代の欧米史・中国史・イスラーム世界など頻出。
- それぞれ各国・地域別に整理しておく。
- 例)中国史なら 過去問の設問を、王朝・行政機構・土地制度・兵制・社会経済・学問・農民反乱・革命運動・条約などの面から分析し、頻出テーマを抽出してみる作業も有効。
③論述力養成
- 何が問われているかを的確に洞察し、次にそれに応じた内容を過不足なく簡潔に表現することが大切。
- 歴史事件の背景・経緯・結果・影響などの因果関係や流れを体系的に整理し、さまざまな視点から設問に答えられるよう応用力を養うことが必要。
- 出題が予想されるテーマや主題をたてて、歴史事件の推移や意義や影響などをノートやカードにまとめてみる。
- 問題集や過去問に積極的に取り組み、30〜150字程度の字数で簡潔に論述できるような論述力を磨いておく。
④世界史年表・地図・資料集などの活用
- 世界史年表をフルに活用する。
- 主要な諸事件は年代も一緒に覚えると設問に答えやすくなる。
- 論述問題…歴史事件の経緯を答える際に年代整理をしておくと正確な叙述が可能。
- 地図上の確認作業も怠らない。
- 国家・王朝の首都や条約の締結地、戦いの場所や会議の開催地などに留意しながら、それらの位置を確認するよう心がける。
- 地名や都市名を覚えるときは、周辺の河川や山脈・半島なども同時に把握する姿勢が大事。
⑤過去問に挑戦!
- 時間を計って独力で解く ⇒ 出題傾向に慣れ、時間配分の目安をつかむ。
- 模範解答や解説を見ながら、間違ったところやわからなかったところを確認。
- 論述の場合は記述すべきポイントが漏れていないか? 文脈がおかしくないか? 誤字・脱字がないか? をチェック。
- 自分の苦手な分野に早く気づき、そこを重点的に学習しておくことも大切。
【地理】
傾向
地図・地形図・グラフ・統計表など多様な資料利用が特色
| 出題形式 | 大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 論述法・記述法・選択法・正誤法が中心。他に訂正法が出題されたことも |
- 論述法:分量は11〜12問(27〜28行)。字数指定はなく、1問当たり2、.3行のものが多く、1行当たり 25〜30字が目安。
- 記述法:リード文の空所補充の他、小問で地理用語や地名が問われる。
- 選択法:グラフや統計表の国名、品目名などの判定を求めるものが多い。
- 図表の判定問題:地名、用語を選ぶ選択法に比べ解答に時間がかかる。
- 近年では短文から正しいもの(適当でないもの)をすべて選べ、2つ選べなどの形式も増えている。
出題内容
- 統計や主題図などの各種資料を通じて地理的思考力を試す。
- 系統分野は各分野からバランスよく出題。
- 地形図(国土地理院地図)の読図問題は必須。
- 地誌のスケールや範囲は多様。
難易度
- 標準〜やや難のレベルだが、年度によって難易度はかわる。
- 高校地理の範囲を逸脱する詳細な事項が問われることはほとんどなく、問題の大部分は、基本事項に関する正確な知識と柔軟な地理的思考力の有無を試すものである。ただし、一部に時事的な問題や相当踏み込んだ理解を求める難問が含まれることも。地図や地形図、グラフ、統計表などの資料が多用され単なる事項の丸暗記では対応できない。
対策
①基本事項の徹底理解+地図帳・統計集等を活用した学習
- 教科書をしっかり読みこなし、その内容を十分理解すること。
☞オススメ参考書『地理用語集』(山川出版社)
- 地理用語の意味や地名の意義について、正確に理解する。文を書くのが苦手な人は、最初のうちは用語集の説明を書き写しながら確認し理解するといった方法も有効であり、論述法への対策にもなる。
- 学習の際に地名が出てきたら、必ず地図帳でそれらの位置を確認すること! ※例えば
- 都市の場合、その場所の確認+立地(河川沿いか港湾か、山麓かなど)や 他の都市との位置関係等
- 国と国の相互の位置関係や主な経緯線の把握
- 一般図だけでなく統計地図(気候区分図・農業地域区分図といった主題図・分布図)の検討。
- 教科書や地図帳からわかる地域の特色を数値を通じて確かめること。
- 最新版の統計集を手元において、地図帳同様、頻繁に利用したい。
- 重要な統計を、様々な角度から繰り返し検討することが大切。
☞オススメ統計集『データブック オブ・ザ・ワールド』(二宮書店)
※国ごとの要覧も収録してあるので便利
point!
- 系統分野では、教科書記載の各テーマ(自然、産業、都市、人口、環境問題など)が順に満遍なく出題。
- 設問には、気候や地形の成因、工業立地論、都市における機能的地域分化など、各テーマの考え方(理論)を問うものも含まれる。
②地誌学習の充実
- 大切なことは『比較』
- 例)西ヨーロッパの学習では、主要国であるドイツ、フランス、イギリス、イタリアについて ⇒自然環境、産業、社会のそれぞれを比較しながら整理すると、(他国と異なる)その国固有の特色が見えてくる。
- 白地図を利用して空間認識を高める 例)
- 北アメリカの山脈や河川、都市、工業地域など記入
- 英語を公用語とする国を世界地図で塗りつぶす…など
- 学習する地域に漏れがないようにする ⇒教科書では説明が省略されている地域(中米やオセアニアの島国など)があるが、それらの地域も含めて網羅的な学習を。
point!
- スケールは地域の場合と1国の場合があり、範囲では、「環太平洋地域」や「極地方」のような通常の区分に基づかない地域設定もあり、多様。
③地形図読図の問題演習は不可欠
- 基本的事項の確実な習得 ⇒地図記号、等高線の読み方、縮尺の判定、距離・面積の計算など
- 地形図に慣れる ⇒各種地形(扇状地・三角州・河岸段丘・氾濫原など)の読み取り。集落の立地、土地利用など人間生活に関する読み取り。
☞オススメ参考書『入試地理 新地形図の読み方』(三省堂)
point!
- 地形図の読み取り、雨温図・ハイサーグラフ・人口ピラミッドの判定なども頻出。
- 通常の読図問題(地形・土地利用・集落などを関連づけて問う)のほか、景観写真や鳥観図が利用されることもある。
- 関連事項として地誌的な設問が含まれることもある。
④過去問で力試しを
- 論述問題では、設問の意図を正しく理解することが大事。
- 設問の意図を読み取る。
- 解答用紙から字数の見当をつける。
- 解答のポイントを絞り、わかりやすく表現する。
- 図表の判定では、正解へ至るために必要な情報を、短時間かつ確実に見つける能力を高めることが大切。
【数学(理系)】
傾向
標準的問題中心、結果を導く過程が重視される
| 出題形式 | 大問5題。2,3の小問に分けて段階的に解く問題が多い。 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
| 解答形式 | 全問記述式 |
出題範囲
- 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A(場合の数と確率、整数の性質、図形医の性質)・B(数列、ベクトル)
頻出項目
- 数学Ⅰ:2次関数からの出題が多い。
- 数学Ⅱ:図形と方程式、三角関数、指数・対数関数が解法のベースとして活用されることが多い。
- 数学Ⅲ:複素数平面、数列の極限、関数の極限、微・積分法と全分野から出題されている。最重要分野。特に積分法ではかなりの計算力が要求される。
- 数学A:確率からの出題が多い。数列との融合問題が出されることも多い。
- 数学B:ベクトルは内積を含む問題が多い。数列は、漸化式、数学的帰納法に注意。
point!「解答上の注意」
- 採点時には、結果を導く過程が重視されるので、必要な計算・論証・説明などを省かずに解答すること。計算用の下書き用紙は回収されないので解答用紙に必要な事項の記入漏れがないか確認を忘れずに!
難易度
- 全体的に標準問題が多く、受験生の学習成果がよく反映される良問。2022・2023年度と2年連続で難しい内容が出題され、従来より難化傾向にある。
対策
①標準問題をしっかり解くことが合格のカギになる
- 基本事項をマスターしたら、標準問題中心の入試問題集で基本事項を自在に使う練習をする。
- 問題冊子に「結果を導く過程を重視する」と明示されていることからも、論理的でポイントを押さえた答案作成力を養うこと。
☞オススメ参考書『北大の理系数学15カ年』(教学社)
②証明問題に習熟しよう
- 全分野にわたって証明問題の出題がみられるので、練習を十分に積んでおこう。標準問題をこなすことで記述の仕方をしっかり身につけること。
②頻出分野の重点学習
◆数学Ⅰ
- 全分野で活用するという意味で、数と式、2次関数に力点を置く。きめ細かい議論を要求する出題が多いので、論理性を十分意識した訓練が必要。
◆数学Ⅱ
- 他分野での活用に備え、三角関数や対数関数の変形が自在にできるようにしておくこと。
◆数学Ⅲ
- この分野は計算力が即得点力となるから、まず計算力をしっかりつけておくこと。
- 微分法は合成関数の微分、積分法は定積分の計算(置換積分、部分積分)を中心に、確実でスピーディーな計算力を養う。
- 複素数平面についても典型的な問題をしっかり解けるようにしておく。
◆数学A
- 場合の数と確率(特に独立試行の確率)、数列との融合問題に力を入れる。
◆数学B
- ベクトルの図形への応用(内積を含む)、数列の漸化式、数学的帰納法を重視。
【数学(文系)】
傾向
文系としては難度高め!
| 出題形式 | 大問4題。2,3の小問に分けて段階的に解く問題が多い。 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 全問記述式 |
出題範囲
数学Ⅰ・Ⅱ・A(場合の数と確率、整数の性質、図形の性質)・B(数列、ベクトル)
頻出項目
- 数学Ⅰ:2次関数からの出題が多い。
- 数学Ⅱ:図形と方程式、三角関数、微・積分法と幅広く出題されている。なかでも微・積分法からの出題が比較的多い。内容は接線、最大値・最小値、面積などがよく取り上げられている。
- 数学A:確率が頻出。2020年度は整数からも出題された。
- 数学B:数列、ベクトルとも頻出。数列は漸化式、数学的帰納法、他分野との融合問題が多い。ベクトルは図形への応用問題の出題も多い。
point!「解答上の注意」
- 採点時には、結果を導く過程が重視されるので、必要な計算・論証・説明などを省かずに解答すること。計算用の下書き用紙は回収されないので、解答用紙に必要な事項の記入漏れがないか確認を忘れずに!
難易度
- 例年、標準問題を中心にやや難度の高い問題が含まれており、文系学部としては難しい部類である。
対策
①基本事項をマスターしたら、標準問題中心の入試問題集で基本事項を自在に使う練習をしよう。
- 極端な難問は出題されないが、文系としては難しいほうなので代表的な標準問題を自力でしっかり解く力が必要。
- 導出過程が重視されるので答案の書き方にも十分気を配り、図なども普段から正確に描くことを心がける。
- 北海道大学の過去の入試問題に取り組み、出題傾向に慣れておくこと。
②頻出分野の重点学習
◆数学Ⅰ
- 全分野で活用するという意味で、数と式、2次関数に力点をおく。
◆数学Ⅱ
- 図形と方程式は軌跡、不等式を表す領域、微・積分法は接線、最大値・最小値、面積の代表的な問題にしっかり取り組む。
- 三角・指数・対数関数は他の分野での活用に備え、方程式・不等式を重視する。
◆数学A
- 場合の数と確率は独立試行の確率をしっかり学習する。整数についても典型的な問題をしっかり解けるように。
◆数学B
- 数列は漸化式、数学的帰納法、ベクトルは図形への応用を重視する。
【物理】
傾向
典型的テーマによる標準的良問
空所補充中心だが、描図・論述対策もしておこう!
| 出題形式 | 例年、大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 2科目150分 |
| 解答形式 | 空所に当てはまる数式や数値を記述する記述空所補充問題が中心。年度によっては、結果に至る理由などの論述問題や選択問題など。 |
出題範囲
- 物理基礎・物理
頻出項目
- 力学:振り子と円運動、衝突、慣性力に関する問題が多い。
- 運動量保存則や力学的エネルギー保存則は毎年出題されると考えて準備しておこう。
- 電磁気:コンデンサーと電磁誘導に関する問題が多い。
- 熱力学:2022年度を除く、2019〜2023年度に出題。
- 気体の状態変化や分子運動などの熱力学に関する問題は今後も十分出題が予想される。
- 波動:2022年度に弦の振動および回折格子に関する問題が出題されている。
- どの分野が出題されても対応できるようにしっかりと習熟をしておく。
出題内容
- 1つの大問中では、後半に思考や計算を要する問題が配置されていることが多い。
- 誘導的な設問が中心であり、前半には、教科書や標準的な問題集でみられる基本的なものが多く、難しい考え方や複雑な計算を要するものは少ないが、前半で誤ると連鎖的に全滅してしまうこともあるので十分注意が必要。
難易度
- 多くは標準的な題材・設定。個々の問題は誘導に従って解いていくとそれほど難しく感じないが、全体としてみると問題量も多く、正確な計算力やしっかりとした物理的思考力が要求される出題となっている。
対策
①基本事項の徹底が第一
- 誘導的な設問が中心。個々の設問は、物理現象を正しく理解し、基本的な公式を確実に把握していれば十分に対応できる。
- 教科書傍用問題集や標準的レベルの問題集を用いて完全に解答できるようになるまで取り組む。
- 標準的な入試問題集を繰り返し解いて、物理的な原理をしっかりと理解しておくことが大切。ことさら難問に当たる必要はない。
②描図問題、論述問題対策
- 教科書に出てくる代表的なグラフや模式図などは、なにも見なくても描けるようにしておく。
- グラフを書く際には、各軸がそれぞれ何を表しているかをしっかりと意識し、ケアレスミスをしないようにする。
- 2023年度は5年ぶりに字数制限付きの論述問題出題。いつ出題されても対応できるように、文章をまとめる論述練習も必要。また普段から、計算過程は誰が見てもわかるように記述し、説明できるようにしておこう。
③幅広い学習を心がける
- 力学と電磁気は出題比率が高い。この両分野は物理学全体の基礎でもあるので、重点的に学習をすすめよう。
- 熱力学もよく出題されている。
- どの分野から出題されるかは予想しがたいが、波動や原子の分野もおろそかにはできない。
- 基本事項は確実にマスターしておこう。各分野の幅広い学習が有機的に連係して物理的な思考力の養成につながる。
【化学】
傾向
基礎~標準の学力を多角的にみる出題
問題量多め、問題文をよく読み理解することが必要!
| 出題形式 | 大問3題、各大問が独立した2つの問題に分かれている。 |
|---|---|
| 試験時間 | 2科目150分 |
| 解答形式 | 記述・計算・選択問題中心。計算問題は答えのみを示すようになっており、有効数字指定の場合が多いので注意。 |
出題範囲
- 化学基礎・化学
- 理論・無機・有機の各分野から幅広く出題。理論を中心に無機および有機分野と関連させた総合問題も多くみられる。また、問題文の読解力を試す問題もよく出題される。
出題内容
- 理論:すべての分野にわたって出題。化学反応の量的関係など計算問題とともに出題されることが多い。
- 無機:気体、金属、金属イオンの関与する反応は頻出。また単体・化合物の性質は周期表とも関連して出題されている。
- 有機:さまざまな有機化合物の反応と性質、構造の推定が出題され、思考力を要するものも頻出。糖類やアミノ酸・タンパク質の出題も多い。
難易度
- 標準からやや難のレベルと思われる。思考力を要するものが多く出題され、無機・有機分野は理論と関連することも多く、詳細な知識が求められることもある。問題量も多く、問題文をよく読み文意を理解することが大切。
対策
①理論
- 1つ1つの化学用語・法則・化学的概念の中身をよく理解し、化学に特有なものの見方・考え方に習熟しておくこと。
- 反応速度、化学平衡、化学結合と物質の構造・性質、酸・塩素、酸化・還元、電池・電気分解など。
- 計算問題のウェイトが大きいので、基礎固めから思考力の養成に向けて、幅広く練習問題に取り組んでおく。
- 結果のみを答える形式となっているので、正確な計算力を身につけておくことが重要。
②無機
- 主な単体・化合物の性質と反応をよく理解し、正確に把握しておくこと。
- 気体および金属イオンに関するものは頻出項目。
- 理論との関連性に目を向けた理解が必要。
- 周期表と化学結合、酸・塩基、酸化・還元などの分野における関連性には注意。
- 分子の電子式・化学式・化学反応式の記述も頻出であり、教科書にある式は確実に理解しておくこと。
③有機
- 主な化合物の構造・性質・反応をよく押さえておくこと。
- 異性体を含めた構造推定問題が頻出であり、関連問題での練習は個々の物質の性質・反応を理解するためにも役立つ。
- 天然有機化合物は頻出分野、細かいところまで気を付けて整理を。
④実験に関する問題やグラフを使った問題もよく取り上げられる。
- 教科書に出ている実験や、データの図表化の仕方、グラフの読み取りなどに日頃から注意して慣れておくこと。
⑤論述問題対策
- 正確な理解が不可欠。その上で問題演習を行い、実際に書く練習を積み重ねておくこと。
【生物】
傾向
考察力・分析力が問われる
| 出題形式 | 大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 2科目150分 |
| 解答形式 | 記述・選択・論述問題中心で、計算問題も出題される。 論述問題は字数制限のある場合とない場合があり、ある場合は10〜100字程度。2019・2022年度は描図問題も出題された。 |
出題範囲
- 生物基礎・生物
出題内容
- 2023年度は遺伝情報、体内環境、生殖・発生、進化・系統、生態などの分野から出題されており、2022年度と大きく変わらない。大問が複数の分野から出題されることが多い。
難易度
- 2023年度は2022年度に比べ、設問数はやや増加したものの論述量が減少。難易度は2022年度に比べて大きな変化はなく、標準〜やや難のレベル。
- 実験からの考察問題や論述問題の出来が結果につながると思われるので、これらの問題にじっくり取り組むことができるよう、時間配分に注意しよう!
対策
①基礎の充実が第一
- 知識を要求する記述問題では難しい内容のものはほとんどないので、まずは教科書に沿って学習をすすめよう。
- 生物用語の記述問題の比率が高いので、定義も含めて正確に覚え、現象の説明といった論述問題の中でも正しく使えるようにすること。
②実験・考察問題:実験結果の資料(表・グラフ)から、それらが意味する内容を考える考察力・分析力を養っておく。
- 問題集や他大学の過去問の実験・考察問題に多数当たって、そのつど、操作・目的・結果・考察等をノートに整理しておく。
③頻出分野の重点学習と総合理解
- 過去の出題分野は十分に学習し、その際に「生物」と「生物基礎」で関連性が強い分野はそれを意識して総合的にまとめておくとよい。
- 例)「生物」の動物の反応については「生物基礎」の体内環境と絡めて学習する。
④過去問研究
- 数年間の過去問を解くと、同じテーマの問題が形式を変えて出題されていたり、他の分野と関連させて出題されていたりすることに気づく。
- 早い時期から過去問に挑戦して、出題形式や苦手分野を把握したり、時間配分の感覚を身につけることが大切。
- 苦手な分野は教科書や問題集に戻って克服し、得意分野や頻出分野は資料集や参考書で幅広い知識を得るなど、過去問から実戦的な対策を立てる。
【地学】
傾向
基礎重視の出題だが、論述・計算問題多し! 描図問題にも注意
| 出題形式 | 大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 2科目150分 |
| 解答形式 | 記述・論述・計算問題中心。計算問題では、計算過程が要求される場合が多い。論述では20〜100字程度の字数指定のものが例年出題されている。描図問題が出題されることも多い。 |
出題範囲
- 地学基礎・地学
出題内容
- 幅広くさまざまな分野からバランスよく出題されている。おおむね、地球、地質、地史、大気または海洋、宇宙の4題構成が多い。
難易度
- 標準的なレベルの出題。高校地学の基礎・基本を尊重した出題が多いが、数値や文字式の計算、数量の解釈、作図などで、やや高度な出題もみられる。
- 試験時間と大問数を考慮すると、大問1題あたり18分程度で解くことになり、論述問題や計算問題、描図問題が多いことも考えると、解ける問題から確実に解答していくことが求められる。
対策
①基礎知識の充実と論述対策
- 基礎知識や基本的事項の理解と整理を行い、体系的に理解するよう努めること。
- 論述問題:過去問や他大学の問題で練習。指定される字数が少ないので、要点を短文で描く練習をしておくとよい。
- 計算問題:過去問や他大学の問題などで、典型的な計算問題の練習を。
②出題項目と学習のpoint!
◆大気・海洋
- 地球の熱収支、大気の力学と大循環、断熱変化と大気の安定度、高気圧・低気圧と高層気象、日本の四季の天気、海洋の層構造、海水の流れや循環などについてよく理解しておくこと。
◆地球
- 地球の形や大きさ、地球の内部構造、地震、地磁気、重力異常、熱などについて、数値やグラフの意味を含めてよく理解しておくこと。
- 基本的な計算問題の練習も。
◆鉱物・岩石
- 火成岩…造岩鉱物や化学組成、組織から、成因等の地学的意義を整理しておく。
- 造岩鉱物…肉眼及び偏光顕微鏡下での特徴、固溶体、多形などについても確認。
- 推積岩や変成岩も含め、地球・地質分野との関連性を重視して学習したい。
◆地質・地史
- 地球の歴史、示準化石と相対年代・絶対年代、示相化石と古環境を十分学習しておく。
- ルートマップ・地質図・断面図などの読図や描図は十分な練習が必要。鉱物・岩石と関連させて理解しておこう。
◆宇宙
- 宇宙分野全体の広範囲から出題されている。
- 太陽系…惑星の特徴、惑星現象と会合周期、ケプラーの法則、自転・公転の証拠、太陽の活動など。
- 恒星の距離・等級・HR図・進化、銀河、宇宙の構造と歴史などについても整理。
- 頻出の計算問題は、各法則の意味をつかみ十分に練習しておきたい。
【国語】
傾向
全体的に字数制限が厳しい
古文・漢文も本格的な記述問題あり
| 出題形式 | 4題(現代文2・古文1・漢文1) |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
| 解答形式 | 全問記述式(制限字数が示されているものが多い) |
出題内容
◆現代文
- <本文>社会論や文化論などが中心。評論の出題も多い。
- <設問>漢字の書き取りは必出。その他は全て字数制限つきの説明問題。大問当たりの総記述量は、例年200字を超えている。
◆古文
- <本文>出題される作品のジャンルや時代は多岐にわたる。和歌を含む文章や、和歌や俳句の基本的な知識を前例とする文章も出題されている。
- <設問>口語訳と内容説明が中心。説明問題には字数制限つきのものが多く、長いもので60〜90字。
◆漢文
- <本文>比較的読みやすい文章が出題されている。
- <設問>書き下し文、口語訳、読みは必出。最後の設問では本文全体の読解力を試す説明問題が出題され、75字の字数制限となっている。書き下し文は歴史的仮名遣いが要求される。
難易度
- 現代文:標準〜やや難レベル ⇒目安:各30~40分
- 古文:現代文に比べるとやや平易なことが多い ⇒目安:20~30分
- 漢文:全体としてやや易~標準レベル ⇒目安:20分程度
対策
現代文
①論理的文章の読解:評論文を中心に学習しておくとよい。
- 抽象度が高くしっかりとした内容の文章をじっくり読んで、論理的な思考力を養成。
- 各出版社の新書は、現代の社会や文化に関わる事象を話題としたものや、入試に頻出する筆者によるものも多いので、読解練習には最適。
- 過去に出題された評論文をじっくり読んでおくことも有益。
- わからない語句は調べ、キーワードは傍線や囲みを入れてチェックする。
- 整理しながら論理展開を明らかにしていくよう意識すること。
- ある程度読解に慣れてきたら、要点をまとめたり問題を解く練習をしたりするなどして、内容理解を深める。
②実際に書く練習を積み重ね、理解した内容を的確に表現する力をつける。
- 赤本や問題集(薄いものでもOK、記述・論述問題中心のもの)の活用。
- 字数制限のある問題にも多く当たり、字数の感覚を養う。
- まず自分で書いてみた上で、模範解答や解説に照らし、相違等自分の答案を客観的にチェック。入試問題に精通した先生などに添削指導を受けることも有効。
③漢字問題は確実な得点源!
- 受験用の漢字問題集を活用して、実際に書いて練習すること。
- 音読み・訓読みや意味もそのつど確認していけば、読解力・記述力もUP!
古文
①基本的な単語力・文法力の習得
- 古語辞典を引く習慣をつけ、文法を網羅した問題集に繰り返し取り組む。
- 意味や訳し方の丸暗記はNG! その語句が文章の中でどのように出てくるのかを確認し、用例に基づいて理解することが大切。
②和歌や背景知識も意識して深い読解力を
- 『源氏物語』『枕草子』『平家物語』『宇治拾遺物語』などの中古の文章や中世の説話を中心とした有名作品にはひととおり当たっておく。
- 更にこれらの作品を含む問題集として『体系古文』(教学社)の利用がオススメ。
- 和歌を含む文章も意識して学習しよう。
- 修辞法などを確認しつつ、詠まれた心情を文章で示されたエピソードと関連付けて理解することが必要。
- 古典の常識を踏まえた記述力
- 口語訳は、機械的ではなく、場面に応じた意味を吟味した上で、場面によっては適宜補足を加えるなどの配慮して訳す習慣をつけること。
- 説明問題については、30〜60字程度を中心に字数制限を想定してまとめる練習。
漢文
①書き下し文と口語訳が必出⇒漢文独特の語法や構文に習熟し、重要句法のマスター
- 句法を網羅した形の問題集を利用して、用例や訳し方をひととおり身につける。
- 文章問題形式の問題集や過去問で演習を行い、文章の中で出てきた句法はそのつど確認し、知識を確実にしていく。
- 読みも毎年出題されているので、意識して学習。
② 漢文問題に頻出、具体的なエピソードから教訓を導き出す内容の文章に読み慣れる。
- 因果応報譚や賢人・愚人の言行録など、ある程度パターン化できるものが多い。
- 「天」や「治世」などに関する考え方の基本や、その当時の思想についての知識も増やし、読解の一助としたい。
③ 本文の主旨や筆者の主張を踏まえて内容を説明する記述力が必要。
- 部分的な説明問題では、指示語の具体的内容や省略されている要素を落とさず書くように注意する。
- 最終的には本文全体について70字前後の字数制限で要旨をまとめる練習をすると良い。























































