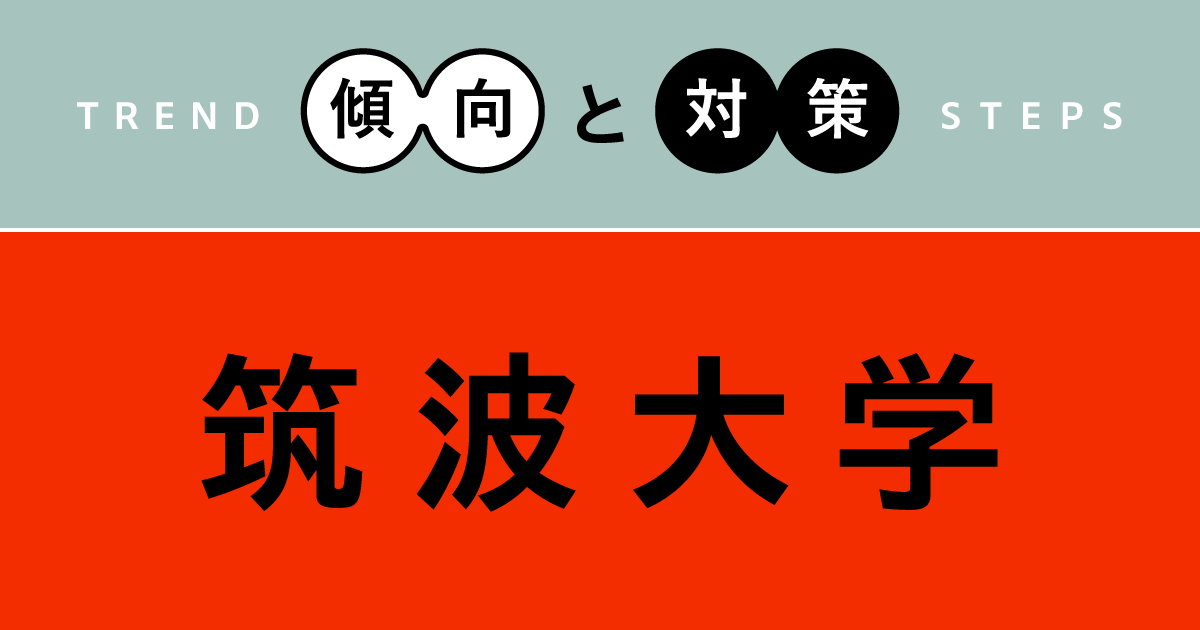
傾向と対策(前期日程)
2023年度までの前期日程の入試問題を分析しました。さらに詳しい最新の分析は「大学赤本シリーズ」をご覧ください。
【目次】
【英語】
傾向
文法・語彙の正確な知識と記述力が必要
| 出題形式 | 例年大問3題。2020年度以降は〔3〕が読解(語句整序)・英作文の2本立てとなっている。 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
| 解答形式 | 内容説明や英作文などの記述式と、内容真偽や同意表現、空所補充などの選択式が見られる。 |
出題の特徴
長文読解問題
- 英文の内容は多岐にわたっており、同じ年度に出題される2題には、傾向の違う英文が選ばれることがある。過去にはエッセー風の文章が出題されたこともあった。
- 〔1〕も〔2〕も設問はオーソドックスなものとなっており、内容理解を問う問題が中心で、記述式の問題が多い。
- すばやく要点を押さえて制限字数内に手際よくまとめる力が求められる。
英作文問題
- 意見論述、要約など、指定語句は50〜100語程度。
- いずれの形式でも難問ではないので、ケアレスミスをしないように解答する必要がある。
難易度
- 読解問題の英文で使われている語彙・表現や、文章の内容はいずれも標準的なものが多く、選択式の問題にも紛らわしい選択肢はほとんどない。英作文問題も標準的。
- 英語の読解力だけでなく日本語の記述力も求められ、うまくまとめるのが難しい設問もある。文法・語彙の正確な知識の運用力など、実際に言葉を使いこなす力が求められる。地道な積み重ねが必要であるという点でやや難だが、取り組みがいのある問題であるといえる。
対策
①読むことに慣れる
- 読解問題の英文自体は、具体的でわかりやすいものが多い。ただ、論点や話の運びに意外性のあるものが多い。
- 柔軟な思考力や豊かな想像力が求められる。
- テーマも多岐にわたるので、日頃から文章を読むこと自体になじんでおく。その際、各段落の話題、段落間の展開といった、文章全体の構成がどうなっているのかを考えてみると、内容把握に大きな違いが出る。
- 読解の設問として指示内容を問われることも多いので、it や this などが何を指しているのか、必ず確認する習慣をつけておく。
②書くことに慣れる
- 過去問に取り組む際は、解答を作成したら模範解答と比較して、自分の解答を添削してみる。どこをどう直せばよりよくなるか検討することが書く力のもとになる。
- 内容説明では解答に盛り込むべきポイントやまとめ方をよく研究する。
- 英作文については、基本的な構文や熟語など決まった表現を蓄えていく。
- 「例題の丸暗記」から脱して「使いこなし」のレベルまで到達しよう。
- 主語や目的語、時制などが覚えた例文と異なっても、ポイントとなる表現を使って正しい英文が書けるように応用力をつけていく。
読解問題の文章量は例年同程度で、記述量にも変化はなく、読み書きするスピードが鍵となる。英作文問題も標準的で、基本的な語彙・文法・構文で対処できるが、さまざまなパターンで出題されているので、柔軟に対応できるよう準備が必要である。
【日本史】
傾向
120分で400字の論述が4題 時代ごとの内容理解が大切
| 出題形式 | 400字の論述4題
例年、4個の指定語句をヒントに解答するものが出題の中心を占めているが、史料中の下線部に絡めて解答するものもある。 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
出題の特徴
◆時代別
- 原始・古代・中世・近世、近現代から1題ずつというのが原則となっている。
◆分野別
- 政治、外交、社会経済、文化から出題されている。
◆史料問題
- 例年出題されており、ほとんどが基礎的資料である。
- 史料中の下線部の説明をしつつ論述するものが出題されるようになっている。
- 史料中の空欄の適語や下線部の具体的名称を明らかにしながら解答していくものもあるが、大半は著名な史料で、基礎的知識があれば書くべきことは容易に想起できる。
難易度
- 教科書の内容を理解していれば合格ラインに達することができるが、時間的余裕はほとんどないので、難易度は高いといえる。
- 解答にあたっては、問題をひととおり見て、解答しやすいものから手をつけていくべきであるが、時間配分に注意してほしい。試験時間を問題数で割れば1題30分程度となるが、構想に十分時間を取り、解答を見直すことも見込むと、1題400字を20分程度で書くと考えるべきだろう。
傾向
①教科書を熟読して各時代の特徴をまとめる
- 原始・古代、中世、近世、近現代というように大きなまとまりの中で出題されている。
- 各時代の特徴をノートにまとめる練習をしておく。
- 利用する教科書は、書店で求められるものもあるので、2,3冊用意して読み比べながら学習すると効果的である。
☞オススメ参考書『詳説日本史B』(山川出版社)・『日本史B』(実教出版)など
②問題演習に取り組む
- 論述の力を養うためには、実際に書いてみることが大切で、書くことで自分の弱点などが把握でき、歴史理解も深まっていく。
- 最初はあまり制限字数にこだわらず、論旨を引き出して出題者の意図に応じた解答ができるようになることが重要。
- 高校の先生など指導者に必ず答案を添削してもらうようにする。
③指定語句から出題者の意図を探る
- 単にそれぞれの指定語句を説明するだけでは不十分であり、指定語句と論旨を結びつける“隠れ指定語句”を的確に引き出せるかがポイントとなる。
- 4個の指定語句のつながりを考え、論旨に沿った説明を付け加えるように工夫する。
- 知らない人物や用語が出されても、それ以外の指定語句や題意から判断して解答作成にチャレンジしよう。
- 問題演習の際はできるだけ先生の指導を受けるようにする。
- 先生と問答することで、解答に必要なひらめきが養われるはずである。
④ 過去問で演習を
- 数年おきに類似する内容が問われることが多いので、過去問にできるだけたくさん当たり、対策を怠らないようにする。
★他大学では
- 新潟大学、京都府立大学が同様に使用する語句を指定した400字相当の論述問題が出題されている。
- 京都大学、大阪大学では、200字ではあるが同類のテーマの論述問題が出題されている。 ※論旨をつかむ練習になるのであわせて取り組んでみよう!
- 指定語句を使用する問題は論述する内容を想起しやすいが、史料問題の場合、下線部の説明に加え、史料文から何を論述するかを考えなければならず、400字の字数を過不足なく調整するのに時間を要するだろう。
- オーソドックスな内容でも歴史事項を正確に理解していないと解答できないものもあるので、苦手な分野や時代を作らないように注意したい。
【世界史】
傾向
時系列を問う論述テーマが多い 論述量が多いので時間配分に工夫を
| 出題形式 | 例年、400字の論述問題が4題。指定語句(5個)を用いて論述する形式。 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
出題の特徴
◆地域別
- 欧米地域:一国史からの大問が目立つ。
例)
- 2020年度 ポーランド
- 2022年度 アメリカ合衆国
- 2023年度 ローマ・チェコスロヴァキア
- アジア地域:中国史は例年必出。イスラーム世界やインド、東南アジアなど。
- その他:欧米地域・アジア地域にまたがるテーマが出題されることもある。2021・2022年度は連続してエジプトから大問が出題された。
◆時代別
- 古代から現代まで幅広く出題されているが、年度により、時代に偏りがみられることもある。
- 欧米地域では近世〜現代が出題の中心となっている。
◆分野別
- 政治史のウエートが高いが社会経済史や文化史も出題対象となっている。
例)
- 「活版印刷技術の影響に関する問題」(2021年度)
- 「1920年代のアメリカ社会の特徴に関する問題」(2022年度)
- 「宋~明初期の商業に関する問題」(2023年度)
難易度
- 体系的な歴史知識と論理的思考力・文章構成力を試すスケールの大きな論述問題。時期を設定して時系列的に論述させる問題が多いという点では比較的書きやすいが、指定語句や重要事項の年代順があいまいだと、全体的に誤った文章になりやすい。指定語句の使用に工夫が必要なものも多い。
- 4題で計1600字の長文論述なので、120分の試験時間でも不足気味になるだろう。不得意な分野は後回しにし、得意な分野の問題から着手するよう時間配分を工夫したい。
傾向
①教科書・用語集・年表の徹底理解を
- 教科書をまず古代から現代まで熟読し、基本事項(事件・人物など)に注意しながら、歴史の大きな流れと諸事件の因果関係を把握しておく。
- 各問題の指定用語には一部の教科書にしか記載されていないものもみられる。
- 『世界史用語集』(山川出版社)の見出し語とその説明にひと通り目を通しておく。
- 論述対策では地域別・国別の年代学習が有効。
- サブノートやカードを利用して年代を整理しておく。年表や世界史地図を活用する。
②テーマ別・分野別対策を…論述の定番といえるテーマの問題も多い。
- 論述用の問題集を参考にするほか、過去に頻出しているテーマを詳しく研究して応用力をつける。
- 出題者のねらいを知る上でも指定語句を丹念に研究しておく。
- 各問題で提示される指定語句には論述全体を展開する上でのキーワードになるものが必ず含まれている。
☞オススメ参考書『世界史用語集』・『世界史小辞典』(山川出版社)
※用語の意味が不明確な場合に活用するとよい。
- 事件や事項の歴史的意味・意義・背景については、『詳説 世界史研究』(山川出版社)などの大型参考書を使って調べるとよい。
③論述力をつける
- 時間的・空間的にスケールの大きいテーマを特色とする論述問題で要求されるのは
- 個々の指定語句を有機的に結びつける推察力
- 文章を構築していく構想力
- 要点を簡潔を簡潔に記述する表現力
- 過去問や類似の形式を持つ他大学の問題に当たり、日頃から400字程度で論述できる力を鍛えておく。
- 年代的な流れや因果関係などに注意しながら文章を構成していくことが、実戦力養成の秘訣である。
【地理】
傾向
図表の利用が多く地形図読図が頻出 自然環境を中心に幅広く問われる
| 出題形式 | 総合選抜(文系)、および生物資源学類・地球学類以外の学類⇒大問4題
生物資源学類・地球学類⇒大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 総合選抜(文系)、および生物資源学類・地球学類以外の学類⇒120分
生物資源学類・地球学類⇒理科1科目と合わせて2科目120分 |
設問形式
- 1題1問の論述問題がほとんどで、「〜について述べよ、説明せよ、比較せよ」などの表現で問われる。1題の制限字数は大問4題の場合は各400字で合計1600字。大問3題の場合は各300字で合計900字であることが多い。
- 他にも
- 200字の論述と描図法を組み合わせた問題
- 使用語句を指定して論述させる問題
- グラフ・統計表や地図などの資料を利用した問題
- 地形図の読図問題(頻出)
- 視覚資料を用いた問題
など。
出題の特徴
- 例年、地形図読図問題が出題されている。
- 山麓や海岸など特徴の表れやすい場所が選ばれ、地形の特色・土地利用・集落立地などの説明やその要因を問う問題が多い。
- 新旧2枚の地形図から地域の変化を考えさせたり、地形図と陰影起伏図を用いて考察させる問題も見られる。
- 自然環境に関する問題、なかでも気候分野の問題が最近頻出。地点比較による気候の特徴と要因や、海洋気候の現象などが出題されている。
- 集落や都市人口、住民生活に関連する問題や、産業の立地や経済の動き、国家に関する問題も目立つ。
- 統計表やグラフ・地図・分布図などの資料類を参考に論述する問題が多い。
- 資料はシンプルなものが多く、どちらかといえば、その事項に関する基本的な考え方や、幅広い知識が試されることになる。
難易度
- 入試問題としてはハイレベル。
- 深い知識に裏打ちされた思考力の必要な問題が3題または4題もあり、ほとんどが300字または400字の論述が求められる。しかし、高校地理の学習内容に基づいて考えれば解答できるように工夫されており、地理的判断さえ間違えないようにすれば、基本に即した学習の積み重ねで十分対応できるだろう。
傾向
①教科書レベルの基本事項は全分野確実に理解しておく
- 地理用語や地名をさまざまな場面で駆使できるような力が必要。
- 重要な用語を整理して、意味と具体例を知り、主要地名は必ず地図帳で位置を確認するなどの習慣を身につける。
☞オススメ参考書『地理用語集』(山川出版社)
②地理的な考え方を身につける
「何が」「どこに」を知るだけでなく、それが「どのようにみられるのか」「どのような要因によるものか」を考える習慣を養う。
- 普段の授業を大切にし、授業中に説明される思考過程を自分のものにする。
- 地理現象を自然的・社会的・経済的諸条件に合せてとらえるとともに、時代による変化や場所との比較をしてみるなどの学習が必要。
③地形図や資料類に強くなる
- 地形図の読図能力を高める。
- 主要な地図記号や等高線の読み方。
- 初見の地形図から地形を判断し、土地利用や集落立地の説明ができる。
- 地域の特色を読み取れるようにする。
- 地形図読図には日本地誌が含まれることもある。
- 日本各地の特色にも関心を持つようにする。
- 資料類に平素から慣れ親しんでおく。
- 統計表・グラフ・統計地図・写真などから地域の状況を読み取れるようにする。
④自然環境と経済・社会を入念に
- 自然環境は、地形・気候ともに成因などについて論理的な説明ができるようにする。
- 気候分野は気候差の生じる要因、気候分布と特色、人間活動との関係などをしっかり押さえておく。
- 環境問題は、原因・発生地域・対策などを整理しておく。
- 経済・社会は、それらの動向が地域の特色といかに関わっているか、具体的に捉えておく。
☞オススメ参考書『新詳 資料 地理の研究』(帝国書院)
⑤論述練習:実際に文章を書いてみる訓練が大切
- 頭の中で論述する内容がわかっていても、試験時間内に、しかも制限字数に合わせてまとめる作業は非常に難しい。
- 過去問などを参考にして、300字または400字で文章を書く練習をする。
- 100字くらいの短文を書き、それらを論理的に並べる訓練が効果的。
- 自分の答案を担当の先生に添削してもらうなどの指導を受ける。
★生物資源学類と地球学類では、理科と合わせて2科目120分で
解答しなければならず、地理だけでも3題あるので、時間配分には十分に気をつけたい。
【倫理】
傾向
諸思想の比較や関連を考察する論述問題が頻出
| 出題形式 | 2023年度に大きく変更され、600〜800字の論述が4題出題され、そのうち2題を選んで解答する形式となった。それ以前は400字の論述の4題構成。 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
出題の特徴
- 洋の東西を問わず、西洋思想、東洋思想、日本思想などさまざまな分野から出題。
- 思想家についての重要語句や短文、資料が提示されることもあり、思想家や思想を対比する形での出題も多い。
- 基本的な知識の確認にとどまらず、生き方や問題解決へ生かす力や主体性が試される内容になっている。
- 教科書に載っていない事項や初見の資料が出題されることもある。
- 教科書で学習した内容を単なる勉強で終わらせずに、日頃の生活の中で生かそうとする態度が重視されている。
- キーワードに使われている語句は基本的なものではあるが、素直にみえても、設問の要求に沿った論述のためには深い思考力を要する。
難易度
- 論述のテーマや分量、内容の深さ、制限字数内にまとめる技術などを考え合わせると、難度は高いといえる。
- 2023年度は指定字数が600〜800字となったが、600字を超えるためには、思想家や用語についてもしっかりと説明しなければならず、知識も相当量必要である。試験時間120分で600〜800字を2題、合計1200〜1600字の論述を書くのにあまり余裕はないだろう。時間配分に注意して取り組みたい。
対策
まずは、教科書・参考書で基礎的知識を身につけ、専門用語を正確に理解し、それを言葉で表現できるようにしよう。どんな問題でも基礎力の養成が第一である。
①単に用語の丸暗記ではなく、一歩踏み込んだ学習をしよう。
- 問題は素直だが、内容は深く、かなりの思考力を要する。
- それぞれの思想や事項の要点を明確に把握する。
- 他との共通点や相違点、関連性までも広く深く研究しておく。
- 発展学習の度合いを見る問題が出されることもある。
- 日本思想と西洋思想の比較をさせたり、現代社会からの視点を要求したりするなど。
②原典史料に慣れよう。
- 思想家の言葉など、短い史料が提示される問題もある。
- 資料集や関係図書にあたって、原典に親しんでおくことが望ましい。
- 史料文中のキーワードやキーセンテンスなどから、だれの思想か、その思想の特色は何かを判断できるようにしておく。
③論述問題を十分に
- 要点を整理し、制限字数内に所定時間でまとめることはなかなか難しい。
- 最初は過去問を使って、教科書・資料集を見ながら解答を自分でまとめてみる。
- 慣れてきたら、自分で問題を設定し、論述する練習をする。
- 2023年度は600〜800字2題に変更になったが、120分で総字数1600字以内というボリュームに変化はなかった。
- 過去問で執筆量がどのくらいかを経験的に身につけ、要点を外さずまとめあげる訓練をしておく。
- 同じような事柄が視点を変えて出題されているので、過去問研究も大切である。























































