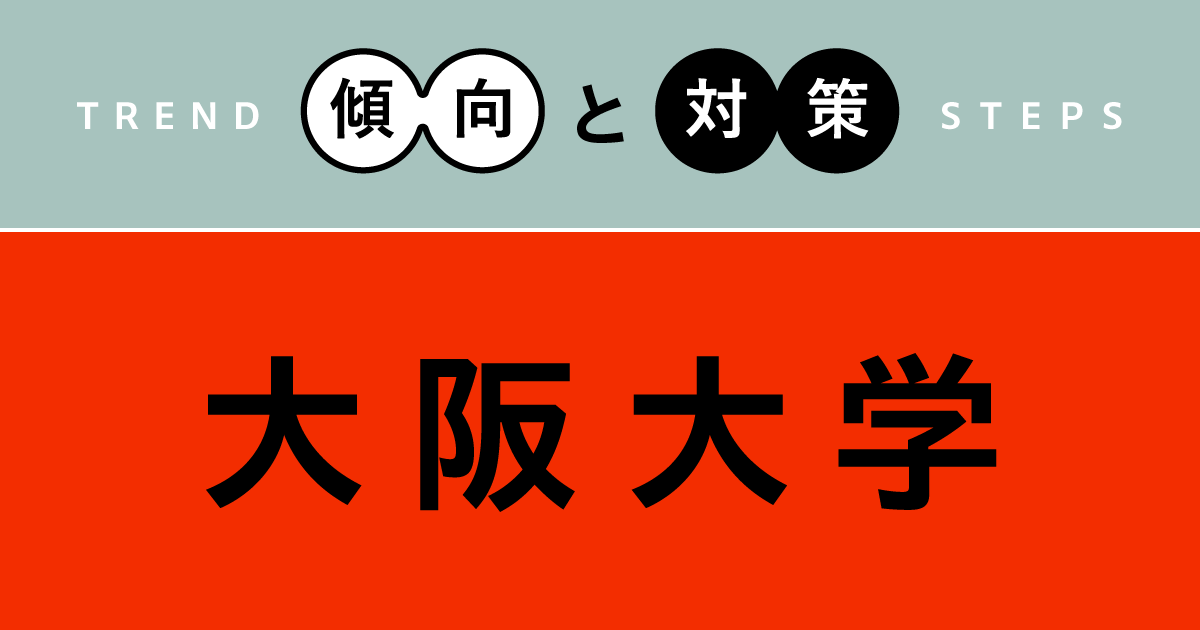
傾向と対策(前期日程)
2023年度までの前期日程の入試問題を分析しました。さらに詳しい最新の分析は「大学赤本シリーズ」をご覧ください。
【目次】
【英語】
傾向
英文を読み・書く 総合的な英語力が深く問われる
| 出題形式 | 例年、大問4題(読解2題、英作文2題)
読解のうち1題は英文和訳のみ、もう1題は長文読解総合問題 英作文のうち1題はテーマ英作文または意見論述、もう1題は和文英訳 ※外国語学部は大問5問、〔1〕〔3〕は共通問題。〔2〕は長文読解総合問題、〔4〕が和文英訳問題、〔5〕がリスニング問題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分
※文学部は105分(〔4〕の英作文問題でやや長い英訳が課されるため) ※外国語学部は120分 |
| 解答形式 | 記述式が中心。選択式がマーク式での解答の年度もあった。 |
出題内容
〔1〕読解(英文和訳)
- 例年、2つの英文が出題される。下線部和訳、全文和訳、部分和訳など。
- 取り上げられる英文のジャンルは多岐にわたっており、抽象的な内容のものもある。
〔2〕読解(総合問題)
- 英文の分量は700〜750程度。設問は同意表現、空所補充といった語句レベルのものと、内容説明、英文和訳、内容真偽といった内容把握力をためすものに二分される。
- 取り上げられる英文は論説中心だが、もう少し柔らかいエッセー調のものもある。扱われる内容は科学的なものから社会、文化・人間のあり方など多岐にわたる。
- 外国語学部は別問題。内容説明と英文和訳で文章の記述力が大いに求められる。英文の全体の分量は1100〜1500語程度。
〔3〕テーマ英作文・意見論述
- 制限語数は70〜80語程度。 「~に賛成か反対かを述べる」「印象に残った経験を述べる」「〜について自分の考えとその理由を述べる」といった形式のものが多い。
- 一定の知識とやや専門的な語句を必要とする社会的な内容のものや、世の中のことに対して関心があるかどうかが試される。
〔4〕和文英訳
- 2問の出題が定着している。問題文は毎年こなれた日本語のものが選ばれており、語句のレベルから文構造まで、直訳を許さないものが多い。
- うち1問は文学部のみ別問題。他学部より高度で分量が多い。
- 外国語学部は別問題。一連の和文中の下線部(3カ所)を英訳するという形式。エッセーが取り上げられることが多い。
〔5〕リスニング(外国語学部のみ出題)
- 例年、まとまった量の英文を通して聞き、内容について、日本語での設問に日本語で答える形式が多い。
難易度
- やや難。外国語学部は例年、高め。
- 全体的な難易度に年度による大きな違いはないと言ってよいが、もともと高度な力が試される問題である。表面的な英語の知識だけでは太刀打ちできない。言葉を通して考えること、一般教養的な知識、要点や自分の考えをまとめて効果的に述べる表現力といった、その人の知力全般を問うものである。
- 〔1〕は15分、〔2〕は25分、〔3〕は20分を時間配分のおおよその目安とし、残りの時間を〔4〕にあてたい。
対策
①英文和訳
- 基本的な語句・熟語・構文の知識を確実に身につけて土台作りをする。
☞オススメ参考書『速読英単語』シリーズ(Z会)
『システム英単語』(駿台文庫)、『東大の英単語』(教学社)
※各語のニュアンスや成り立ちがうまく説明されており、分野別にまとめられている。
- 日本語の表現力を磨く:全体のバランスを考えて自然な日本語にする力が求められる。
- 解答例の日本語をしっかり研究し、単語レベルだけでなく、訳しにくい箇所の処理や全体の流れの自然さといった、優れた日本語表現を吸収しておきたい。
☞オススメ参考書『英語長文問題精講』(旺文社)
②読解総合問題
- 文脈から判断する必要のあるものが含まれており、単純に基本的な訳語が同じになるとは限らない場合もある。
- どのようなニュアンスでその語句が使われているかをよく考える。また、下線部の語句が見慣れぬものである場合、どのような意味の語句か文脈から判断する力が必要。
- 日頃から、意味を知らない語句が出てきても、すぐに辞書を見るのではなく、前後からこのような意味になるはずだと推測するように心がける。
- 外国語学部の〔2〕は語彙レベルがかなり高い。英字新聞などの、「生の英語」に触れる機会を増やし、さまざまな分野の専門的語句も積極的に取り込む。
③テーマ英作文・意見論述
- 英作文の基本を身につける。
- 市販の英作文問題集の暗記例文を数多くこなし、基本例文レベルのものならいつでもスラスラ書けるようにする。
- 英語の文章の習慣にのっとって、実際に書いてみる。
例)
- 賛否を問うものなら初めに賛成か反対かを表明して理由を述べる。
- ある事柄をどう思うかというと出題なら、まず考えの要点を述べてから詳細を説明したり例を挙げたりする。
- 辞書などを使わずに、自分の「手持ちの」語彙・構文の知識だけでひととおり書いてみる。
- 書いたら、主語と動詞の数や人称の一致、名詞の数や冠詞、名詞を受ける代名詞の一致、時制など、英文法の基本的事項が正しく処理できているか見直す。
- 不明だった語句は和英辞書で調べるだけでなく、その語句の語法や類義語・類義表現の使い分けといった点を英和辞典で調べ直すなど、「言えること」を広げる努力をする。
☞オススメ参考書『大学入試 すぐ書ける自由英作文』(教学社)
④ 和文英訳
- 基本的な英語表現をできるだけたくさん身につける。
- 和文和訳(パラフレーズ)の習慣を身につける。
- 例)
- 「当てずっぽう」は英語で何かと問われても即答できないかもしれないが「当てずっぽう」=「でたらめな推測」=「a randam guess」などと表現できる。日本語の語彙力と、その言葉の意味合いやそれがどのような事態・様子を表すものなのかを十分理解しておく必要がある。
- 日本語の文章における「何がどうした」(SV)を常に意識し、動詞に合わせて文型や語法を整えるやり方を培うと同時に、動詞の正しい語法を必ずチェックする習慣をつけておく。
- 解答例において「直訳」ではなく何か言葉を補ってあったり、逆に日本語にはあった語句がなくなったりしている箇所について、その理由の解説をしっかり読んで理解する。また、英文を読むときに、日本語なら言わずもがなの語句が書かれていたり、くどいと思えるほど丁寧に述べられていたりする箇所に注意を払う。それを言わないと成り立たないから書いてあるのである。 ⇒英語を母語とする人たちがどのような理屈で物事を考えているかをある程度体得しておく必要がある。
⑤ リスニング(外国語学部のみ)
- 練習は、CDなど音源とそのスクリプトを用意して行う。
- まず、スクリプトを見ながら音声だけを聞き、唇だけを動かす。次に、音声を聞くのと同時に音読する。慣れてきたら、スクリプトを見ないで、音源に少しあとからついていく感じで声を出す。 ⇒いずれの段階でも内容を理解しようとしなくてよい。音源の速さやリズムをまねすることが第一。余裕が出てきたら、意味はおのずと音と同時に浮かんでくるようになる。
【数学(理系)】
傾向
証明問題頻出 融合問題多し! 柔軟な思考力と計算力を問う
| 出題形式 | 大問5題 |
|---|---|
| 試験時間 | 150分 |
| 解答形式 | 全問記述式。途中の計算、推論なども含めて記述するよう指示されている。 |
※医(保健(看護学))学部除く。文系学部と共通問題)
出題範囲
- 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(数列、ベクトル) ※「確率分布と統計的な推測」は出題範囲から除く。
頻出項目
- 微・積分法。融合問題も含めて2題出題されることが多い。
出題内容
- 微分法は、接線、関数の増減への応用、積分法は面積・体積への応用問題が多い。特に近年は、方程式・不等式への応用や、体積を求める問題が頻出。
- 微・積分法との融合問題として、極限が出題されることが多い。
- 整数の性質に関する思考力を要する論証問題がしばしば出題されている。
- 確率、数列、ベクトル、複素数平面の出題頻度も高く、融合問題の形で出題されることも多い。
- 証明問題が頻出で、論理的な答案を書くことが要求される。
難易度
- 標準~やや難。
- 参考書や問題集などにみられる平凡な問題ではなく、思考力・直感力などを必要とする工夫された問題。例年1題はやや骨のある問題が出題されている。
対策
①基本事項の完全理解
- まずは、教科書および参考書を利用して、基本事項を完全に理解し、定理・公式なども自力で証明・作成できるようになるまで学習しよう。
- 基本事項を自由に使えるように練習し、関連ある事項を組み合わせて使用できるようにしておく。
②計算力の充実
- 模範解答の計算の仕方を研究し、煩雑な計算を避けるテクニックや効率的に計算を行う工夫を体得する。
- 数学のいろいろな知識を活用して、簡単で確実な計算方法や検算方法を考案する。
③答案作成の練習:証明問題など論述の必要な問題に対しては記述力が重要!
- 教科書や参考書、赤本などの解答を参考にして、簡潔で的確な論述・記述とはどのようなものであるかを研究し、そのような答案が作成できるようになるまで練習する。
- 添削・模擬試験なども利用する。
④融合問題への対策
- 実際の入試問題を集めた標準的な受験用問題集を使用して、演習する。
- 「数学Ⅰ・A」の内容が「数学Ⅱ・B」の問題に、「数学Ⅰ・Ⅱ・A・B」の内容が「数学Ⅲ」の問題に、というように下位科目の内容が上位科目の問題の中に含まれていることが多い。学習が進むにつれて、上位科目の演習量を増やしていくとよい。
⑤思考力の育成
- 目標として、過去の国公立大学の入試問題で少しレベルの高い問題を集めた問題集を使い、大問1題につき、20〜25分程度で何とか解答にたどり着けるようにする。
- 問題集の解答を見て、解法の知識を増やすのに、丸暗記するのではなく、基本事項の使い方を学び、解法の考え方の本質を理解することが重要。
⑥図形感覚(特に空間図形)を磨く。
- ただ単に図を描くのではなく、数学関係の書物に描かれた図を参考にして、どうすればわかりやすい図が素早く的確に描けるかなどの研究が大切。
- フリーハンドで円や直線などをきれいに描く技術を磨くとともに、頭の中で図形(特に空間図形)がはっきりイメージできるような訓練もする。
⑦頻出事項の強化学習
- 微・積分法をはじめ、頻出項目については今後も出題の可能性が高い。
- 問題集や、他大学の最近の入試問題についても十分に演習を行い、確実に得点できる自信がつくまで学習しておくことが大切。
☞オススメ参考書『阪大の理系数学20カ年』『阪大の文系数学20カ年』(ともに教学社)
【数学(文系)】
傾向
思考力と計算力をバランスよく試す 基本事項の積み重ねで解決できる良問多し
| 出題形式 | 大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 全問記述式。途中の計算、推論なども含めて記述するよう指示されている。 |
※医(保健(看護学))学部と共通問題。
出題範囲
- 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列、ベクトル) ※「確率分布と統計的な推測」は出題範囲から除く。
頻出項目
- 微・積分法。ほぼ毎年出題されている。
出題内容
- 微分法は、接線、関数の増減、最大値・最小値、積分法は面積に関する問題が多い。
- 次いで、図形と方程式、ベクトルの出題頻度が高い。また、三角関数、指数・対数関数、確率および漸化式を中心とした数列などは、融合問題の題材としてよく使用されている。
- 証明問題が頻出で、論理的な答案を書くことが要求される。
難易度
- 年度によって難易度に差がある。入試問題の中級程度の問題が中心で、やや難程度の問題も含まれる。
- 3題で90分の試験時間は標準的であり、方針の立てやすい問題から取り組むのがよいだろう。
対策
①基本事項の完全理解
- 教科書や参考書を利用して、基本事項を完全に理解し、定理・公式などは自力で導けるようになるまで学習しよう。
- 例題などで基本事項を自由に使えるよう練習し、関連のある事項を組み合わせて使用できるようにしよう。
②計算力の充実:微・積分法を中心に、計算力を試す問題が出題
- 公式の適切な利用方法も含めて、正確かつ迅速に計算ができるように練習する。
- 模範解答の計算の仕方を研究し、煩雑な計算を避けるテクニックや効率的に計算する工夫を体得する。
- 計算結果の検算方法もよく研究し、数学のいろいろな知識を活用して自分に適する計算方法を見出し、マスターしておく。
③思考力の養成:受験問題集の演習によって実力の養成を図る。
- 過去の国公立大学の問題を集めた中級程度の問題集が適当。
- 問題をよく読み、問題設定の複雑なものでも題意を確実に把握できるようにする。
- 方針の立て方、基本事項・頻出事項の使い方を理解するとともに、結論を導くまでの解法の流れをつかむ。
- 問題をいろいろな角度から考え、よりよい解法あるいは視点の異なる解法を研究し、柔軟な思考力や応用力を身につけるよう心がける。
④答案作成の練習:答案は解答結果だけでなく、解答過程も記述が必要
- 何の説明もなく、数字や式を並べるだけでは不十分。我流で記述していては、意図が正確に伝わらなかったり、厳密さに欠けていたりする。
- 論述の必要な証明問題に対しては、特に重要! 教科書や参考書、赤本などの解説を参考にして、答案の作成練習をする。記述力養成には、添削・模擬試験も活用。
⑤融合問題への対策
- 教科書・参考書の例題では単元別の問題がほとんどであるが、「数学Ⅰ・A」の内容が「数学Ⅱ・B」の問題の中に含まれていることも多い。
- ある程度学習が進んだ段階で、中級レベルの受験用問題集を使用して、少しレベルの高い「数学Ⅱ・B」の問題を増やすとよい。
⑥頻出事項の強化学習
- 微・積分法や図形と方程式をはじめ頻出項目については、今後も出題の可能性が高いと予想される。
- 問題集や他大学の最近の入試問題についても演習を行い、確実に得点できる自信がつくまで十分に学習を重ねておこう。
☞オススメ参考書『阪大の文系数学20カ年』(教学社)
【物理】
傾向
物理法則の本質的な理解を大切に!
物理現象に対する柔軟な思考力の養成を
| 出題形式 | 例年、大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 理科2科目で150分
ただし、医学部保健学科看護専攻は理科1科目で75分 |
| 解答形式 | 設問は、小問形式が中心、空所補充完成形式の場合もある。解答は、結果のみを記す形式。一部に、語句や式、グラフなどを選択する形式が含まれる場合もある。年度によっては描図問題が出題。論述問題は近年出題されていない。 |
出題範囲
- 物理基礎・物理
頻出項目
- 高校物理の2大分野である、力学と電磁気からの出題が毎年みられる。
- 他は、熱力学からの出題が目立つ。
- また、3つの大問のうち、1題が2つの中問から構成された出題となっており、熱力学、波動、原子から出題されている。
出題内容
- 主題となる物理事項に加え、そのほか種々の物理事項についても理解を問うような形で問題が構成されており、各分野全般から、大きな偏りがなく、いろいろな内容の出題がみられる。
- 複数分野を融合した問題もみられる。
- 描図問題はグラフを書くものが比較的多く出題されている。
- 語句や式、グラフなどを選択する問題では、その大問のまとめとなるような内容を問われることが多い。
- 計算力が問われる問題、式やグラフの数学的な処理を必要とする問題が毎年出題されており、数学的な力も必要といえる。
難易度
- やや難度の高い問題が中心。見慣れない設定での物理現象を題材として扱った問題や、思考力、計算力を要する問題の出題が多くみられる。
- 問題量は若干の増減がみられるが、問題のレベルの高さや試験時間を考えあわせると、その増減に関係なく、かなりボリュームのある年度がほとんどである。さらに各大問の後半部分では深い思考力を問う問題が出題されるなど、全体的に高いレベルの入試問題となっている。
対策
①教科書を中心に物理法則の徹底的な理解を
- 教科書を中心に物理法則を十分に理解し、公式を導く過程や物理量の定義などについてもしっかりと学習しておく。
- その上で、理解の整理のためにもレベルの高い参考書などに目を通しておく。
②読解力を身につける
- 目新しい題材や見慣れない題材、複雑な題材を扱う問題も多く、長い問題文をしっかりと読み取り、その設定や物理現象を正確に把握する。
- 問題文中に解答の手がかりとなる誘導がなされていることが多く、これらを的確にとらえる必要がある。
- 問題演習などの際に、問題文をしっかりと読み、題意をつかみながら解答する習慣をつける。
③深い思考力を養う
- 基本事項についての理解の徹底を図るために、標準レベルの問題集を1冊完璧にこなし、その上で実戦的な入試問題集に取り組む。
- 単に結果を求めるだけでなく、問題で扱われている物理現象の背景や計算結果の持つ意味を考察するなどして、もう一歩踏み込んで理解を掘り下げる。
- 一つの解法に固執せず、いろいろな解法を考えてみる。
④計算力を含めた数学的な力の養成と描図問題・論述問題対策
- 計算力:問題演習時から、見直しに備えて適切な計算過程を示しながら、自分の力で計算を行う訓練を積んでおく。
- 式やグラフの数学的な処理や近似計算を必要とする問題、三角関数や数列、対数や指数の計算処理を必要とする問題なども出題される。
- 描図問題:問題の題材となっている物理現象についての図やグラフを描いてまとめるのに慣れる。
- 論述問題:問題演習時に単に答えを導くだけではなく、その導出過程を論述も含めて理論立てて記す。決められた時間内に簡潔に論述することは難しいので、解答時間を意識して取り組む。
⑤問題傾向の研究・対策と試験時間のペース配分
- 出題内容や出題形式にさまざまな特色があり、年度によって難易度や問題量に変化はみられるが、過去に出題された内容と類似した事項について問う問題もある。
- 過去問等を活用して問題傾向の研究を行い、十分対策しておく。
⇒オススメ参考書『阪大の物理20カ年』(教学社)
- 平素の問題演習時から試験時間を意識して取り組む。
- 解答しやすい問題を見定めて取りかかれるような力を身につけておく。
- 大問の後半部分での難度の高い問題の出来具合が合否のカギを握ると思われる。
- 前半部分の標準的な問題を迅速かつ正確に解答し、後半部分の問題をじっくりと考えて解答する時間を残しておきたい。このための試験時間のペース配分をつかんでおくことも大切。
【化学】
傾向
有機化合物の構造決定は頻出!論述問題に注意
| 出題形式 | 例年、大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 理科2科目で150分
ただし、医学部保健学科看護専攻は理科1科目で75分 |
| 解答形式 | 説明文について化学反応式や構造式、理由の説明、計算、実験操作法などを小問で求める形式が多い。計算問題は、結果のみでなく、計算過程を要求するものも出されている。論述問題が必出。他に計算問題や描図問題。 |
出題範囲
- 化学基礎・化学
頻出項目
- 同じテーマの問題が何度も出題されることもある。
- 水素結合、化学平衡における近似計算、有機化合物の立体構造、電気泳動、6,6-ナイロンやポリエチレンテレフタラート、アミノ酸の電荷、同じ化学的環境にある炭素の問題、など。
出題内容
- 理論分野:気体の法則、蒸気圧、反応速度、平衡定数、溶解度積、中和滴定とpH電気分解など。
- 無機分野:陽・陰イオンの分離と沈殿・溶解反応などがポイント。単に知識を問うだけでなく、前後の内容から、あまり知られていない内容を誘導する問題がよく出題される。
- 有機分野:構造式・異性体の決定、実験装置の操作・分離・精製法、化学反応式などがよく出題される。
難易度
- 思考力を必要とする問題が多く、どれもよく練られたすきのない問題。
- 表面的な知識だけではまったく歯が立たない。基礎学力をつけた上での、思考力・応用力が要求される。また、試験時間に対して分量がかなり多い。試験時間を考えると、大問1題にかけられる時間は15〜20分程度である。時間がかかりそうなら後回しにし、先に解ける問題からとりかかるなど、時間配分にも気をつけたい。
対策
①教科書を隅々まで徹底的に理解する。
- あまり見慣れない反応や経験のない実験問題がよく出題されるが、それらの解決の基本は教科書の基礎的・基本的な知識の積み重ねによる場合が少なくない。
- また、基本問題を取りこぼさないことも合否に関わる重要なポイントである。
②理論:出題の柱となっている。
- 教科書によって、多少内容にばらつきがみられる場合もあるので、参考書などでやや広範囲にわたってまとめておくことが望ましい。
- 難度の高い化学平衡(蒸発平衡。溶解平衡、解離平衡、電離平衡などを含む)についてはいろいろなタイプの問題を練習しておくこと。
③無機
- 気体の発生・捕集・精製、陽・陰イオンの沈殿・溶解・呈式反応、単体や酸化物などの酸・塩基との反応、主要な無機化合物の製法など。
- 無機化学工業についての問題も十分に学習を積んでおく。
④有機:出題に占める割合も大きく、また難問も多い。
- 実験式から分子式・構造式へと発展させる有機独特の考え方にしっかり慣れておく。
- 立体構造は対策を怠らない。
- 合成高分子化合物では、工業的製法の性質だけでなく、計算問題も多い。 ⇒あらゆるタイプの問題を数多く練習しておく。天然高分子化合物では、アミノ酸、タンパク質が毎年のように出題されているので、過去問での対策が有効。
⑤理論と知識の一体化:無機・有機とも理論を織りまぜての出題が多い。
- 知識的な内容に理論的考察を加えるようにして、総合的理解力をテストするねらい。
- 化学反応式が書けなければ計算ができない場合もある。
- 反応の理論を理解していないと未知の反応式は書けない。
- 原子構造と化学結合、化学平衡、反応速度、酸・塩基や酸化還元理論は物質の各論と深い関係がある。 ➤「なぜそのようなことが言えるのか」と常に問い続け、理論的に深く考える学習態度を心がける。
⑥論述問題と実験問題
- 字数制限がない場合もあるが、30〜100字程度の論述問題は必出。要点を押さえ、簡潔にまとめる工夫と練習を積んでおく。
- 化学の諸事例を具体的・定量的に生きた知識としてとらえるため、授業における実験には積極的に取り組もう。
⑦過去の問題練習を
- まず過去の出題傾向をつかみ、平素から地道に学習を積み重ねることが有効な学習法である。
- 重要な理論や実験などはしばしば形を変えて出題されている。赤本等を活用し、十分に演習することによって、出題内容の範囲や偏りも発見できる。
- あくまでヤマをかけることなく、すきのないきめ細かい学習を心がけることが大切。
☞オススメ参考書『阪大の化学20カ年』(教学社)
【生物】
傾向
実験・考察問題重視! 知識力、論述力、データ解析・考察力を要求
| 出題形式 | 例年、大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 理科2科目で150分
ただし、医学部保健学科看護専攻は理科1科目で75分 |
| 解答形式 | 空所補充問題が含まれるものの、計算・描図を含む、論述中心の出題 |
出題範囲
- 生物基礎・生物
頻出分野
- 遺伝・遺伝情報:DNAの塩基配列とタンパク質合成、DNAの突然変異といった分子遺伝からの出題が主。
- 体内環境、動物・植物の反応:生体膜(細胞膜やミトコンドリア膜など)の機能、抗原抗体反応、神経のはたらき。
要注意分野
- 代謝:酵素や反応を調節するタンパク質に関する問題が多い。
- 生殖・発生
出題内容
- 論述問題:知識で書けるものと実験結果から考察するものの2通り。字数制限は年度によって幅があり、おおむね100字程度。
- 実験・考察問題:図とともにグラフや表などの形で実験結果が提示され、このデータをもとに傾向や特徴を読み取って実験結果を考察する問題が多い。
- 全体としては分子生物学に関する出題が多い。
- DNAと遺伝子の形質発現・遺伝子操作、タンパク質の立体構造、能動輸送・ナトリウムポンプ・細胞の興奮、免疫反応、細胞・分子レベルでの細胞の相互作用 など
- 頻出項目としては、細胞膜のはたらき、免疫反応、DNAとタンパク質、神経と反応、ATPに関係する物質代謝など。
- 内容的には実験結果の解釈を中心に理論的な考察をさせるものが多い。
難易度
- 難度は高い。例年、高い読解力と考察力・論述力を要求する問題が出題されている。
- 問題の性質上、それぞれの大問に要する時間を一目で判断するのは困難といえるので、本番での時間配分も難しい。時間切れを防ぐには、問題を読み解くのに要する時間はもちろん、わかった問題は素早く書き切ってしまえる論術への慣れが鍵となる。標準レベルの問題でどこまで点数を確保できるか、そしてその上で、字数の多い論述でいかに多く得点できるかが大切になってくる。
対策
①基礎事項の総点検
- 全分野にわたって基本的な用語などを正確に覚えているか、定義や説明も含めて総点検する。
- 基礎的な用語の記述問題なども出題されている。
- 教科書の索引などを利用して生物用語を50〜100字で説明する練習をする。
- 知識の定着と論述の練習になる。
②実験・考察問題対策
- 論述問題:実験・考察問題が重視されている。
- リード文や設問文の中にヒントとなる内容がある。実験結果から結論を論理的に導き出す思考力と、それを的確に表現する文章力が必要。
- グラフ・図表問題:論述の中に単なるグラフの傾向を書くだけではなく、そう考えた根拠やグラフからの計算などが要求されることが多い。
- 教科書に出ている典型的なグラフだけではなく、図解などで「グラフの〜から、…ということがいえる」というポイントをつかむ練習をしておく。対数グラフの扱いにも慣れておくとよい。
- 授業等で実験をする機会があったら、積極的に取り組む。
- 実験の目的・経過・結果はもちろん、実験手順、使用する器具・注意事項まで常に「なぜ」を考えながら行い、あとで必ずまとめておく。
- 実験の結果から何がいえるのか、自分なりに分析し、考察することが大切。文章の形でまとめてみる。
- 教科書や参考書に載っている有名な実験についても、目的・手順・結果・考察・結論を整理しておく。
③過去問で演習を
- 標準的な問題集をひととおり終えたら、赤本で過去問をしっかりと、特に頻出・要注意分野についてはできるだけ多く解いておく。
- 傾向からみても、また試験の特性からみても、論述力の養成は二次試験突破の最大のカギである。
- 50〜100字程度を中心に十分な練習が必要である。
☞オススメ参考書『生物 新・考える問題100選』(駿台文庫)
『生物 理系上級問題集』(駿台文庫)
京都大学などの入試論述問題など
【日本史】
傾向
事象の歴史的意義・影響・動向などの論述
知識を整理・体系化してまとめる力が必要
| 出題形式 | 例年、4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 全問論述問題。各大問の字数は、近年200字程度で統一されており、総論述量は800字程度で定着している。 |
出題内容
- 時代別
- 例年は古代・中世・近世・近代から各1題が出題されている。
- 分野別
- 政治史(軍事を含む)・外交史、あるいは身分制、都市、貨幣、農民と土地制度といった社会経済史分野からの出題が多い。
- 問われ方の特徴として、次の3つのタイプがみられ、それぞれに理由・背景・影響・原因・時期設定などの留意点が指定されることが多い。
- 歴史事象を時代ごとに比較・説明するもの
- 歴史事象の政治的・社会的・文化的要因とその影響を論述するもの
- 複数の時代にまたがって部門史的に書くもの
難易度
- 全体的に取り組みやすい出題が続いており、内容的にも教科書の範囲内のオーソドックスなテーマが多い。
- 例年みられる特徴として、問題の設定や条件が明確なものが多く、人物・事件などは想起しやすくなっている。しかし、それゆえに歴史事象を並べただけの解答になってしまいがちである。設問の設定や条件を検討して、まとめ上げるには、正確な日本史の知識と理解を必要とし、論旨の整った質の高い解答が要求される。
対策
①教科書の熟読とノートの整理:問題は教科書の記載内容を中心に作られている。
- 日頃から教科書を丁寧に読み、日本史の基礎的知識をしっかりと把握する。
- まとめノートを作る。
- 教科書を読んで、重要事項を抽出し、それを図解や表にして流れをつかむ。
- さまざまな事件・法律・条約などがもたらした歴史的な影響や意義に留意しながら学習を進める。
- 教科書の太字部分だけではなく、その前後に並べられている原因・結果にも着眼し、関連する知識の定着にも気を配りたい。
- 教科書以外に史料集や年表などの解説にも目を通す。
- テーマ別の学習に取り組む。比較的ポピュラーなテーマが多く出題されるだけに、差がつきやすい。
- 時代ごとにまとめた知識を一つのテーマを軸に時代を超えてつなぎ合わせる。
- 時代ごとの比較も要求されるので、その点にも注意してまとめる。
②問題演習に取り組もう:解答は200字程度、「まとめる力」が試される。
(1)問題の諭旨を読み取り、論述に必要な人物・事件・法律などの歴史用語を抽出する。
- 基軸になるテーマをしっかり見据え、歴史用語の羅列や年代順に事象を並べるだけの解答に陥らないように注意。
- 解答の際、西暦年を使用することは極力避けた方がよい。西暦年を使用すると年代順に事象を並べるだけの解答に陥りやすくなる。
(2)抽出した歴史用語を論旨に沿って並べ、構成(解答の枠組み)を組み立てる。
- 結論をどう締めくくるかがポイント。
(3)論述の方針が決まったら、実際に下書きし、その後で清書をしてみよう。
- 歴史用語をどれだけ盛り込むかより、どれだけ省けるかを念頭におく。
- 字数をカバーするための歴史用語の羅列は避ける。
(4)添削してもらおう!
- 塾・予備校の季節講座で開設される論述講座を積極的に利用する。
(5)過去問に必ず取り組むこと
- 例年、出題傾向に大きな違いはない。過去の出題に取り組みながら歴史理解を深め、どのようなニュアンスで出題されるかを体感する。
★他大学では…
- 京都大学:200字の論述問題で類似している。
- 名古屋大学:字数や傾向に違いはあるが、短くまとめる練習になる。
- 筑波大学・新潟大学:指定語句を利用した400字の論述問題。字数はやや多いが、指定語句から論旨を探り、構成を組み立てる練習になる。
- 市販されている問題集などを利用する。
- 頻出テーマは類似の出題も多く、本番で遭遇すれば迅速に対応できる。
【世界史】
傾向
論述主体! 2023年度は1題が別問題に
| 出題形式 | 近年、年度により問題構成が変化している。2023年度は3題、ただし、文学部と外国語学部とで〔1〕が別問題となった。 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 50〜150字程度の小論述および、200〜300字程度の長文論述の問題が混合して出題されることが多い。ほかに、記述法、選択法など。論述の総字数はおおむね800字前後。 |
出題内容
- 地域別
- 欧米地域:近年は西ヨーロッパが頻出。他に、ロシア・南欧・東欧・南北アメリカなど、複数地域の関連で問われる問題も多い。
- アジア地域:中国史が多出しているのが特徴。他に、東アジア。東南アジア、インド、中央アジア、西アジアなど。
- 時代別
- 中世史と近世・近代史から最も多く出題されている。
- 「異なる地域・国家の比較」や「文化の交流」について論じやすい時代が選ばれている。
- 現代史は、毎年何らかの形で出題がみられる。
- 分野別
- 政治・外交・制度に関するものが最も多く、次いで社会経済・貿易関係・文化や宗教などからの出題が多い。
- 近年は宗教や文字・言語に関する出題が増加しており注目されている。
- 単なる知識だけでなく、歴史事象の背景・原因・経過・結果・影響などの観点からどれほど深く歴史を理解しているかが問われている。
難易度
- 論述問題が中心で、歴史事象の原因や影響まで理解が深められているかどうかが問われ、細かな知識の丸暗記のみでは対応できない問題がほとんどである。
- 論述問題の解答を構成するのに時間がかかるかもしれない。1つの問題に時間をかけすぎないよう、目安の時間を決めて、効率よく取り組んでいきたい。
対策
①用語集・歴史地図の活用
- 知識としては教科書中心の学習を十分行うことが前提。
- 論述問題を想定しながら教科書の文章を繰り返し読む。
- 不明な点や疑問点は『世界史用語集』(山川出版社)で確認。
- 日頃から、歴史地図に親しみ、同時代の世界の空間的な広がり、東西交流や貿易のネットワーク、周辺地域との外交関係などの観点でイメージをつかむ。
②第二次世界大戦後を中心とした現代史の重点学習
- 長文論述に耐えられるだけの正確な知識をつける。
- 過去には、単に「世界史」の知識だけでなく、「日本史」「地理」「現代社会」「政治・経済」などの知識を駆使しなければ解答できない問題の出題もあるので、他科目の学習もおろそかにしない。
③論述問題の研究
- 問題文をよく読んで、出題の意図をよく理解してから論述するよう心掛ける。
- 解答例と自分の解答の違いを分析することに十分時間を割く。
- 過去問の研究が終わったら、市販の問題集などを利用して、100〜300字程度のオーソドックスな問題で練習を重ねる。
- 要点を押さえたコンパクトな論述になるように、構想にしっかりと時間をかける。
point!
- 書き始める前に、出題者の意図、つまり題意をしっかり把握する。
- 解答を書く前に、想起できる歴史事項をメモして使う順序をきめる。 (指定語句のある場合はその語句をどのように使うか、図や写真の場合はそこから読み取れるものは何か)
- 書き上げた文章は、先生に添削してもらう。
④過去問の研究
- 独自の出題形式や、論述のスタイル、内容の深さなどを自身で理解するためにも、赤本等を利用してしっかり過去問に取り組んでおく。
- 近年の問題は資料から読み取れる内容と学習した知識をいかに総合的にまとめることができるかが問われている。
- まずは過去問に取り組み、どういった問題が出題されているのか、教科書の知識がどのように問われているかを研究してみよう。
【地理】
傾向
基本的で大きなテーマについての論述
世界各地の時事的問題に注意、資料対策を十分に
| 出題形式 | 例年2題。各大問はいくつかの小問に分かれている。 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 大問〔1〕〔2〕のいずれも論述法。1問の字数は、100字や150字のものが多い。50字や250字のものも出題されている。地理資料を使う出題が必出。他に選択法、記述法など。 |
出題内容
- 例年、基本的かつ大きなテーマが1つ取り上げられ、その事象と背景、現状と変貌、問題点・課題などについて、掘り下げて論述させる問題が多い。
- 高校地理の重要テーマに関する出題が多いが、問い方がシンプルなために解答に盛り込むべき事項を的確に判断する必要がある。
- さまざまな地理事象についての知識の豊富さや正確さが必要となる。
- 系統地理と地誌的分野が出題。
- 教科書などの記述内容が少ない分野・内容が出題されることもある。
- 世界各地域の中では、アジアや発展途上地域が頻出。
- 現代社会の最新情勢を素材としたテーマも出題されており、地理的思考力が試される問題となっている。
難易度
- 100から200字程度の字数の論述問題が中心であるため、難度はやや高い。
- 出題内容は、高校地理の内容に沿った、基本・重要事項が重視される傾向がみられるが、それらをベースとしながらも教科書の範囲をこえて、現代社会の動向を反映させたテーマも出題されている。オーソドックスな内容であるとはいえ、出題意図を的確に理解し、長い字数の論述をまとめるには、かなりの高度な知識と学力が必要である。
対策
①基本的知識をマスターし、地理的な考え方を身につける。
- 教科書に書かれている内容を完全に理解し、副教材の資料集なども隅々まで目を通しておく。
- 問題数が少なく出題内容が限定されているため、どの分野にも対応できるよう、満遍なく十分に学習しておく。
☞オススメ参考書『地理用語集』(山川出版社)
※用語や地名について、その定義も含め、知識を確実なものにする。
- 地理的事象に関する因果関係やその背景の理解などに十分留意するとともに、普段の授業で解説される地理的なものの見方・考え方をしっかりと身につける。
- 単なる用語の暗記だけでなく、さまざまな地理的知識を組み合わせて、地理的事象や地域の特色、問題点を説明することが求められている。
- 面積・人口などの国勢や、農畜産物・鉱産物などの主要生産国や貿易など、主要な統計や各種のテーマについての統計地図について十分学習しておく。統計資料が物語る地理的事象の意味を理解するよう心掛ける。
②十分な論述対策を
- 50から250字程度で文章をまとめる訓練をしっかり重ねておく。 参考)大阪大学、九州大学などの過去問
- 実際に文章を書く練習を積み重ねておくことが大切。
- 頭の中で論述すべき内容がわかっていても、それを試験時間内に制限字数内で論理的にまとめる作業はかなり困難が伴う。
- 自分で書いた文章を先生に添削してもらうなどの指導を受けるとよい。
③現代的課題に興味・関心をもつ
- 世界の各地や日本で話題になっている時事的な問題について、幅広い知識を身につけておく。
- 例えば…人口問題、環境問題、民族紛争、地域統合、経済のグローバル化、情報化社会、日本の社会問題など
- 地域的には、アジア諸国、EUなどの政治・経済的動向など
- 普段から、教科書の内容をさらに広げて、新聞やテレビのニュースなどを通して、今話題になっていること、そこから読み取れる地理的な事象について考える習慣を身につけておきたい。
【国語(文学部)】
傾向
現代文は現代思想の最前線が中心
古文は有名出典・頻出箇所に注意
| 出題形式 | 4題(現代文2題、古文1題、漢文1題) |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
| 解答形式 | 全問記述問題。
説明問題が多いが、字数制限は基本的になく、設問の要求内容や解答欄の大きさを見て適切な量を判断し、書かなければならない。 |
出題内容
◆現代文
- 〔1〕本文:論理的文章が出題される。文学に限らず人文科学全般(言語・歴史・思想・哲学・芸術・教育など)の論評が多い。
- 設問:説明問題の難易度は高い。単に本文から抜き出してまとめるだけでは不十分で、自分の言葉で的確に説明することが求められる。
- 〔2〕本文:小説からの出題がほとんど。明治期の作家から現代作家まで幅広い。
- 設問:〔1〕以上に難度が高いことが多い。心情説明の問題では、状況描写から演繹して論述するという点で、受験生の文学的な素養が必要とされる。
- 設問文では…
「なぜだと考えられるか」「考えを述べなさい」
「どういう~と思われるか」「どうのような~だととらえられるか」
などと問われることが多い。
- 設問文では…
◆古文
- 〔3〕本文:時代は中古と中世中心。ジャンルは多岐にわたっている。例年は有名出典が比較的多く、頻出箇所であることも少なくない。文章の長さ・内容ともに標準的。
- 設問:例年、口語訳や語意、内容説明の設問が中心。和歌解釈も頻出。
◆漢文
- 〔4〕本文:『韓非子』『論語』といった有名出典からなじみのない出典まで、さまざまな文章が出題。文章の長さ・内容ともに標準的。
- 設問:書き下し文・訓点・口語訳・内容説明を中心に設問が組み立てられている。本文全体の主旨をふまえた内容説明もよく出題される。概して、書き下し文・訓点は標準、内容説明・主旨はやや難レベル。
難易度
- やや難〜難レベル。問題文が比較的長文で、試験時間に対して論述量が多い。
- 時間的に余裕がないので、いずれの問題についても速読即解が必要。解答作成の時間を考えれば、古文・漢文は現代文と同様のスピードで内容が理解できるかどうかが試される。この2題を50分程度で解答できれば、残り時間を現代文に回せる。
対策
①読解力、着想・柔軟な思考力の養成
- 新書・文庫・選書類の評論に親しみ、読書を通じての学習を日常的なものにして、総合的な読解力養成をめざす。
- 哲学・思想系の硬い文章も自在に読みこなせるレベルに達していることが目標。
- 目次をヒントに本全体の構成をつかむ
- キーワードをチェックしつつ、段落・章・節の題(小見出し)などから個々のパートの役割と、全体構成を考える。
- 図を描きながら考える…論旨展開を図式化して客観的理解をめざす。
- 要旨を書き出してみる…結論部や例示内容の要約を試みる。
- 段落どうしの関係をつかむ…序論→本論→結論→、導入→展開Ⅰ・Ⅱ‥→まとめ、起承転結など)
- 自分にひきつけて考えたり広げて考えたりする
- 自分の言葉で説明する
- 〔1〕は「国語」という教科に限定される内容ではなく、「社会」で扱う内容まで踏み込んだ素材が多いので、教科の枠を超えた幅広い学習が必要である。
- 〔2〕は詩や小説・随筆など幅広く接することが必要である。
②論述力の養成
- 正確な表記・表現(漢字・仮名遣い・文体など)を心がけ、はっきり丁寧に記す。
- 主旨説明などの要約力が求められる。全体要約や箇条的抽出をシミュレーションする。
- 心情・性格説明などが問われるので、登場人物の行動・発言をまとめる力を養成しておく。
- 慣用表現に慣れておく。表現効果を問う設問が頻出しているので、表現技巧の理解を深めておくこと。
③語彙力の養成と漢字・語句対策
- 一般の語はもちろん、いわゆる<評論文のキーワード>といわれるものを含めて幅広く語彙力を養っておこう。
☞オススメ参考書:中村雄二郎『術語集』『術語集Ⅱ』(ともに岩波新書)
中山元『高校生のための評論文キーワード100』(ちくま新書)
仲正昌樹『いまを生きるための思想キーワード』(講談社現代新書)
- 同音・同訓異字や熟語を中心に問題集の反復練習
- 単なる知識にとどめず、日常の学習において、まめに国語辞典などを活用して、使いこなすレベルまで習得する。
④古文対策
- 辞書を用いての原典通釈を重ねて、まずは語彙力を身につける。
- 「現代文と同様に読める」レベルを目標に練習を重ねる。
- 受験用に解説した「百人一首」の参考書などで和歌の解釈力や修辞の知識を深める。
- 有名出典の頻出箇所からの出題もみられるので、基本〜標準的な問題集などでこのような箇所をひととおり押さえておく。
⑤漢文対策
- 出題はオーソドックスで、本文の内容はいずれも比較的平易である。
- 教科書と副読本の精読を繰り返して、高校(大学受験)レベルでの基礎漢文を、句形・句法を中心に復習する。
- 訓点をつける、頻出漢語の読みを覚える、といった基本的な学習も忘れないようにする。
【国語(人間科・外国語・法・経済学部)】
傾向
現代文の記述対策は要約を中心に
古文は和歌や俳句の解釈がポイント
| 出題形式 | 3題(現代文2題、古文1題) |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 全問記述問題中心。説明問題では、字数制限が設定されることが多い(総記述量は500〜900字弱)。選択式の問題も数問程度出題されることもある。 |
出題内容
◆現代文
- 本文:評論2題の出題が多い。哲学・思想系のものからの出題が目立つ。
- 設問:本文の主題を把握した上で論述させる設問が多い。150〜250字の説明問題、空所補充問題などが出題されている。書き取りは必出。文脈で判断する必要がある語が問われている。
◆古文
- 本文:出題される文章の時代は中古または中世が多い。ジャンルは物語、日記、説話など幅広い。文章の長さ・内容は標準的。
- 設問:口語訳、内容説明、和歌解釈が中心。このほかには語意、人物指摘、文学史など。和歌解釈のレベルが高く、和歌の理解が大きなポイントとなっている。
難易度
- 設問レベルの高さ、記述量の多さ、90分という試験時間などを考慮すると、総じて「やや難」のレベル。
- 現代文のみでみると、年度によっては「難」となっている。いずれの大問も30分はかける必要があるだろう。時間の制約が厳しい。古文を先に解くのが得策かもしれないが、2023年度のように古文が難しい場合もあるので、出題に応じて柔軟に対応したい。
対策
〔現代文〕
①第一に読解力の養成をはかる…高レベルの記述力・論述力が要求される。
- 評論・論説・随筆の類を数多く読み、全体の要旨、各段落の主旨、筆者の表現意図などを100〜300字程度でまとめる練習をする。
- 評論対策
- 最初は基本的で短い文章から始め、次第に文学論・芸術論・作家論・経済論、ひいては批評論まで、とにかく読み慣れておく。
- 説明的な言い回しから、さらに思考的かつ哲学的な文章に慣れておく。
☞オススメ参考書『阪大の国語15カ年』(教学社)
point!
野矢茂樹・村上陽一郎・柄谷行人・大江健三郎・中村雄二郎、山崎正和・小此木啓吾・小林秀雄・鷲田清一といった人の著者にも接しておき、1冊でも多くの哲学・思想系の書物に親しんでおく。
- 小説対策
- いろいろなタイプの小説に接するようにする。
- 授業で扱う教材で、作者の意図・登場人物の心理を読み解くことに普段から慣れておく。
②演習でも制限時間の設定と十分な検討が必要
- 短時間で要領よくまとめるコツを身につける。国公立大学二次試験対策用の問題集を制限時間通りにやってみて、模範解答と比較検討してみる。
☞オススメ参考書『体系現代文』(教学社)
- 添削指導を受ける。
③漢字・語彙力の養成
- 書き取りは必出。確実に点を稼げる分野にする。
- 慣用表現・故事成語・類義語などにも習熟しておく。
- 普段から読書に親しみ、語句にこだわり、幅広い教養として蓄積していく。
〔古文〕
- 基本古語のマスター、文語文法、和歌修辞の整理から始め、物語・説話・日記・歌論・俳文や近世の随筆などさまざまなジャンルの文章にあたっておく。
- 文学史についても、基本事項を整理しておく。
- 和歌・俳句解釈の練習をする。
- 教科書や問題集に出てくる和歌や俳句をまず自分で解釈してみる。
- 枕詞や掛詞などの和歌修辞もきちんと押さえておく。























































