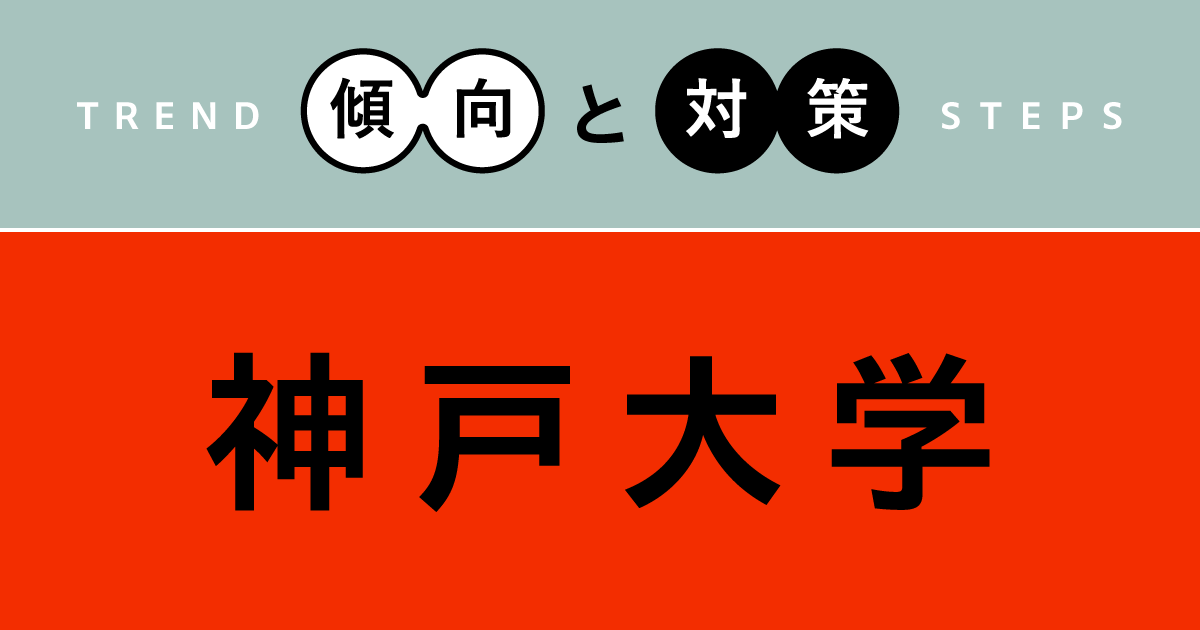
傾向と対策(前期日程)
2023年度までの前期日程の入試問題を分析しました。さらに詳しい最新の分析は「大学赤本シリーズ」をご覧ください。
【目次】
【英語】
傾向
読解問題3題、英作文1題の出題が基本
2021年度は会話文が登場
| 出題形式 | 例年、4題(読解問題3題、英作文1題) |
|---|---|
| 試験時間 | 80分 |
| 解答形式 | 記述問題(英文和訳、英作文、内容説明など)、選択問題(空所補充、同意表現、内容説明、内容真偽など)とバラエティーに富んでいる。 |
出題内容
①読解問題
- 出題の中心はバラエティーに富んだ設問からなる総合読解問題。英文の量は、1題500〜650語前後のものがほとんど。総語数としては1400〜1900語前後。
- 英文の内容は、環境問題をテーマとするものが多く、他には健康問題、格差問題など今日的な話題や、やや抽象度の高い科学系の論説文などから計2題、会話文が主体のものが1題というパターン。
- 英文のレベルとしては、語彙には一部難解な語があるものの、全体的には読みやすい英文が多い。
- 英文和訳:1つの長文につき1,2カ所、全部で3〜5カ所の下線部を和訳させることが多い。指示語の内容を明確にしながら訳すという条件がついていることもある。
- 内容説明:20〜70字の字数制限があるものが多い。
- 文法・語彙問題:基本的な語彙力・文法力や熟語力、文脈から判断する力をみるような設問が多い。英文の中の語句と同じ意味や用法の語句を選択する問題も出題も出題されている。
②英作文問題
- 例年、意見論述の問題が出題。語数は40〜70語程度で2問のことが多い。
難易度
- 難問・奇問の類はなく、実力どおりの得点が得られる、日頃の地道な努力が報われる良問。
- 試験時間が80分と比較的短く、記述量がかなりあるため、時間配分には細心の注意が必要。
対策
①読解問題
- 難解な語も含まれた総語数1400〜1900語前後の英文を短時間で読みこなすためには、かなり高度な語彙力が必要。
☞オススメ参考書『速読英単語 必修編』『速読英単語 上級編』(いずれもZ会)
※語の意味を文章中で覚えていく形で、単語の暗記などに用いるとよい。
- 重要構文・熟語の暗記や、挿入・倒置・省略・同格といった英文解釈上のテクニックも必ず身につけておく。
- 英文の一文一文の意味を正確に読み取りながら、パラグラフごとに話の大まかな流れをとらえる習慣をつける。
- 英文和訳
- ポイントとなる構文・イディオムを確実に押さえることができるよう練習を積む。
- 直訳ではうまく日本語にならない箇所も多くみられるので、あくまで英文全体の話の流れに沿ったわかりやすい日本語を書くように心がける。
- 過去問に当たる際には、下線部以外の箇所も全訳を注意深く読んで、「これは」と思われる部分の和訳には注意し、訳の練習に利用するとよい。
- 内容説明
- 前後にある該当箇所の特定と、それをいかに要領よくまとめるかが最大のポイント。
- 原因と結果、一般論と具体例など、文と文のつながりにも気を配りながら、必ず自分で答案をまとめる練習を繰り返す。
- 文法・語彙問題
- 純粋に文法の知識や語彙力・熟語力を問うものも出題されているので、確実に身につけておく。
- 単語学習の際には、同意語・反意語、特殊な意味など多角的な知識を得るようにすること。
- 長文のテーマには今日的な話題が取り上げられることが多いので、環境問題、健康問題、社会問題などの世相を反映した文章や、科学技術、心理学、教育学、文化や言語の歴史といった分野の文章には、英文・和文を問わず普段からよく目を通し、一般教養を深めておくことも有効な対策となるだろう。
②英作文問題
- 意見論述は、例年、書きやすい題材が取り上げられることが多く、語数もそれほど多くないので、基本的な英作文の力があれば対処できる問題が多い。
- 小論文や面接の対策本を利用して、自分でテーマを設定し、辞書を使わずに40〜70語程度の英文を書く練習を繰り返す。
- 書き慣れていない語彙・構文を利用するよりも、正しく使いこなせる語彙・熟語・構文を用いるよう心がける。
- 先生に添削してもらう。
☞オススメ参考書 赤本プラス『大学入試 すぐ書ける自由英作文』(教学社)
【数学(理系)】
傾向
考察力・論証力・計算力を要する標準程度の良問
| 出題形式 | 大問5題の出題。全ての問題が2〜4の小問に分割されている。 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
| 解答形式 | 全問記述式 |
出題内容
- 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(数列、ベクトル)
出題範囲
- 微・積分法、ベクトル、数列、確率などの出題が多い。
- 他の分野も幅広く出題されており、全範囲に注意が必要。
出題内容
- 証明問題が頻出。年度によっては図示問題も出題されている。
- 小問に分割された誘導的問題が多く、設問の意図を理解して対応する柔軟な理解力が必要である。
- 正確・迅速な計算力の養成も重要である。
難易度
- 標準程度ではあるが難度は高め。
- 論理的によく練られた良問であり、これに応じて答案を作成するには論証力を要する。難度の高い問題もあるが、誘導的な小問に分割されているので、その誘導に従えば解答できる。しかし、誘導されていることに気がつきにくい設問もあるので注意しなければならない。1題あたり20分強を目安として、取り組みやすい問題から確実に解いていきたい。
対策
①基本事項の学習と問題集の演習
- 教科書の基本事項の習得は学習の基礎!
- 用語の定義を正確に記憶しているか?
- 定理は証明できるか?
- 公式を知っているだけでなく自力で導くことができるか?
- これらを用いて基本程度の問題ならば即座に解くことができるか?
- 自問して、「基本事項は習得できた」という自信が持てるまで、繰り返し学習する。
- 大学入試問題による演習も必要。問題が解答できないときは、基礎事項の習得が不十分であるから、よく点検して補強しておく。
- 問題集の解答をみるときは、解法を丸暗記するのではなく、基本事項の使い方を学ぶことが重要である。
②計算力の増強
- 正確・迅速な計算力の養成訓練をする。
- 解答結果の検算も重視し、検算方法を研究しておく。
- 計算によって解法を探ったり、解法の正しさを計算で確かめたりできる。
- 計算力が弱いと、解法は見出せても、解答途中で挫折することにもなりかねない。
③図の活用
- 演習の際、図が利用できる問題に対しては必ず図を描くようにして、その技量を高めるとともに、図を利用する習慣をつける。
- 問題に対して、適切な図が描けると、題意の理解、解法の発見、解答結果の検討などが容易になり、問題の本質を具体的かつ的確に把握できるようになる。
④頻出項目の学習強化
- 頻出項目の問題は標準程度ならば確実に解答できるという自信がつくまで、主として演習により、十分に学習しておきたい。
⑤答案作成の練習
- 週に1回程度は答案の作成練習を行う。
- 答案は解答の経過がよくわかるように、的確かつ簡潔に記述する。
- 教科書の例題の解答を参考にして独学するだけでも効果は上がるだろうが、可能ならば添削などの指導を受けることが望ましい。
【数学(文系)】
傾向
標準程度だが、実力差の出る設問
| 出題形式 | 大問3題の出題。全ての問題が2〜4の小問に分割されている。 |
|---|---|
| 試験時間 | 80分 |
| 解答形式 | 全問記述式 |
出題内容
- 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列、ベクトル)
出題範囲
- 微・積分法、ベクトル、数列、確率、2次関数などの出題が多い。
- 他の分野からも幅広く出題されており、全範囲に注意する必要がある。
出題内容
- 証明問題が毎年のように出題されている。
- 正確・迅速な計算力も重要。
- いくつかの小問に分割された誘導的な設問が多く、その誘導を理解して順応する力が求められる。
難易度
- 標準程度。よく練られた論理的な良問。
- これに応じて答案を作成するためには論証力が必要である。難度が高めの問題もあるが、誘導的な小問に分割されているので、その誘導に従えば解答できる。1題あたり25分程度を目安として、取り組みやすい問題から確実に解いていきたい。
対策
①基本事項の学習と問題集の学習
- 教科書の基本事項の習得は学習の基礎!
- 用語の定義は正確に記憶しているか?
- 定理は証明できるか?
- 公式は自力で導くことができるか?
- これらを用いて基本程度の問題ならば即座に解くことができるか?
- 自問して、「基本事項は習得できた」という自信が持てるまで、繰り返し学習する。
- 教科書学習に加え、問題集による演習も必要。標準問題が解けないときは、基本事項の習得が不十分ということであるから、必要な基本事項を確認して、補強しておく。
- 問題集の解答をみるときは、解法を丸暗記するのではなく、基本事項の使い方を学ぶことが重要である。
②計算力の増強
- 正確・迅速な計算力を養成するように訓練する。
- 計算力があると、計算によって解法を探ったり、解法の正しさを計算で確認したりできる。
- 解答結果の検算も必要。検算方法を研究しておくことが望ましい。
③図の活用
- 演習の際、図が利用できる問題に対しては必ず図を描くよう習慣づけて、図を描く技量を高め、図を利用する力の向上をはかる。
- 問題に対して、適切な図が描けると、題意の理解、解法の発見、解答結果の検討などが容易になり、問題の本質を具体的かつ的確に把握できるようになる。
④頻出項目の学習強化
- 頻出項目の問題は標準程度ならば確実に解答できるという自信がつくまで、主として演習により、十分に学習しておきたい。
⑤答案作成の練習
- 週に1回程度は答案の作成練習を行う。
- 答案は解答の経過がよくわかるように、的確かつ簡潔に記述する。
- 教科書の例題の解答を参考にして独学するだけでも効果は上がるだろうが、可能ならば添削などの指導を受けることが望ましい。
【物理】
傾向
描図・論述問題が頻出 必要な物理量は各自で定義する問題も!
| 出題形式 | 例年、出題数は3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 試験時間は1科目60分、2科目120分 |
| 解答形式 | 記述・論述・描図問題が中心。全問もしくはほとんどの問題で答だけではなく導出過程を示すことが求められている。 |
出題範囲
- 物理基礎・物理
頻出項目
- 3題のうち2題は、力学と電磁気からの出題。もう1題は熱力学や波動からの出題が多い。過去には原子からの出題もあった。
出題内容
- 物理的な現象のとらえ方・法則などに対する理解の徹底度が問われている。
- 解答に必要な物理量を表す記号を自分で定義する問題が出題。
- 力 学:運動方程式、力学的エネルギー保存則、仕事、運動量保存則、力のつりあい、円運動、万有引力や単振動が頻出。
- 電磁気:電磁誘導とコンデンサー、電場と荷電粒子の運動。
- 熱力学:気体の分子運動論や気体の状態変化、断熱変化。
- 波 動:光や波の干渉、ドップラー効果、ヤングの実験、波長などが出題。
難易度
- 難問・奇問はなく、入試問題としてはきわめて標準的な問題。
- 近年は、必要な物理量を自ら定義して答える問題、論述・証明・描図問題など手間のかかる問題が並んでおり、1科目60分相当なので時間配分には注意しなければならない。
対策
①教科書を熟読し、問題集で多くの問題に当たる
- 高校物理の全分野について、その基礎事項を確実に理解する。
- 基本概念、法則・公式の導き方を確認し、完全に自分のものにする。
- 教科書の索引に出てくる用語について簡潔な説明を書いてみる。
- 神戸大学の問題は、ほとんどが既出のパターンの組み合わせであり、難問はあまり出されない。
- 受験用の問題集でいろいろなパターンの問題に当たり、暗記でなく、理解ののちに自然に覚えてしまっているようにしておく。
- 受験用として標準的で、物理の基本法則や陥りやすいミスを確認できるような問題集で、詳しい解法・解説のついたものを使い、理解に重きを置いた学習をするとよい。
☞オススメ参考書『体系物理』(教学社)
『物理のエッセンス』シリーズ(河合出版)
②計算力・注意力をつける
- 文字計算・数値計算ともに十分に問題演習し、計算スピードを上げる練習をする。
- 問題文が長く、その中にいろいろな注意がなされているので、問題文を注意深く読む練習をしておく。読み間違いをなくすことが第一!
- 速度ベクトルでは向きを表す符号は正しいかなど、文中の指定に正しく添えるよう注意力をつける。
③論述・証明・描図問題
- 論述・証明問題に備えて論理的な思考力・表現力を身につける。
- 詳しい解法・解説のついた問題集で、採点者に自分の考えが正しく伝わる簡潔な表現を意識して、コンパクトでかつ論理的な答案を書く練習を十分にする。
- 描図問題もよく出題されるので、普段の学習から正確でポイントを押さえた図を描いて考えることを習慣にしておく。
④二次試験対策を中心に
- 論述形式・描図形式の問題が数多く出題されている。共通テスト対応の演習に重点を置いている人も多いだろうが、神戸大学の場合は共通テストの延長に二次試験があると考えるより、むしろ二次試験対策の中に共通テスト対策が含まれていると心がけて学習する方がよいだろう。
【化学】
傾向
理論と有機が中心 基本~標準の内容だが、なかには難問も
| 出題形式 | 例年、出題数は4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 1科目60分、2科目120分 |
| 解答形式 | 問題文の空所補充、計算問題、選択・記述・論述問題などの設問形式。計算問題では結果のみを答える設問がほとんどであるが、途中の過程を書かせることもある。論述問題は20〜30字程度の字数制限がある場合もある。他にグラフの描図問題など。 |
出題範囲
- 化学基礎・化学
出題内容
- 出題は理論・無機・有機の3分野にわたってるが、理論と有機からの出題量が多い。
- 理論分野:気体の法則、蒸気圧、熱化学方程式などを含む計算問題の頻度が高い。次いで、反応速度と化学平衡、酸・塩基、電池・電気分解、反応と物質量の関係、電離平衡の量論など。
- 無機分野:理論と合せて出題されることが多く、出題の割合としては少ない。
- 有機分野:例年2題程度出題。そのうち1題は元素分析や分子式から構造式や異性体などを推定し、それらに関する反応や性質なども含めて問う場合が多い。また天然・合成高分子化合物からの出題率が高く、やや難度の高い出題もみられる。
難易度
- 例年、全体として標準的なレベルの出題とみてよいが、有機や計算の問題に難しいものも出されている。
- 試験時間に対して問題量が多いので、解く順序を考えるなど時間配分に注意したい。
対策
①理論の基礎力の充実をはかる
- まず教科書などで基礎内容を理解し、基本から応用へと段階的に練習問題に取り組む。
- 理論では計算に慣れることが必要。熱化学、気体の法則と蒸気圧、速度反応と化学平衡、酸・塩基などの問題に当たって思考力・応用力を養うことが大切。
②無機
- 教科書に出てくる各種物質の化学式・製法・性質などをよく整理し覚えておくこと。理論と関連させてそれらの理由などもよく理解しておくこと。
- 化学反応式も頻出。誘導法などをよく理解した上で、確実に書けるようにしておく。製法などの実験もよくみておくこと。
③有機
- 出題量が多いため、特に力を入れて学習しておく必要がある。
- 元素分析や分子式などから構造式・異性体を推定する出題が頻出しているので、その思考過程を確認しておく。アルケン、アルコール、ベンゼンなどを発生物資とする合成経路なども整理しておく。
- 天然・合成高分子化合物は、構造や合成反応をしっかり押さえておく。
★全体的に
- 試験時間に対して問題量が多いので、時間配分をよく考えて解く工夫が必要。
- 難問に時間をかけるより、基本的・標準的な問題で失敗しないよう心がける。
- 実験に関する出題について、教科書の実験操作や探究活動にもよく目を通しておく。
- 簡潔に化学現象を説明できるように論述問題に対する対策もしておく。
- 過去問についてよく研究をしておく。過去と類似の問題の出題がみられる。
【生物】
傾向
簡潔な論述力と思考力・考察力を問う
計算問題も頻出、確かな知識がポイント
| 出題形式 | 例年、大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 試験時間は1科目60分、2科目120分 |
| 解答形式 | 例年、選択式は少なく、記述式が主体。リード文の空所補充、用語問題、論述問題、実験設定や実験結果の考察、計算、グラフの描図など多様な出題形式がとられている。 |
出題範囲
- 生物基礎・生物
頻出項目
- 2021〜2023年度は「代謝」「植物の反応」「生態」から続けて出題されている。
- 「遺伝情報」「進化・系統」からの出題も多い。
- 1つの題材から複数の分野にわたって問う総合的な問題も出題されており、「進化・系統」と他の分野を組み合わせた問題の出題が多い。
- 大問の中に「遺伝」に関する問題が含まれていることも多い。
出題内容
- 記述式の空所補充問題が多い
- 教科書レベルの標準的な生物用語や基本的知識を問う問題が多いが、一部の教科書にしか記載のない用語や知識が問われることもある。
- 論述問題は知識・説明中心
- 15〜100字程度の字数制限のあるものが多い。
- 用語の説明や実験に関連した内容説明などが中心。
- 計算問題は頻出
- 標準的な問題集でみられるような典型的な計算問題が多いが、遺伝の考え方に基づく計算には注意が必要。
- 考察問題は表やグラフ・図の解釈が主流
- 実験結果の考察や、表やグラフをもとに考えさせる問題がよく見られる。実験結果をもとにグラフを作成する描図問題が出題されたこともある。
難易度
- 教科書レベルの標準的な問題が中心。
- 知識・理解型の論述、考察型の論述、計算、グラフ理解などがバランスよく組み合わされており、総合力が試される出題。試験時間に対して問題量は妥当と思われるが、標準的な問題を確実に得点し、完成度の高い答案を仕上げることが要求される。
対策
①教科書の学習をしっかりとし、問題集で演習をしよう。
- 出題される問題は大半が教科書レベルの知識を踏まえたものである。
- 教科書を使った学習を繰り返し、どの分野も偏りなく仕上げよう。
- 問題を演習するノートを1冊つくる。
- 苦手な分野はまとめや例題から丁寧に行う。
- 得意な分野は問題演習から行う。わからなくてもすぐに答を見るのではなく、教科書や図説を調べて自分で答えを見つける手間をかけることが大切。
- 教科書や図説の調べた箇所に印をつけておくと、後で復習するときに役立つ。
- 問題集は教科書に準拠した標準レベルから始めるとよい。
②論述してみよう
- 問題集用とは別に論述ノートを作る。
- 問題演習でうまく書けなかった論述が出てきたら、簡単に問題文と答えを書いておき、類似問題に備える。
- 正解を模範解答から書き写すことで、的確な表現や答えなければならない内容への理解が深まっていく。
- 論述する内容にはいくつかの「キーワード」が含まれていることが多い。
- 正解を書き写した後で自分なりに「キーワード」や「キーセンテンス」を探し、チェックして覚えていく。
- 書いた文章を先生に添削してもらうと、採点者から見た欠点がわかり、より効果的。
③過去問で時間配分を確認しよう
- 二次試験直前ではなく、できるだけ早い時期に、必ず試験時間を計って過去問を解いておこう。
- 年度によって、論述量や問題量は異なるが、論述や問題を解くおおよそのスピードを確認しておくことが大切である。
★さらにレベルアップ!
- やや難度の高い実験考察が出題されることもある。
- できれば、『生物〔生物基礎・生物〕標準問題精講』(旺文社)など二次試験レベルの問題を集めた問題集でさらに演習を行っておくとよい。
【地学】
傾向
論述の比重大、計算・描図問題頻出
定番問題だが、正確な知識と思考力・表現力を要求
| 出題形式 | 例年、大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 試験時間は2科目120分 |
| 解答形式 | 論述問題と計算問題は毎年出題されている。描図問題も頻出。他に問題文の空所を補充する記述問題や問題文を読んで語群から適当なものを選ぶ選択問題。 |
出題内容
- 地学基礎・地学
頻出項目
- 例年、地球、宇宙分野を中心に、年度によっては、地史、大気、海洋分野と、バランスよく出題されている。
- 宇宙:太陽系と恒星に関するもの
- 地球:隕石、地磁気、プレートテクトニクス、地震に関するもの
- 地史:日本列島の形成
- 大気:低気圧、前線、風の吹き方、太陽放射
- 海洋:海水の循環、エルニーニョ現象
- 地質・岩石:地質図、地層形成順序
出題内容
- 宇宙分野は計算が多いが、論述問題も出題。
- 地球・大気・海洋分野は論述・記述・計算などの形式で、洞察力を求める設問が多い。
- 地質・岩石・鉱物分野は論述・記述・描図のほかに、地質図やルートマップの読図のような考察を要する出題形式も目立つ。
難易度
- 基礎的事項を問う記述問題や標準的な論述問題が出題されている。また、教科書に掲載のあるような描図問題も頻出。
- 基礎知識だけではなく応用力、表現力も十分身につけておきたい。計算問題は、年度により多く出題されることもある。レベルは標準的であることが多いが、煩雑なものも出題されている。論述問題や描図問題に時間をかけすぎないように注意して解答したい。
対策
①論述対策:解答を簡潔にすばやくまとめる練習が必要。
- まず、教科書や参考書を用いて全般的に広く学習することを心がける。
- 教科書はしっかり理解し、重要語句は、その内容をノートに記述し、整理しておく。
- その上で、過去問はもちろん、問題集の中の論述問題も実際に自分で書いてみる。
- 新書を読んで幅広い知識を得る。
- 地学に関係するテレビ番組、科学雑誌などの内容を簡潔にまとめてみる。
②計算・描図問題
- 計算問題は問題集などで練習しておくこと。
- アイソスタシー、万有引力の法則、ケプラーの法則、恒星の明るさと距離・半径・質量など。
- 計算するときは自分で丁寧にやってみること。
- 宇宙分野の計算問題では、対数の扱い方に慣れておくこと。
- 描図問題は、問題集などを用いてルートマップから地質図を描く練習をし、地質断面図・地質構造図からの読図ができるようにする。
- 教科書や図説の図を多く見て、簡単な模式図を自分で描けるようにする。
③ 頻出分野の重点学習
- 地球分野
- 固体地球の層構造、地震、重力などの内容について整理しておく。
- プレートテクトニクスなども、十分理解を深めておく。
- 地質分野
- 基礎的事項をしっかり学習しておく。
- 岩石・鉱物分野
- 地質・地史、地球分野と関連づけて出題されることも多い。
- マグマと鉱物の化学組成については深く学習しておく。
- 宇宙分野
- 恒星の進化、ケプラーの法則、シュテファン・ボルツマンの法則、ウィーンの変位則、惑星の特徴、太陽とその活動について、教科書の内容を正確に理解しておくこと。
- 大気・海洋分野
- 基本的事項とともに地球環境問題にも関連させて学習しておくとよい。
【国語】
傾向
内容説明が設問の中心となる
古典では文法、口語訳、書き下し文にも習熟しよう
| 出題形式 | 3題(現代文1題、古文1題、漢文1題)
配点は、現代文が80点、古文が40点、漢文が30点。 ※経営学部は2題(現代文1題、古文1題) ※海洋政策科学部は1題(現代文1題) |
|---|---|
| 試験時間 | 100分。経営学部は80分。海洋政策科学部は60分 |
| 解答形式 | 原則として全問記述式。ただし、知識問題などでは選択式のものもみられる。記述式の問題は、漢字の書き取り、内容説明、文法、和歌解釈、口語訳、書き下し文など。説明問題では字数制限がある場合とない場合があり、字数制限がない場合は、解答欄の大きさに合わせて答えなければならない。 |
出題内容
◆現代文
- 本文:人文系・社会系を問わず、比較的有名な著者の重厚な内容の表論が出題。総じて5000字前後と分量も多い。
- 設問:例年5問の出題で、書き取りと内容説明で構成。内容説明は傍線部を軸として前後をきちんと押さえた解答が要求され、最後に「本文全体の論旨」を踏まえた問題が出題される。内容説明の解答の総字数は400字で一定している。
◆古文
- 本文:有名な作品からの出題が多い。大学入試の古文としては標準的。
- 設問:例年、口語訳が出題。文法は敬語法、品詞分解、用言・助動詞の活用形や用法などの基本的な問題。ほかには心情や理由などを答える内容説明問題が複数出題されるのが通例。文学史は例年出題されている。
◆漢文
- 本文:幅広いジャンルから出題。比較的易しい内容のものが多い。
- 設問:書き下し文、口語訳、内容説明など設問形式は標準的であるが、文章の展開を正確に読み取る読解力や応用力が必要。設問で問われる傍線部や波線部は白文(返り点・送り仮名のない文章)となっていることも多い。
難易度
- 文章は読みやすくても、本格的な記述問題が中心で、しかも字数制限のある問題も多いので難易度が高くなっている。
- 解答のポイントとなる問題文の該当箇所を押さえ、短い時間で要領よく解答をまとめる練習を積んで、記述力・論述力を養いたい。現代文が長文であり、現・古・漢いずれも本格的な記述問題主体の設問構成をとっているので、時間配分を考えておかないと、時間切れになる恐れがある。古文や漢文が出題される学部は、現代文50分、古文30分、漢文20分がおおよその目安か。
対策
①現代文:神戸大学の現代文は<読解力が要>である。
- 日頃から新書などに触れ、語彙や思想に関する知識を蓄えながら、論の展開を押さえていく訓練を積んでおく。
- 1日数節、あるいは1章分などと範囲を決め、話の流れを図式化してノートにまとめたうえで、字数を決めて要約していく訓練などは読解力向上に非常に有効。
- 自分で納得するだけではなく、他人が見てもわかるようなまとめ方を心がけると記述力アップにもつながる。
- 設問数自体は少ないが、一つ一つ丁寧な読解を前提としたものが多いので、過去問の演習は必須。過去問を参考にしながら、最初は時間をかけてきちんと解答を書く練習を行うこと。
- 自分の書いた解答を再度見直して書き直す、という作業も記述力向上に効果的。
- 問題集は記述式中心の標準〜難レベルのものを選ぶとよい。
- 160字程度で全文を要約していくと、「本文全体の論旨」を踏まえた設問の練習になる。
☞オススメ参考書『神戸大の国語15カ年』(教学社)
②古文
- 文法力と単語の知識で一文一文に口語訳をつけていく練習を積む。
- 訳出箇所に指示語があれば、具体的な指示内容を把握することを意識する。
- 主語の明示を求める口語訳の設問もあるので、人物関係や動作主も押さえるようにする。
- 古文単語は古語辞典や単語集を十分に活用して学習していく。
- 和歌に表れた心情を説明させる設問や贈答歌の理解を求める設問については、文章内容と和歌の関連を読み取り、詠まれている状況や心情を把握する訓練をしておく。
- 文学史の対策もしておく。
- 記述力については、基本的に現代文と要領は同じであるが、心情説明問題などは古文特有の答えにくさがあるので、過去問や問題集で演習しておく。
- 『体系古文』(教学社)は古文の世界での行動形式や約束事、さらには和歌の解釈についての知識を身につける問題集としてオススメ。
③ 漢文
- 国語便覧などに整理されている句法、構文はしっかり身につけよう。
- 便覧には短めで有名な文章(故事成語が多い)が挙げられているので、それを白文に書き直して、何度も読み下す練習をする。
- その上で教科書に載っている文章を何度も読み、漢文読解の呼吸をつかむ。
- 珍しい出典からの出題も多いので、初見のものでも読み下し、解釈できるように、漢文読解に慣れておく必要がある。
- 過去問や他の国立大学で出題された問題文に当たっておく。
- 頻出の書き下し文は、古文文法にのっとって行われるので、漢文においても正確な古文文法の知識が必要となる。
- 古文学習の際、漢文への応用も視野に入れ、正確な文法力を身につけるよう心がけよう。























































