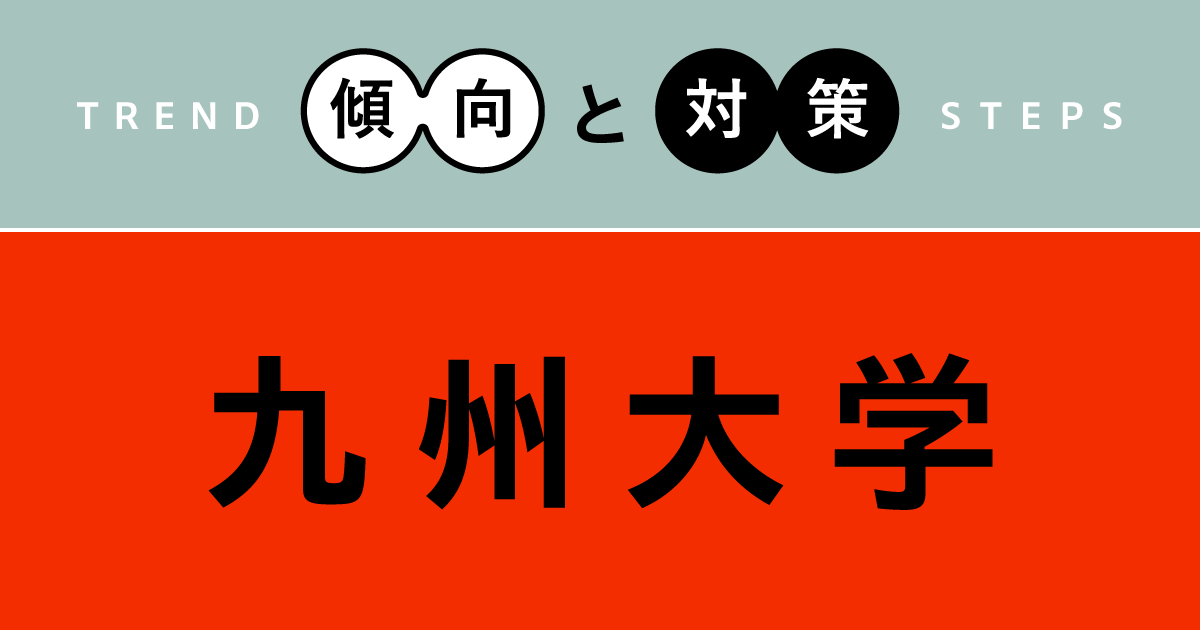
傾向と対策(前期日程)
2023年度までの前期日程の入試問題を分析しました。さらに詳しい最新の分析は「大学赤本シリーズ」をご覧ください。
【目次】
【英語】
傾向
読解・英作文の2本立て 記述中心で、総合的英語力をみる
| 出題形式 | 大問数5題(読解問題3題、英作文2題)
※2023年度の配点は、読解問題が合計120点、英作文問題が合計80点 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
| 解答形式 | 記述式中心(読解問題では一部に選択式の問題がみられる) |
出題内容
①読解問題:例年3題出題
- 読解英文は比較的平易なもので、特別難解な語彙や構文はほとんどみられない。文化・社会・医学・科学などに関する論説文や随筆から物語的なものまで、内容は多岐にわたる。
- 設問内容は、内容説明と英文和訳が中心だが空所補充や内容真偽、要約や同意表現など。
②英作文問題
- 和文英訳は、与えられた日本文の下線部を英訳する形式。問題文はこなれた日本語なので、英訳しやすいように分解・分析して組み立て直す必要がある。
- テーマ英作文・意見論述・要約は、 書くべきテーマが与えられる場合と、まとまった英文を読んでそれに対する意見を述べる場合とがある。テーマは身近なものが多い。
- 語数:2019年度:要約が100語程度、意見論述が50語程度。
- 2020〜2023年度:100語程度。
③資料読み取り
- 資料読み取りは、与えられた資料の内容をそれぞれまとめるもの。
難易度
- 全体としては、問題自体は標準的なレベルだが、記述量の多さを考慮すると、やや高いレベルといえる。
- 読解問題…内容・設問ともオーソドックスなものがほとんど。
- 英作文問題…文法・語彙力に加えて表現力やセンスも要求される高度なものが出題されることもある。
- 読解問題3題と英作文問題2題を120分で解くには、スピードが勝負。時間配分としては、読解各20〜25分、英作文各20分、見直し10分というところか。
対策
①読解問題
- 語彙力:長文読解など日頃から学習の中で出合う単語を確実に覚えていく。
- 辞書を引く際には、派生語やイディオムにも目を通すなどして、知識を増やす。
- 市販の単語集や熟語集は、知識の整理・確認に活用する。
- 速読力:一読して素早く内容をつかむ練習は不可欠。
- さまざまな分野の英文を、正確にしかも短時間で読み取る訓練をする。
- 指示語が何を指しているか、また、文の構造がしっかり理解できているかを確認しながら読み進める習慣をつける。
☞オススメ参考書『大学入試 ぐんぐん読める英語長文〔STANDARD〕』(教学社)
- 表現力:内容説明・英文和訳など、記述式の問題が中心なので、しっかりした国語力が求められる。日頃から積極的な読書を心がけ、国語力の充実に努める。
- 過去問や問題集を利用して、答案を書く練習を積んでおく。
- 書いたものは必ず読み返し、解答例と比較するなどして、よりこなれた日本語になるよう工夫する。
☞オススメ参考書『九大の英語15カ年』(教学社)
②英作文問題:まず、教科書を利用してしっかりした基礎を築くことから始める。
point!
- 英作文や英文法の教科書の基本例文のなかから、重要な文法事項や慣用表現を含む文を抜き出して徹底的に暗記する。
- 読解の練習などを通じて、良質の英文に数多く触れ、使いこなせる表現を増やす。
- 和文英訳 : 与えられた日本文の下線部を英訳する形式。問題文はこなれた日本語なので、英訳しやすいように分解・分析して組み立て直す必要がある。
- 問題集や過去問を利用して何度も練習する。
- 書いた英文は、学校や塾の先生に添削してもらう。
- テーマ英作文・意見論述・要約
- 英語で文章を書くことに慣れる。
- 慣れたら100語程度での要約に挑戦。
- 次に、身近な出来事や、新聞のニュースなどからテーマを選び、自分の意見や経験についてまとめた内容の英文を作ってみる。 ⇒その際、できるだけ易しい表現で書くように努める。そのほうが読み手にとっても理解しやすく、説得力のある文が書けるものである。
- 資料読み取り
- 実際に書いてみるのが一番の訓練になる。
- そのなかで、表・グラフに限らずいろいろな資料に対して使える汎用性の高い表現を身につけておきたい。
- このような練習を繰り返すことにより、英語で表現することが習慣化し、どのようなテーマであっても短時間で的確な英文が書ける力がついてくる。
★過去に出題された資料読み取り問題は…
2021年度:表に示された「アメリカの大学への留学数の変化」…70語程度
2022年度:グラフで示された「UFOの目撃数の変化」…75語程度
2023年度:2つのグラフで年齢層別に示された「ある年の日本国民の人口」と「同年の在留外国人の人口」の違いを説明し、その違いの理由を推測する。…語数ではなく、使用する文の数を指定。
【数学(理系)】
傾向
小問での誘導がついた標準レベルの良問
| 出題形式 | 大問数は5題 |
|---|---|
| 試験時間 | 150分 |
| 解答形式 | 全問記述式 |
出題範囲
- 数学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B(数列、ベクトル)
頻出項目
- 微・積分法、確率、ベクトル
- これに加えて、整数の性質や複素数平面もよく出題されている。
問題の内容
- 例年、問題には小問が設定されていることが多く、その小問の巧みな誘導で最終的な結論に導かれるタイプの問題が多いことが特徴。
難易度
- 近年はおおむね標準レベルの問題中心で落ち着いていたが、ここ数年難化が続いている。
- 1題あたり、30分程度で解くことになる。問題のレベルを最初によく見極めて、解きやすい問題から手早く解いていくことが大切である。
対策
①小問による誘導にうまく乗った解答の流れをつかむ訓練をする。
- 特徴として、小問による誘導が施されていることが多く、問題により程度の差はあるが、小問が巧みに配置されて最終的な結論に結びつけられている。
- 解答に詰まったときに、小問による誘導から解答の流れを考えてみることで方針が立つこともある。 例えば…「上の設問でなぜこのようなことが問われていたのか」 「次の設問でなぜそのようなことが問われるのか」 など考えてみる。
- 普段から、小問をただ一つ一つ個別に処理していくのではなく、大問全体を見渡し、その中での各小問の役割を意識しながら問題演習に取り組もう。
② 普段から答えを出すまで粘り強く計算する習慣をつける。
- 基本的には問題を解いていく中で速く正確に計算することを強く意識して取り組む。
- 計算問題集の利用。
☞オススメ参考書『数Ⅲ(極限、級数、微分、積分)試験に出る計算演習』(河合出版)
※基本からかなりレベルの高い計算問題まで扱っている。
③ 論理的にしっかりとした答案を作成する訓練をする。
- 証明問題もよく出題されている。
- 結論から逆にたどり、スタートの仮定の条件から筋道をつなげることを意識すると考えがまとまりやすい。
- 解答スペースが十分ある。
- 大学が論理的にしっかりとした答案を要求していることがうかがえる。「論理的な誤りはないか」「例外事項を落としていないか」「もっと簡単に示す方法はないか」など、常に解答の道筋に気を配る習慣をつける。
- 学校の先生に答案の添削を受けたり、添削教材を利用するのもよい。
④ 普段から、題意に沿った的確な図を描いて考える練習をする。
- 例えば…方程式の実数解をグラフとx軸との共有点のx座標と対応づける。など
- 一見、数式だけで解く問題のようでも、それを図形的な問題に置き換えてみることで問題の核心が見えてくることは多い。
- 図を参考にして考えれば、案外たやすく解法の糸口や適切な発想が浮かんでくることもあるし、応用が利くような形で解き進めていくこともできる。
- 2019・2021・2022年度には図示問題も出題されている。
⑤ 過去問の研究:「解けなくてもいい」を前提に、早い段階で過去問に触れる。
- まずは早い段階で、過去問に挑戦してみて、最終的に自分がどのレベルに達する必要があるのか確認する。
- 過去問は最新のものから解いて過去にさかのぼっていくのがオススメ。
- 初めは解けなくてもOK。解答時間を長めに設定し無理のない範囲で演習してもよい。
- その過程で内容のレベルを体感する。
☞オススメ参考書『九大の理系数学15カ年』(教学社)
※分野別に編集されてレベルも明記されており、解答・解説もかなり詳しくわかりやすい。
- 近年難化傾向にあると述べたが、数年かけて易化し続けたものが難化し、以前のレベルに戻ったという印象なので、過去問を研究しておけば全く問題ない。
- 教学社のホームページでは解答用紙がダウンロードできるので、実物大にプリントして過去問に限らず普段の演習にも活用してほしい。
【数学(文系)】
傾向
小問での誘導がついた標準レベルの良問
| 出題形式 | 大問数4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分 |
| 解答形式 | 全問記述式 |
出題範囲
- 数学Ⅰ・Ⅱ・A・B(数列、ベクトル)
頻出項目
- 微・積分法、ベクトル、確率
- 余弦定理や数列の和の公式など、基本的な事項についての深い理解が問われるものが証明問題として出題されることもある。
問題の内容
- 例年、問題には小問が設定されていることが多く、その小問の巧みな誘導で最終的な結論に導かれるタイプの問題が多いことが特徴。
難易度
- 近年はおおむね標準レベルの問題中心で落ち着いていた。
- しかし、2021年度でやや易化⇒2022年度でやや難化して元のレベルに戻ったか若干難しめになり⇒2023年度はそのレベルが保たれているという印象がある。極端な難問は出題されない。
対策
① 小問による誘導にうまく乗った解答の流れをつかむ訓練をする。
- 特徴として、小問による誘導が施されていることが多く、問題により程度の差はあるが、小問が巧みに配置されて最終的な結論に結びつけられている。
- 解答に詰まったときに、小問による誘導から解答の流れを考えてみることで方針が立つこともある。 例えば…「上の設問でなぜこのようなことが問われていたのか」「次の設問でなぜそのようなことが問われるのか」 など考えてみる。
- 普段から、小問をただ一つ一つ個別に処理していくのではなく、大問全体を見渡し、その中での各小問の役割を意識しながら問題演習に取り組もう。
② 普段から答えを出すまで粘り強く計算する習慣をつける。
- 文系学部としては、かなりの計算力を要する問題が出題されることもある。
- 基本的には問題を解いていく中で速く正確に計算することを強く意識して取り組む。
- 計算問題集の利用。
③ 論理的にしっかりとした答案を作成する訓練をする。
- 証明問題もよく出題されている。
- 結論から逆にたどり、スタートの仮定の条件から筋道をつなげることを意識すると考えがまとまりやすい。
- 解答スペースが十分ある。
- 大学が論理的にしっかりとした答案を要求していることがうかがえる。 「論理的な誤りはないか」「例外事項を落としていないか」「もっと簡単に示す方法はないか」など、常に解答の道筋に気を配る習慣をつける。
- 学校の先生に答案の添削を受けたり、添削教材を利用するのもよい。
④ 普段から、題意に沿った的確な図を描いて考える練習をする。
- 例えば…方程式の実数解をグラフとx軸との共有点のx座標と対応づける。など
- 一見、数式だけで解く問題のようでも、それを図形的な問題に置き換えてみることで問題の核心が見えてくることは多い。
- 図を参考にして考えれば、案外たやすく解法の糸口や適切な発想が浮かんでくることもあるし、応用が利くような形で解き進めていくこともできる。
- 2021年には図示問題も出題されている。
⑤ 過去問の研究…「解けなくてもいい」を前提に、早い段階で過去問に触れる。
- まずは早い段階で、過去問に挑戦してみて、最終的に自分がどのレベルに達する必要があるのか確認する。
- 過去問は最新のものから解いて過去にさかのぼっていくのがオススメ。
- 初めは解けなくてもOK。解答時間を長めに設定し無理のない範囲で演習してもよい。 ⇒ その過程で内容のレベルを体感する。
- 教学社のホームページでは解答用紙がダウンロードできるので、実物大にプリントして過去問に限らず普段の演習にも活用してほしい。
【物理】
傾向
力学・電磁気中心の出題
計算問題を中心に、描図・論述問題にも注意
| 出題形式 | 大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 理科2科目で150分 |
| 解答形式 | 文字式による計算問題が主。 その結果のみを求める(解答用紙には答えだけ記入)問題が大半を占める。
論述問題。過去には導入過程の記述を求める問題が出題された。 描図問題は、例年、グラフ作成問題を中心に主題。 |
出題範囲
- 物理基礎・物理
頻出項目
- 例年3題中2題は力学と電磁気分野からの出題。
- 力学…運動方程式、エネルギー保存則、運動量保存則の三本柱を中心として、円運動や単振動を含んだ力学全般にわたった総合問題となっている場合が多い。
- 電磁気…電磁誘導、電磁場中での荷電粒子の運動、抵抗とコンデンサーとコイルを含んだ回路の問題などがよく出題されている。
- もう1題は、例年は熱力学または波動、他に原子と波動の融合問題など。
問題の内容
- すべての分野にわたって、基本問題から応用問題まで幅広い内容と難易度の出題であるから、典型的な問題を中心に、幅広く学習しておく必要がある。標準的な問題が多いが、普段あまり見慣れない問題や、難易度の高い問題も含まれ、題意の正確な把握と理解が要求される。
難易度
- 標準的な出題がほとんどだが、力学および電磁気を中心にして、かなり難度の高い問題や、数学的な計算力が要求される出題もみられる。
- 平素の学習では、典型的な標準問題が確実に解けるように訓練し、さらに、与えられた条件のもとでの受け身の学習ではなく、常に問題解決のために何が必要かを自問しながら学習していく必要がある。
対策
①典型的な問題の幅広い学習を
- 標準的な問題も多いが、表面的な理解で公式を適用するだけの学習では対処できない問題もよく出題されている。
- まずは、教科書で扱われている程度の事項はきちんと学習し、公式を導く過程や物理量の定義などの本質的な理解を図ることが大切。
②応用力・思考力の養成を
- 教科書傍用や標準的な問題集を完全にこなして、基本事項の徹底を図る。
- その上で、応用力や思考力を養うために、赤本や定評のある問題集に取り組むのが良い。ただし、いたずらに数をこなすのではなく、問題の背景や計算結果のもつ意味を考えてみるなど、一歩踏み込んで掘り下げるような勉強も必要。
- 別の解法を考えるような練習もしておくとよい。 ⇒未経験の問題に対処するための柔軟な思考力やセンスを養うには、こういう積み重ねが大切である。
③計算力の養成を
- 煩雑な計算を要する問題も含まれている。
- 問題演習に際しては、面倒がらずに、計算過程を示しながらきちんと計算することが大切。
- 近似計算も出題されるので、手際よく処理できるように慣れておく必要がある。
④描図・論述問題の準備を
- 描図問題:教科書にあるような作図は自分でひととおりこなし、グラフを書く練習もしておき慣れておくこと。教科書程度の基本的な問題から、物理的な意味を正しく理解していなければ描けない問題、考察力を要する問題など多岐にわたっている。
- 論述問題:考察理由を簡潔な文章に書き表すような練習を普段からしておく。自分の言葉で説明を試みることによって、より理解が深まる効果も期待できる。
【化学】
傾向
理論・有機中心の出題 読解力、計算力、応用力で差がつく
| 出題形式 | 例年大問5題(2021年度は大問4題) |
|---|---|
| 試験時間 | 理科2科目で150分 |
| 解答形式 | 記述式が中心(物質名や化学式、反応式、構造式など)。
計算問題(解答欄に結果のみを書く形式が多い)。 年度により論述問題、描図問題、選択式問題など。 |
出題範囲
- 化学基礎・化学
出題内容
- 基本的には理論と有機中心の出題。無機は理論と絡めて出題されることが多い。
難易度
- 標準問題から発展問題まで出題範囲は幅広い。
- 例年、思考力や応用力の必要な設問が目立ち、基本的な内容も多く出題されている。
- 問題文の説明をよく理解していないと解答しにくい設問が多く、問題演習の量と思考力、および計算力で差がつきやすい内容。大問5題であれば大問1題あたり約15分で解くこととなり、試験時間に余裕があるとは言えない。大問により難易度に幅があるので、時間配分と解く順序に注意が必要。
対策
①理論
- 全体的には理論分野の比重が大きく、無機分野や有機分野の大問でも、理論分野の設問が組み合わされることが多い。基礎から応用まで幅広く出題されるので、化学の全範囲にわたって漏れのない学力をつけておくことがまず重要。
- 原子の構造と物質量、熱化学、酸・塩基と塩、中和反応とpH、酸化還元と電池・電気分解などについて標準問題を数多く解き、基礎力を固める。
- よく出題される電子配置や化学結合に関する基礎知識はしっかり固めて、応用できる力を養っておく。
- 化学平衡の内容は例年さまざまな形で出題されているので、類題で演習を積んでおく。
- 高校生にはあまりなじみのない発展的な内容(気体や溶液の濃度、反応速度などに関する文字式や定数および単位の取り扱い等)でも、問題の誘導に従って慎重に解き進めれば解答できるものも多いので、粘り強く取り組む姿勢も大切である。
- 新傾向の設問や、思考力・応用力の必要な設問に対応するためには、レベルの高い問題に取り組み、研究しておくのが有効。
②有機
- 例年、後半の大問は有機分野からの出題であることが多い。出題パターンが比較的限られていて対応しやすい場合もあるので、早い時期にこの分野を確実な得点源にできれば、その後の対応が楽になる。
- 脂肪族・芳香族ともに代表的な化合物の性質や反応を系統的にまとめ、反応名や構造式、化学反応式を細かいところまで確実に書けるようにする。
- 元素分析と化合物の構造決定に関しては、しっかり演習し、異性体の立体構造などの思考力重視の問題まで十分慣れておく。
- 天然高分子・合成高分子ともに、教科書レベルの化合物の構造、単量体と重合の仕方などに関する知識を確実にし、高分子特有の計算問題にも慣れておく。
③無機
- 単独の大問として出題されることは少なく、理論と絡めて出題されることが多い。
- 教科書レベルの化学式や反応式は、細かなところまで確実に書けるようにする。
- 化合物の性質を原子の電子配置と周期表の原理、イオン化エネルギーや電気陰性度などの理論とあわせて系統的に理解しておくと、応用力もつく。
- この分野の定番である気体の製法と性質、金属イオンの反応と錯イオンの構造や性質、ハーバー・ボッシュ法やアンモニアソーダ法などの工業的製法に関する内容については、計算問題も含めて確実に得点できるようにする。
④実験考察問題対策
- 教科書の探究活動などに目を通す。
- できるものは自分自身で実験を行ってみる。
- 代表的な実験内容である…気体の分子量測定、中和滴定、電池と電気分解、気体の製法、金属イオンの反応、有機化合物の合成、検出と分離 などに関しては代表的な実験を『実験の目的・装置・操作方法・結果』などに分けて整理しておく。
- 実験リポートなどを活用して実験方法や実験結果の意味をよく理解しておく。
- 試薬の保管方法の調製方法なども実際に確かめておく。
⑤計算・論述問題対策
- 計算問題
- 普段から電卓に頼らず自力で最後まで計算すること。
- 問題集や過去問で多くの計算問題に当たり、さまざまな定数や単位の取り扱いに慣れておく。
- 有効数字の扱いにも注意する。
- 論述問題
- 化学用語を正確に用いること。
- 設問意図にあった答案を書くことを心がける。
- 自分で実際に書く練習を重ねる。
【生物】
傾向
正確な知識、柔軟な思考、的確な論述力が要求される
| 出題形式 | 大問5題 |
|---|---|
| 試験時間 | 理科2科目で150分 |
| 解答形式 | 選択・記述・論述・計算・描図とバラエティーに富む。
空所補充(生物用語)。論述問題は必出。字数指定のあるものが多い。 |
出題範囲
- 生物基礎・生物
頻出分野
- 幅広い分野から出題されているが、考察力を要する設問が目立つ。
- 遺伝情報…例年1題は必ず出題される最頻出分野。
- 定石的な問題も出題されるが、通常とは若干視点の異なる、取り組みにくい問題も目立つ。
- 体内環境、動物の反応
- 興奮の伝導、伝達、視覚・筋収縮など神経調節に関連した出題が目立つ。続いて、免疫や腎臓を絡ませた体液の恒常性からの出題が多い。
- 内容を深く考えさせる問題や少し視点の異なった問題が多いことも特徴的。
- 代謝、細胞…光合成、呼吸、酵素などがよく出題される。
- 光合成については、定石的な問題のほか、生態や植物の反応の分野と絡めて出題されることもある。
- 細胞内での物質輸送、浸透圧、ナトリウムポンプ、細胞の成分(水・タンパク質)などが植物生理や代謝、腎臓と融合されて出題されている。
- 細胞周期とDNA量についての出題もある。
- 他分野の大問中で小問としてこれらの知識を問われることもある。
- 生殖、発生
- 生殖細胞形成および発生の仕組みからの出題が目立つ。
- 誘導物質と受容タンパク質、iPS細胞、アポトーシスなど、より高度な題材が出題されるようになった。
- 生態、進化・系統…生物の総合的学力が問われることが多い。細部の項目まで確実にしておきたい。
- 「生態」…生物多様性、個体群、物質循環などの出題がみられる。また個体群と生物多様性の融合問題が出題されたこともある。計算問題にも注意。
- 「進化・系統」…発生・遺伝・生態などの他分野との融合の形で出題されていることも多い(例:生物の進化と生物多様性)
難易度
- 全体的に標準レベル。
- かなりの思考力や詳細な知識を要する設問が出されることもあり、さらに、計算や論述など出題形式が多様であるため、知識・考察力・論述力など高い実力を持っていないと十分には対応しきれない。1科目あたり75分で5題を解くので、1題15分程度しかない。知識問題を手早く解いて、論述問題に時間を割きたい。
対策
① 知識の増強
- 教科書を中心に生物用語、模式図などを理解しながら確実に覚える。さらに、参考書や用語集などで、知識をよりきめ細かく肉付けしていくとよい。
- 各分野の諸事項は個々に記憶するだけではなく、分子レベルや進化・系統の視点などからも総合的にとらえるようにする。
② 問題演習
- 教科書傍用問題集などによる問題演習。
- ややレベルの高い問題集で、さらに考察力や総合力を養成する。
- 同じ問題集を何度も繰り返し使うことで、知識の定着を図ることが大切である。
③ 論述力の養成
- 教科書巻末の索引にある主な生物用語の内容を30〜100字程度でまとめる。
- サブノートを自分の納得のいく言葉で作ったりする。
- まとまりのある自分の文章を数多く蓄えていくことが重要。
- 必ず自力で書いてみてから解答例と引き合わせ、比較・検討するとよい。
- 学校の先生に添削してもらうとよい。
④ 実験・観察
- 教科書で取り扱われている実験・観察はすべて、材料・器具・薬品・実験方法とその留意点を整理しておく。
- 仮説に対する考え方、結果の処理法や考察にも目を配り、仮説がどのように検証されているかを自分なりに理解しておく。
【地学】
傾向
論述問題が頻出、計算・描図問題も!
地球・宇宙・大気分野は最頻出
| 出題形式 | 大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 理科2科目で150分 |
| 解答形式 | 選択式と記述式の併用であるが、記述式の割合が大きい。
選択式…語句や数値、正文・誤文の選択問題 記述式…用語・数値の記述 論述問題…字数指定(30~120字程度)が多い 他に計算問題、描図問題 |
出題範囲
- 地学基礎・地学
頻出項目
- 地球、宇宙、大気分野は最頻出。海洋、地質、地史分野は頻出傾向。
難易度
- 全体として、標準〜やや難のレベル。
- 単純に計算すると、1題あたり20分弱で解くことになる。年度によっては計算問題に時間を要するものがあったり、物理や化学の知識を要する難問が出題されることもあるので、時間配分には注意が必要である。
対策
① 基礎力の充実
- 教科書・参考書の図や写真・グラフなどを見て視覚を通じて理解する。
- 簡単な計算問題を解いて、さまざまな現象や法則を数量的に把握することも理解を深める上で効果的である。
- 教科書のサブノートをつくり、地学用語とその用法に慣れる。⇒ 論述対策にもなる!
- 地質時代区分表(絶対年代も)や岩石分類表は完全に暗記しておくこと。
② 論述・計算問題対策
- 論述問題:教科書傍用程度の易しい問題集を1冊仕上げて、地学用語とその用法に慣れてから、赤本の過去問や他大学の論述問題で論述演習をしておく。
- 最初は字数にこだわらず自由に論述し、これを手直しして制限字数に収めるやり方で練習するのも一つの方法。自分が書いた文章が解答例の文章と同じでなくてもよい。ポイントを外さず、論旨が首尾一貫していることが大切。
- 計算問題:難しい計算もあるので、受験本番までに計算問題集を1冊仕上げることも一つの目標にする。
- 対数計算・指数計算やラジアン(弧度法)、対数グラフなど、慣れを要する計算やグラフが出題されることがあるため、必ず練習しておくこと。比熱・遠心力・万有引力などの物理公式の使い方や化学の知識を要する計算は、赤本の過去問で演習し、徹底的に研究しておきたい。
③分野別対策
- 地球分野
- 重力・地震波・プレートテクトニクスを中心に理解しておく。
- 火山とマグマについても頻出。
- 物理法則を用いる計算の練習。
- 宇宙・大気・海洋分野
- 宇宙分野は特にケプラー3法則、HR図、ハッブルの法則、銀河系の構造についてしっかり理解する。
- 大気と海洋分野はエルニーニョ現象、高層天気図などについても学習を深める。
- 地質・地史、岩石・鉱物分野
- 相互に関連づけて理解することが必要。
- これに関連して、地質時代区分表は示準化石や絶対年代、火成岩分類表は鉱物組成や化学組成の特徴を覚えてしまうくらい使いこなそう。
- 付加体の具体的な地質構造も重要⇒プレートテクトニクスの視点に立ってきちんと理解しておく。
- 空所補充・記述問題では基礎的な地学用語の知識を問うものから出発して、それらに関連して理由を説明する論述問題が課される、という形式が多い。幅広い確実な基礎力をベースに、考察力・表現力を身につけておかないと十分には対応できない。
【日本史】
傾向
歴史理解と史料の読解・分析力が試される 論述にも注意
| 出題形式 | 大問4題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 記述問題と論述問題〔基本的に字数指定(各25〜135字)有り〕。
論述問題は、大問1題につき1〜3問の構成 |
出題内容
- 時代別…(原始・)古代、中世、近世、近現代から各1題という出題。
- 分野別…文化史、政治史、外交史。江戸時代の貨幣史や近現代の産業史など定番の題材も頻出。
- 史料問題…頻出。リード文に使用されていることもある。設問の中に史料があり、それを参考に解答を導くというものが多い。頻出史料だけではなく、初見の史料も多い。
難易度
- 全体的にはやや難。
- 設問の要求に応じて迅速に要点をまとめる論述力が要求される。
- 用語を問う問題に手早く的確に解答し、論述問題にじっくり取り組む時間を確保するなど、時間配分にも工夫が必要。
対策
①教科書の徹底整理:教科書の学習が基本
- 教科書に太字で表記されている重要事項については、前後の文章から歴史的位置づけをしっかりとらえ、できれば用語集などの説明文を読んで理解を深める。
- 論述問題において、それぞれの視点から背景が理解できているかどうかが問われている。
- 教科書学習では各時代の根幹的な支配の特徴などを把握するとともに、さまざま時代背景にも注目して歴史理解を深めるという姿勢で臨み、論述問題に対応できる力をつける。
②論述対策を重視:とにかく文章を書くことから始めよう。
- 30字程度の短文のものから、500字程度の長文のものまで想定して練習しておく。
- 日頃からオリジナルノートをつくり、まとめる練習をする。
- 字数が少ない場合、簡潔で的確にまとめる力が要求される。
- 各時代の支配の根幹となる制度や法制、また著名な事件・条約などについて、その背景・内容・結果などを、簡潔に短文でまとめる習慣をつけておく。
③多くの史料になじみ、読解力を養う。
- 教科書に載っている基本史料はもちろん、史料集などにも必ず目を通しておく。
- 初見史料が出題されても、出題意図を正確に抽出できるようにする。
- 史料集の解説文は、教科書とは違った角度からわかりやすく書かれており、史料とともに熟読しておく。論述対策にもなる。
- 史料集とあわせて図録などを利用した学習も忘れないようにする。
- 近年、絵画などの視覚資料や寛永通宝の図版を使って文字の配置を答える問題が出題されている。
④ 記述問題対策
- 人物や歴史用語で基礎的知識であるが誤字を招きやすい用語が出題されている。
- 例えば…「鞍山製鉄所」(2019年度)、「藤原煋窩」(2021年度)、「煬帝」「犬上御田鍬」(2022年度)、「重祚」(2023年度)
- 日頃から正確に漢字を記述する練習を欠かさないようにする。 ⇒漢字でしっかり書ければ得点源、ミスなどで失点を重ねると致命傷となる。
⑤ 練習問題・過去問に取り組もう!
- 論述問題:とにかく書く練習をする。
- 高校の先生などに答案を添削してもらう。
- 塾・予備校の季節講座などで開設される論述講座も積極的に利用する。
☞オススメ参考書『段階式 日本史論述のトレーニング』(Z会)
- 過去問にも必ず取り組む:類似問題が出題されることも多い。
- 九州大学と類似したタイプの問題を出題する大学として…北海道大学、新潟大学、名古屋大学、東京都立大学、愛知教育大学などがある。
- 長文の論述対策としては…筑波大学、京都府立大学、新潟大学
- 論述問題は字数の違いは多少あるが、類似するものが多いので、赤本シリーズを利用して取り組んでみよう。
- 全体としては教科書本文程度の内容で構成されており、脚注レベルが若干ある程度である。ただし、論述問題では史料の読解力と分析力を必要とするものであり、年度によっては長文論述が出題されることもあるので、90分という試験時間を考えると、決して易しいとはいえない。
【世界史】
傾向
〔1〕は長期的で広範囲な視野が求められる
〔2〕〔3〕で確実に得点することが必須
| 出題形式 | 大問3題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 出題形式 | 〔1〕長文論述(500字または600字)。
〔2〕論述法(40字〜180字で2〜4問)と記述法が主体。 〔3〕記述法が主体(過去には論述法が出題されたこともある)。 |
出題内容
- 時代別…〔1〕近代以降が目立つ出題。〔3〕古代から現代まで幅広い時代から問われる傾向が強い。
- 地域別…〔1〕欧米中心の出題が続いていたが、2023年度は東欧と中東であり、従来の傾向からややはずれた地域から出題された。〔2〕地域的に幅広く出題されている。〔3〕アフリカやラテンアメリカ、東南アジアも含めた幅広い地域から出題されている。
- 分野別…政治史と人口動態も含めた社会経済史が中心。他に宗教、文化史。
難易度
- 全体的には教科書や用語集のレベルを超えた出題はない。
- しかし、〔1〕の長文論述問題はスケールの大きいテーマで、幅広い知識や正確な理解が求められ、限られた時間で500〜600字という長文をまとめるにはかなりの文章力も必要となる。この問題の出来・不出来が成否を大きく左右すると思われる。一方、記述問題の大半は教科書・用語集の知識で対応できる標準レベルであるため、かえって失点は許されない。
- 記述問題や選択問題をスピーディーに解答し、長文論述問題に時間を割きたい。長文論述問題でどれくらい得点を上乗せできるかが決め手となるだろう。
対策
①まずは教科書の精読を第一に行おう。
- 教科書に記された事項を正しく理解することこそ、学習の土台となる。
- 教科書の精読とは…一つの歴史事項に出合ったら、その事項が歴史の流れの中でどのように位置づけられるかがすぐ思い描けるくらい読み込むことである。
※本文だけでなく、脚注や地図、図版・写真の視覚資料にも注意。そのようなところにこそ、問われるポイントが潜んでいることも多い。
- その上で、よくわからない箇所(「なぜそういえるのか」「どういう意味なのか」)に出合ったら、それを用語集や資料集・参考書を利用して調べていく。
- 知識は増大し、論述問題に対応できる力も身につくはずである。
- 『世界史用語集』(山川出版社)などの用語集の併用で、自分の使用している教科書では取り上げられていないような歴史事項を確認・理解する。
- その上で、よくわからない箇所(「なぜそういえるのか」「どういう意味なのか」)に出合ったら、それを用語集や資料集・参考書を利用して調べていく。
- 教科書の精読とは…一つの歴史事項に出合ったら、その事項が歴史の流れの中でどのように位置づけられるかがすぐ思い描けるくらい読み込むことである。
②〔1〕の長文論述対策に重点を置く。
- わかりやすい使用語句(10個前後)が指定され、これを論点のヒントにすれば対処しやすい。
- 論述問題のパターンはいろいろ考えられるが、大きく次の2つに分ける。
(1)特定の国家・地域・テーマを通史的に述べる問題
- 問題の使用指定語句を手がかりに、教科書の各時代で記されている該当国(該当地域)やテーマに関する部分を導き出し、それを設問に沿って連結させるとよい。
- 指定語句を時系列で並べ、それぞれの語句から推測される状況を想起し文章化する。
- 教科書などから設問に対応した部分を導き出せる力の育成が必要
★例えば…オランダ、ポーランドといった国の通史は、教科書でとびとびに記述されている部分を自分で探して簡単な年表を作ってみる。
- 教科書などから設問に対応した部分を導き出せる力の育成が必要
(2)特定の時代の諸国家・諸地域の様相や関係について述べる問題
- 論述対象となる国家(地域)が複数であることから、各地域の時代状況を想起した上で設問の要求を徹底的に考え、指定語句を「分類」し、論述の構成を決めてから文章を書くことを勧める。
- 設問の要求と指定語句の関係性を自分で考えて「分析」したうえで論述しなければならない。
★教科書の囲み記事やコラムを参考に…「海の道による東西世界のつながり」「大航海時代の世界」「環大西洋革命」といった項目に注目。これらを徹底的に読み込んで理解しておく。
③中論述・小論述対策(40~180字程度)
- 歴史用語を正確に説明できるようにしておこう。
- 全体の構成力よりも歴史事象に対する理解の度合いを試されるものが多い。
- 歴史事象の<原因・背景>や<結果・影響>をしっかり把握しておく
- 例えば…1919年の「五・四運動」はなぜ起こり、どのような影響を与えたのだろうか。
④記述問題対策をおろそかにしない。
- 高得点を得るためには、〔2〕〔3〕の記述問題で失点しないことが大前提。
- 〔1〕の長文論述での指定語句の理解にも歴史用語を覚える学習は必要。
- 「語句を覚える」といっても名前だけを覚えるのではなく、その語句の意味や他の事項とのつながりを理解する。
⑤ 赤本シリーズの活用
- 特に長文論述問題は他大学の問題にもあたってみる。
- 例えば…東京大学は出題形式や難易度において九州大学とほぼ同じなので、赤本シリーズに加え『東大の世界史25カ年』(教学社)を徹底的に読み込む。
- 他には、京都大学、筑波大学などの論述問題にも挑戦してほしい。
【地理】
傾向
100~300字の論述問題中心 答案作成の練習を十分に
| 出題形式 | 大問2題 |
|---|---|
| 試験時間 | 90分 |
| 解答形式 | 論述問題中心。80〜300字の論述問題が4〜6問出題されている。
他に選択問題。 |
出題内容
- 統計表やグラフに示されたデータに該当する都市・都道府県・国・農作物の判断といった記述・選択問題も見られるが、出題の中心は論述問題。
※取り上げられる事項は年度ごとに限定されている。
難易度
- 難問は見られないものの論述問題が多く、さらに統計資料の判読・分析が必要で答案作成に手間取りがちな問題が多い。
- 大問2題で90分なので1題あたり45分と余裕があるように思えるが、迅速な答案作成能力が要求される。
対策
①100~300字の論述問題が出題の中心…論述対策をしっかりと
- 試験時間に対して論述量が多いので、スピーディーに答案を作成することを意識する。
- 同様の長文論述が出題されている他大学の過去問にも取り組む。
- 例えば:大阪大学、筑波大学(理系)、新潟大学など
②地理的リテラシーを磨く
- 統計資料問題のウェートが高い。 ⇒スピーディーかつ正確に統計資料を判読・分析できるよう、地理的なリテラシーをしっかり磨く。
③攻略の手薄な分野を作らない
- 大問2題の構成が続いており、取り上げられる内容が特定分野に偏ることが多い。
- 目標点を獲得するためには攻略の手薄な分野をつくらないことが重要。
④地形図読図対策も
- 近年、出題されていないが、さまざまな地理現象を多面的に取り上げることができるため、今後、出題される可能性がないとはいえない。
- 習熟するのに手間のかかる地形図読図の対策にもしっかり取り組んでおくようにしたい。
【国語】
傾向
記述・論述にも対応できる読解力と表現力を
| 出題形式 | 文学部…現代文1題、古文2題、漢文1題
教育・法・経済(経済・経営)学部…現代文2題、古文1題、漢文1題 経済(経済工)学部…現代文2題(※教育・法・経済(経済・経営)学部と同一問題) ※現代文の1題、古文の1題、漢文が全学部同一問題もしくは類似問題(問題文は同一で設問の一部が異なる)となっている。 |
|---|---|
| 試験時間 | 120分(経済(経済工)学部は80分) |
| 解答形式 | 記述式、ごく一部に選択式が含まれる。 |
出題内容
- 現代文
- <本文>例年評論から出題。現代の社会状況との関わりの深いテーマのものが取り上げられている。人間・社会、文化、言語など、さまざまな領域にわたっており、レベルが高いだけではなく、ユニークな論旨のものが目立つ。問題文の長さは1題2000字から4000字程度で、国公立大学の二次試験としては標準的な長さ。
- <設問>論理的な読解力を問う説明問題が中心であり、解答量も多い。
- 古文
- <本文>中古〜近世の各時代から出題されている。ジャンルも多様。1題は共通問題。1題は文学部のみの問題。
- <設問>例年、口語訳・内容や心情の説明・和歌解釈など、読みの正確さと深さを見る設問が中心で、文法・文学史・読みなどの古文常識を含めて知識を問う設問が加えられている。
- 漢文
- <本文>有名作品から、受験生はあまり目にしないような作品まで多彩。
- <設問>訓読・書き下し文・句法など漢文の定番設問と、内容説明・口語訳・主旨などの読解力を問う問題がバランスよく出題されている。
難易度
- 国公立大学の二次試験の国語の中でも難しい部類に属する。
- 現代文・古文・漢文ともに記述・論述の解答量が多く、試験時間を有効に使い、その間集中力を維持することも課題となる。比較的読みやすい文章が出された大問は手早く仕上げるようにするとよいだろう。
対策
現代文
①記述力・論述力の鍛錬
- 過去問や問題集での演習、模擬試験の見直しなどあらゆる機会をとらえて、思考・判断の力を鍛える。
- 論旨の核心を押さえ、解答の方向を決め、内容を組み立てるなどのプラン作りと、それを具体的に文章化する練習をする。
- 必ず下書きをして推敲し、解答の内容と表現を客観的な態度で点検する訓練が必要。
②幅広い読書
- 評論を読む習慣をつけ、評論特有のさまざまな表現法、論旨展開の形式、抽象的な用語などに慣れる。
- 出題傾向に即して、現代の社会や文化をテーマとする評論を中心に、読書の対象を選んでみる。
- 読書ノートを作って、読み取った内容・読後の感想・批評などを記録していく。
古文
① まず基礎を固めてから応用を鍛える。
- 基本(単語・文法・語法・時代背景・文学史など)をしっかり固める。
- 教科書・参考書・問題集の古文を自力で読み解き、人物関係や場面をとらえることを繰り返し練習する。
- 答案の添削指導を受ける。
- 傍線部だけではなく、本文全体の把握を意識した読解が的確な記述答案の土台になることを意識すること。
② 和歌の学習
- 掛詞・縁語・比喩などの修辞法を理解し、それを押さえて解釈する力をつける。
- 文学部以外の学部の設問にも和歌に関する出題があることもある。
- 『風呂で覚える百人一首』(教学社)などの百人一首の解説書は文法や背景知識の良い勉強になる。
③ 文学史…頻出、記述式でも出題される。
- 重要な作者・作品、文学思潮の歴史的な展開について確実な知識を身につけておく。
- 書名・人名は正確な漢字表記とともに記憶することが大切。
漢文
①基礎と応用
- 基礎固め:訓読法、基本文型、返読・再読文字、重要な句法を確実にマスターする。
- 読みの練習には積極的に音読を取り入れ、漢文の文体・口調に慣れる。
- 問題演習:初めから解説に頼らず、試行錯誤しながら自力で読んでいく。
- 書き下し文を作成する際には、句形や語法に加えて、解釈も併せて考える。
- 傍線部の箇所だけを読んで安易に解こうとせず、全体の内容を把握してから各問に取り組む姿勢も必要。
②漢文由来の語句・表現の関心
- 漢文の読解には語学的な面とともに、作品が育まれた歴史や生活文化の知識を持っておくことが大きな力となる。
- 国語便覧や漢和辞典の付録などに、簡潔にまとめられた中国史や思想・文化の解説があるので、活用して整理しておくとよい。
- 日常生活でも漢文由来の表現や故事成語に触れる機会は多い。
- そのような機会を積極的に活用し、関連の知識を増やしておく。










