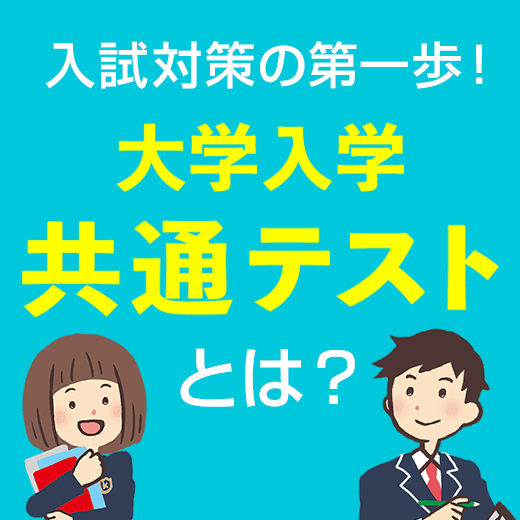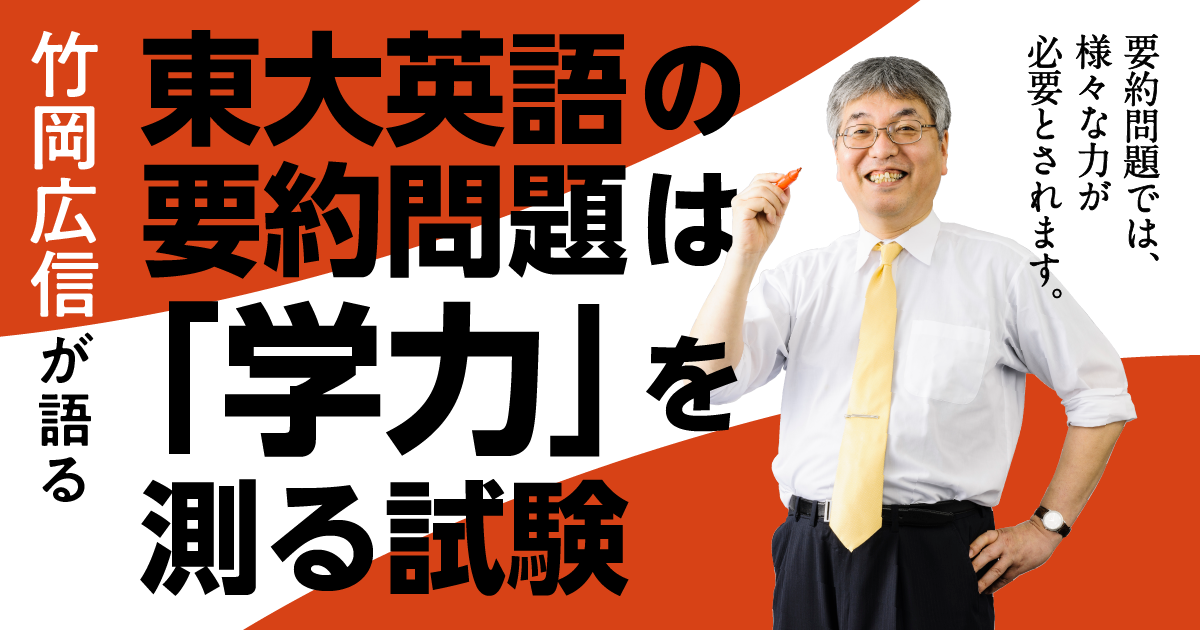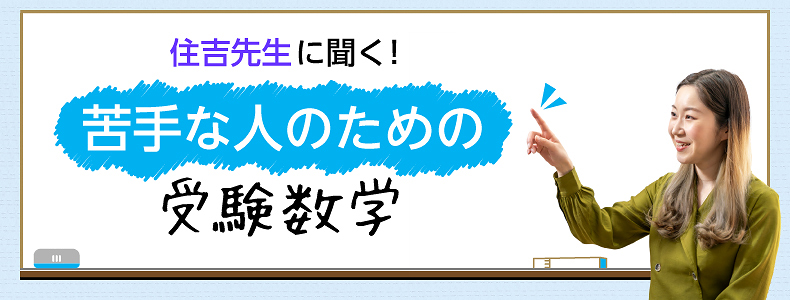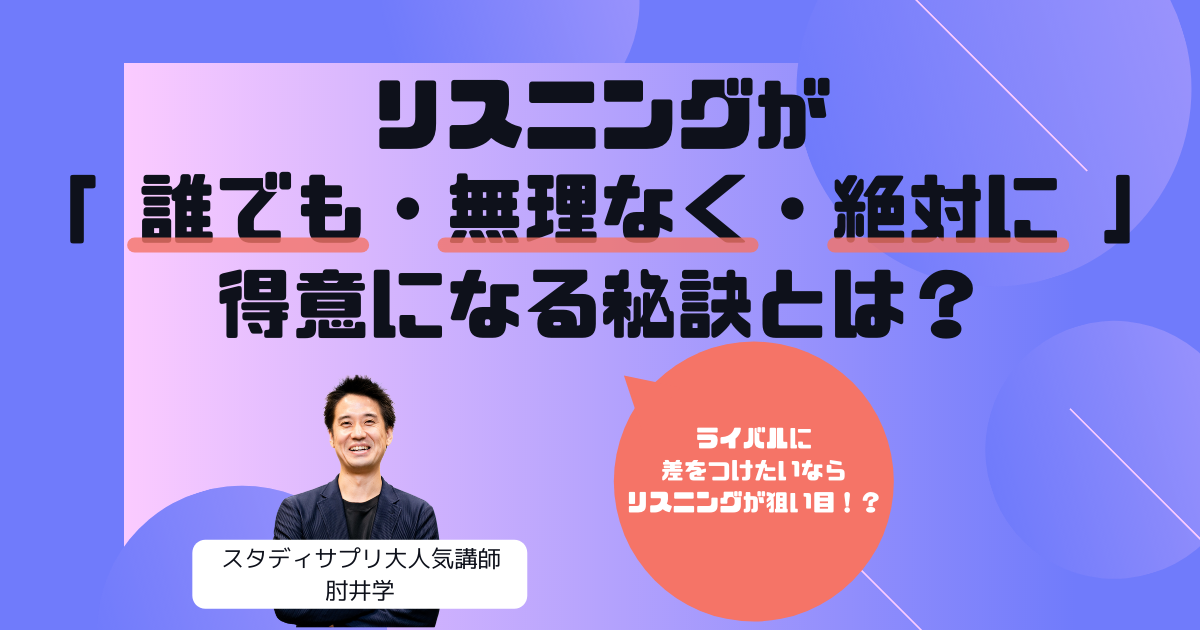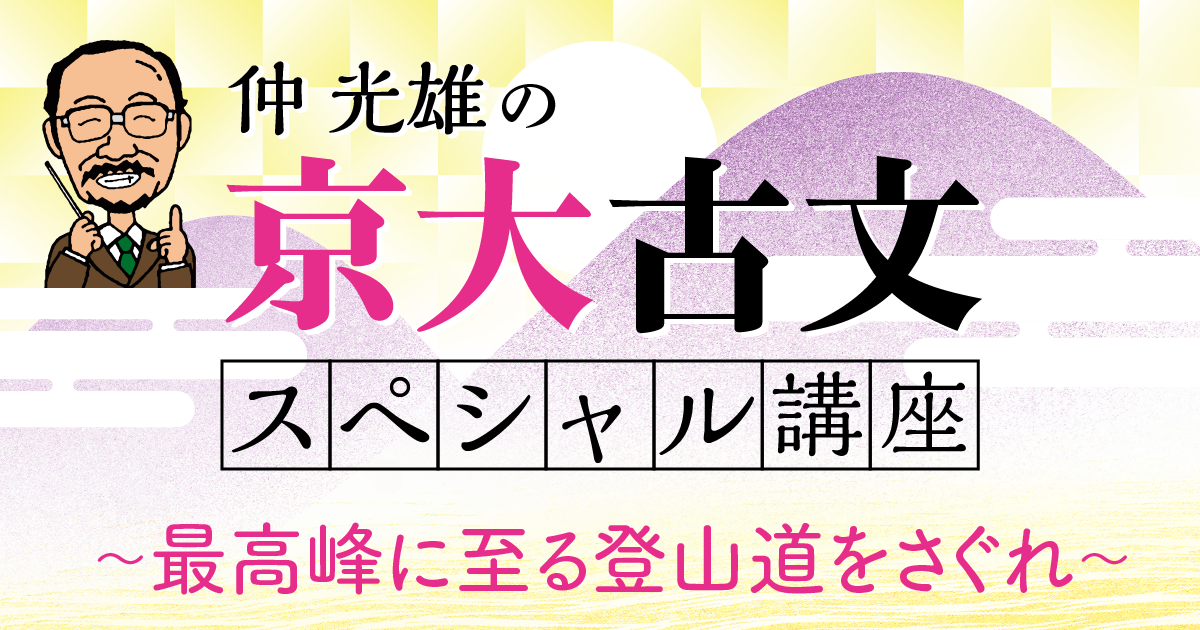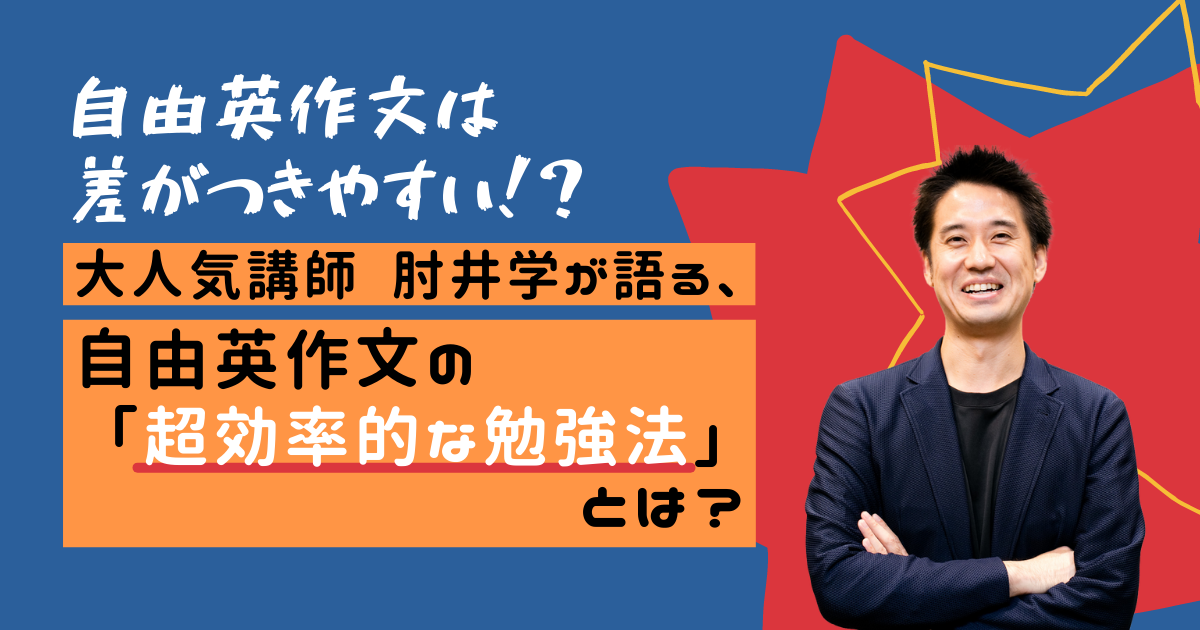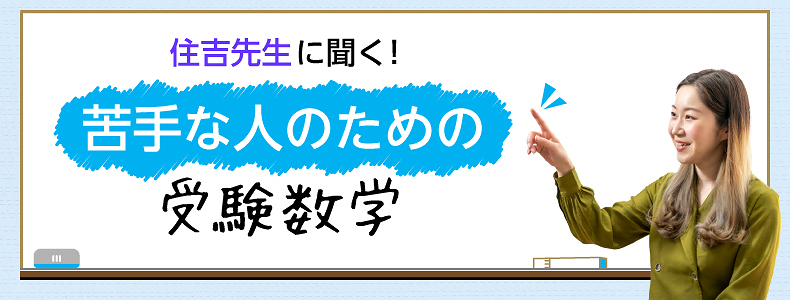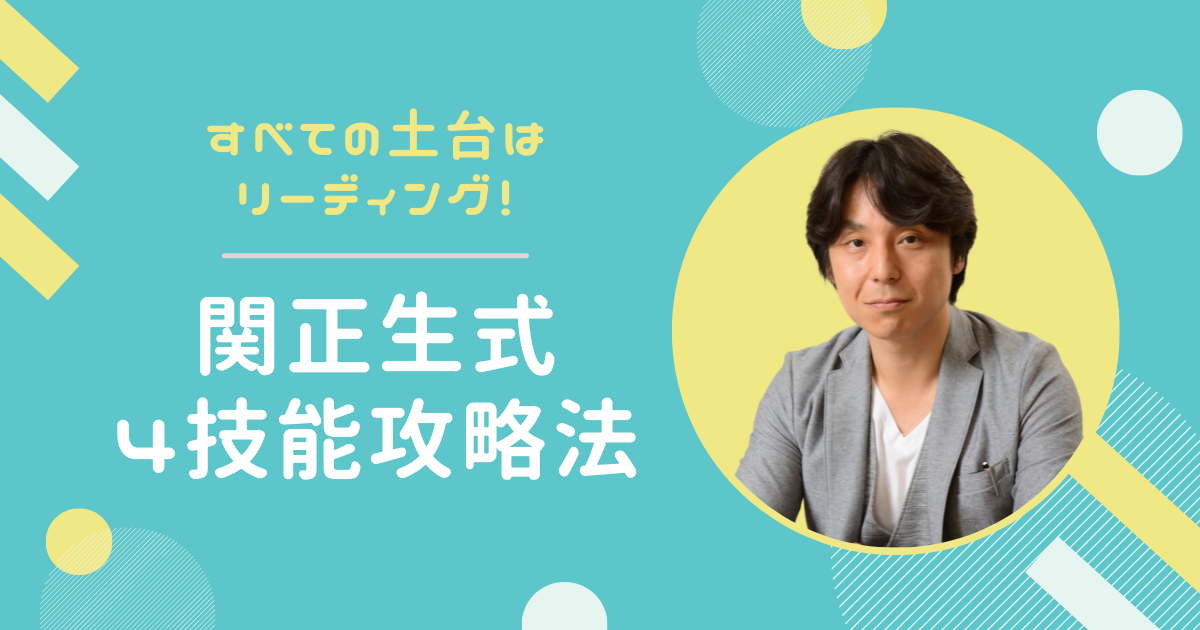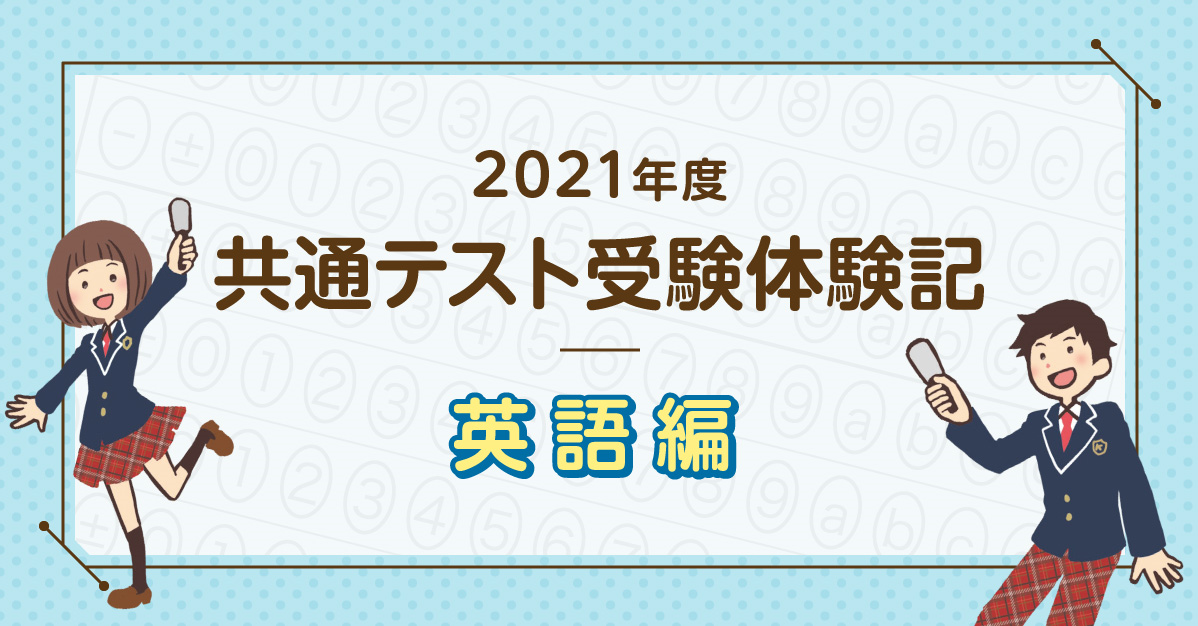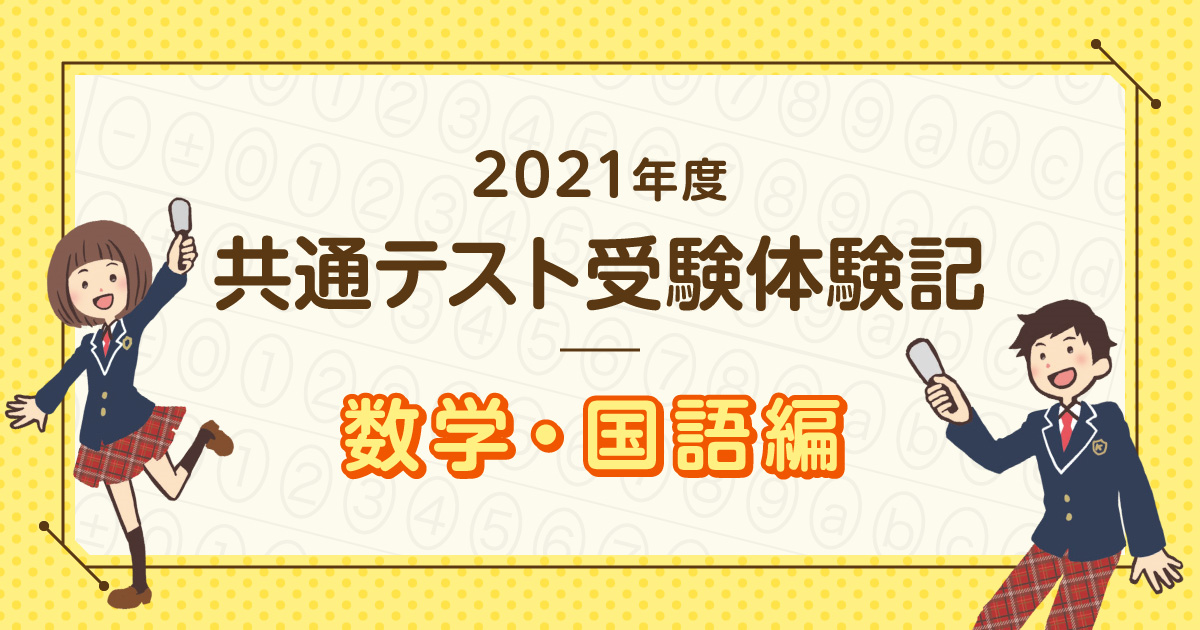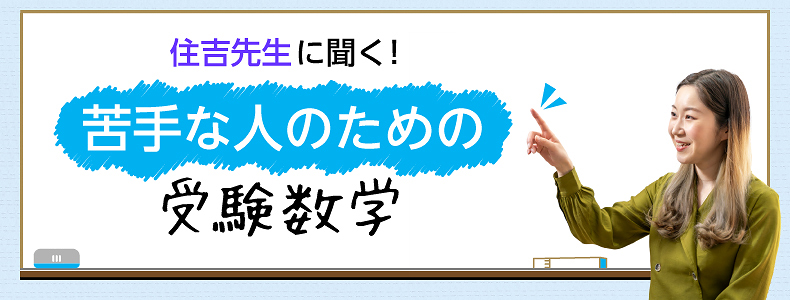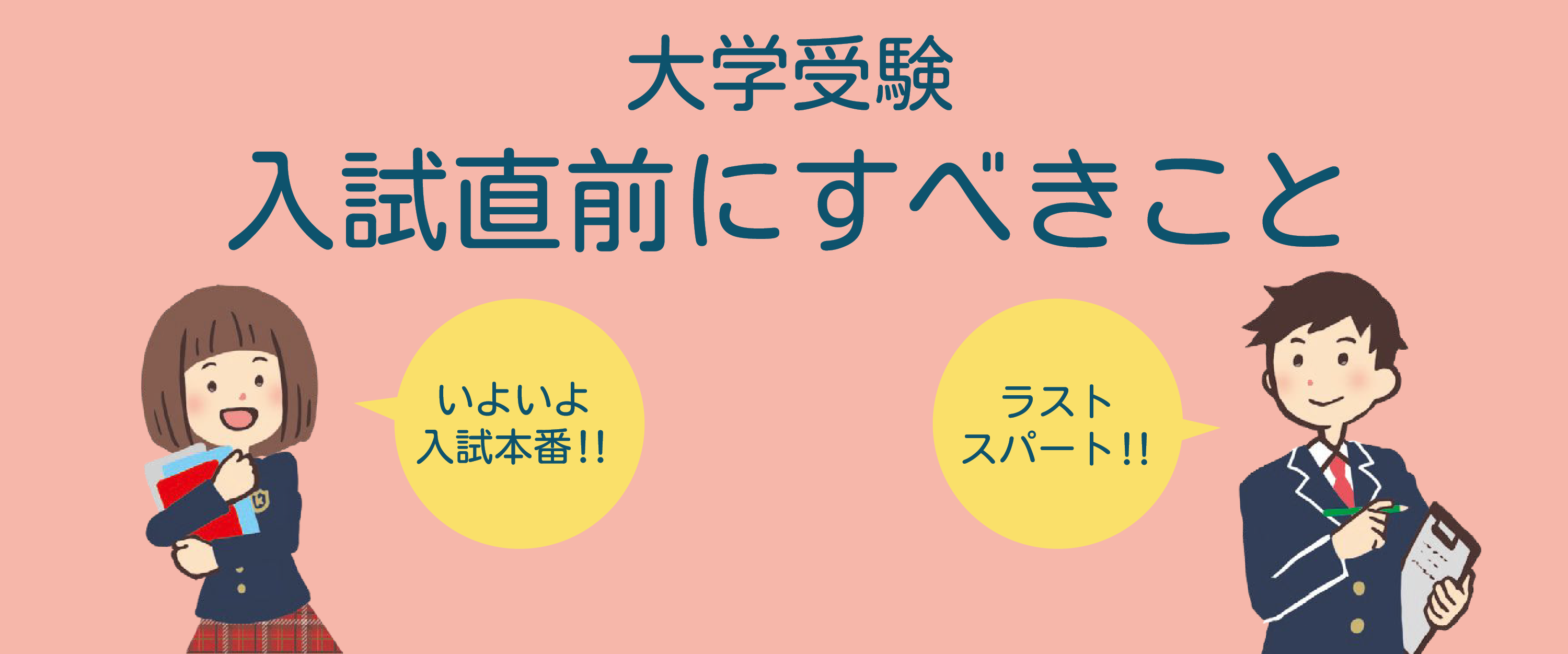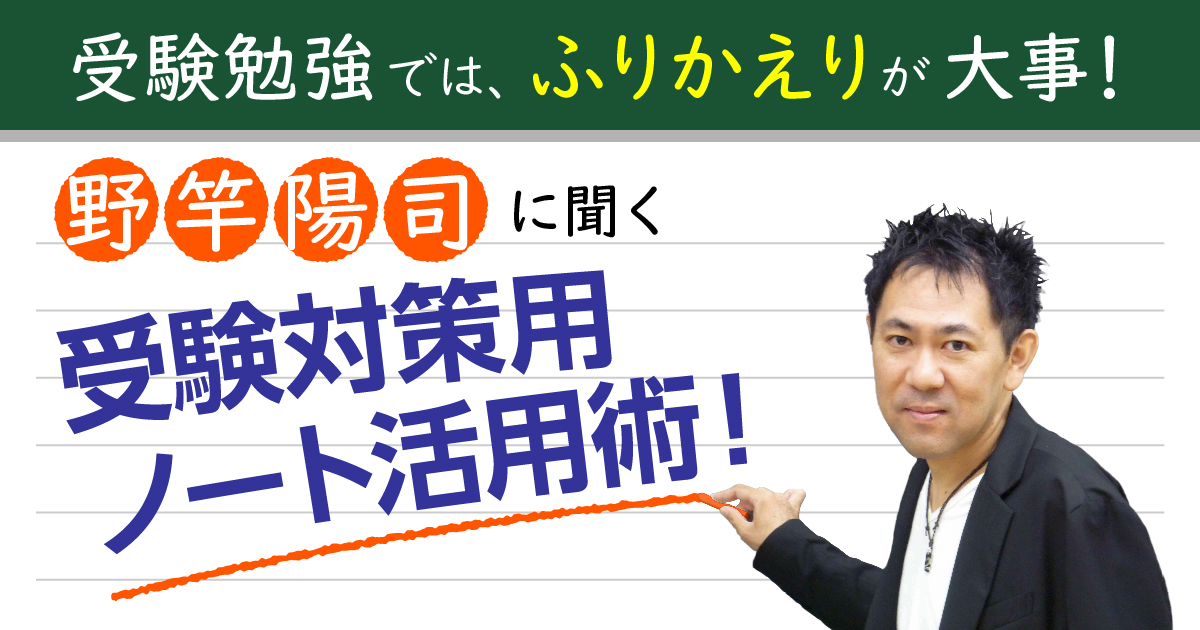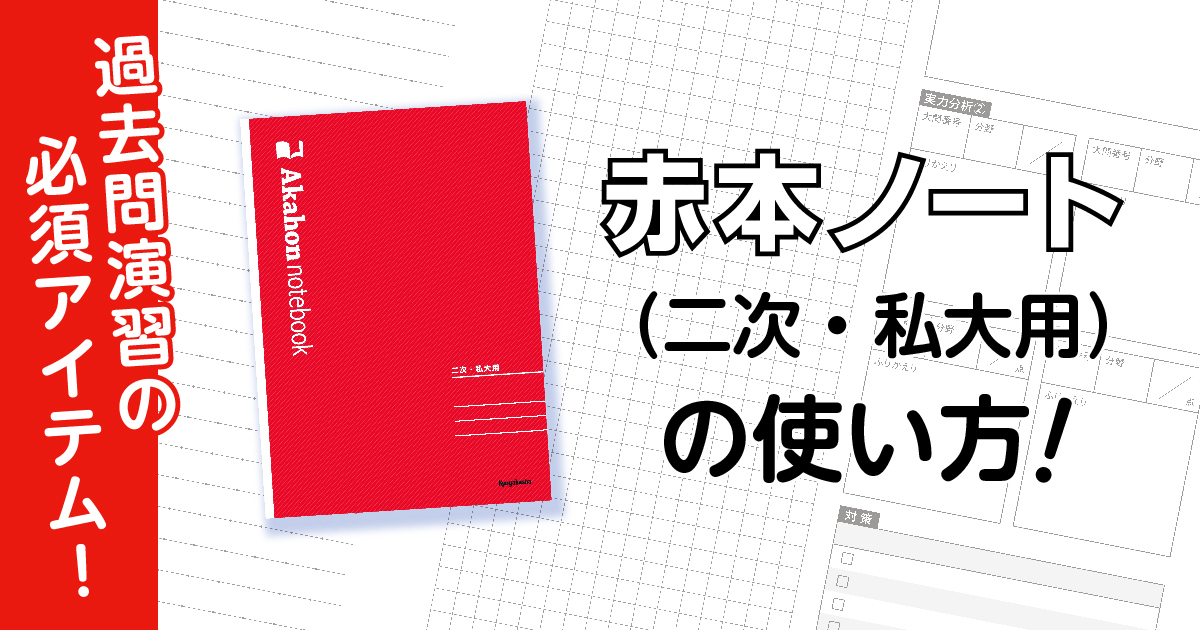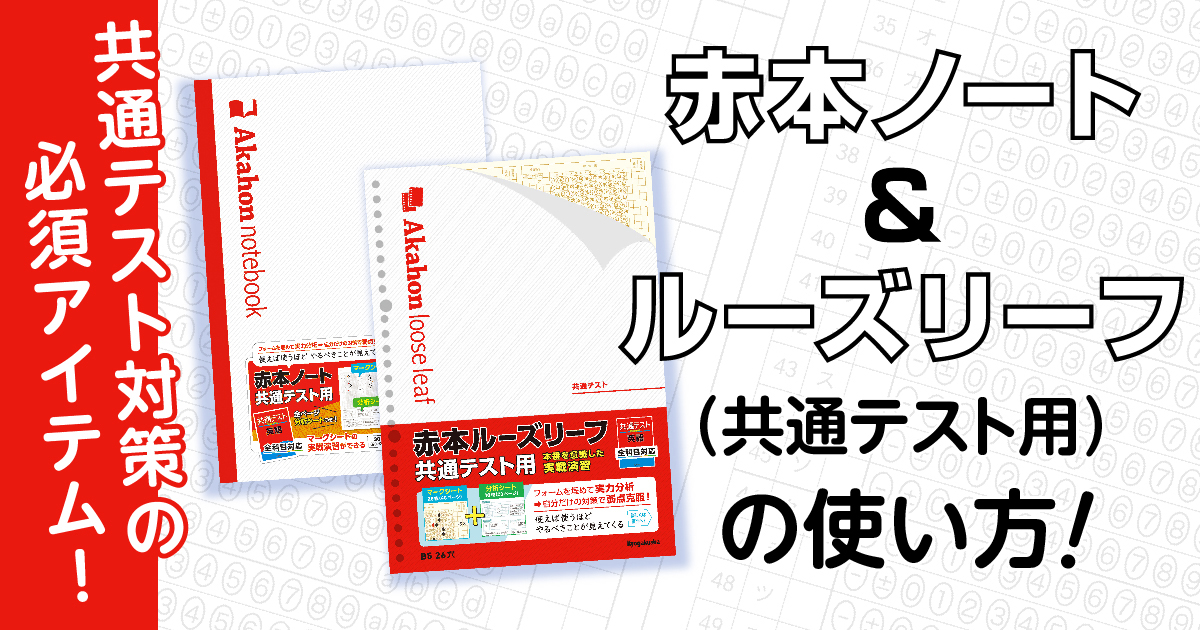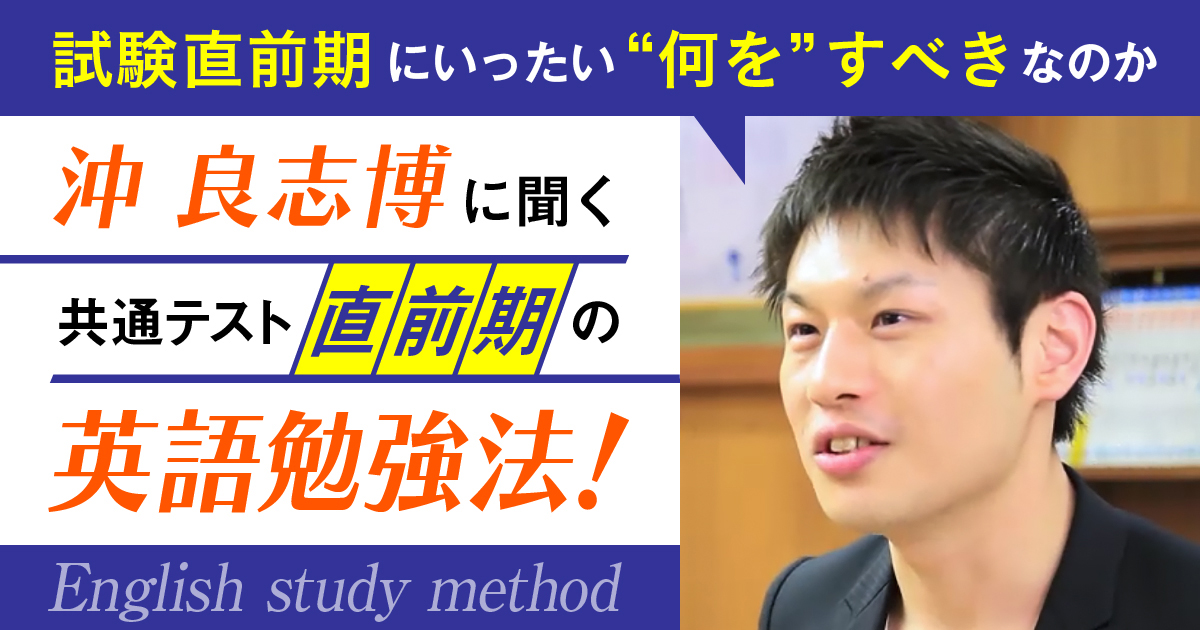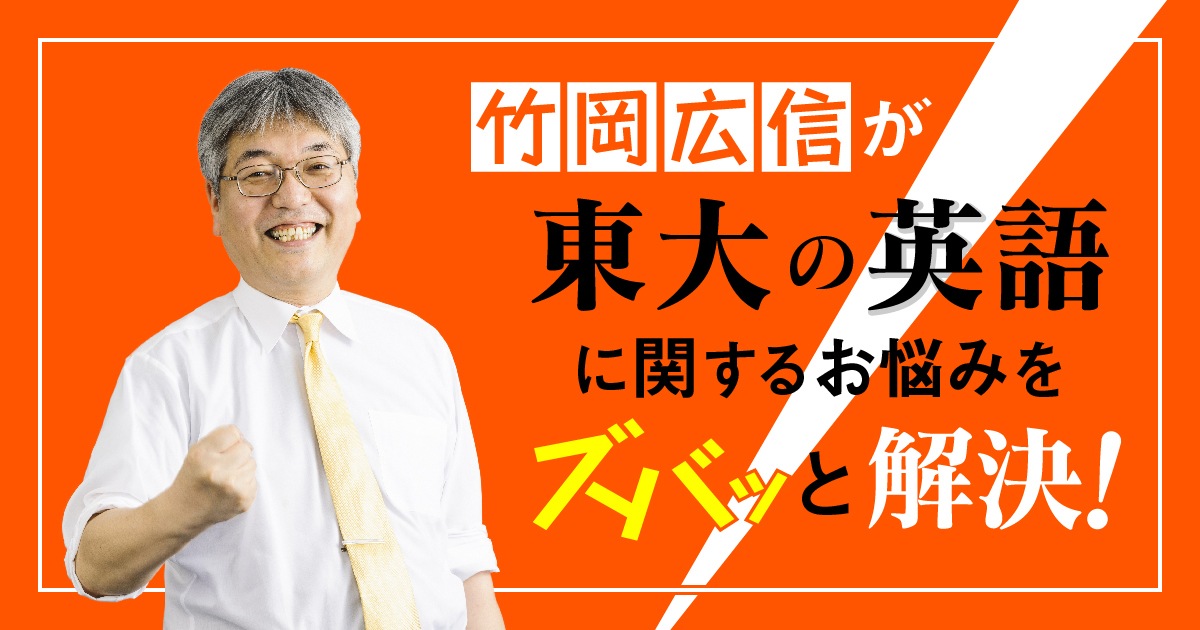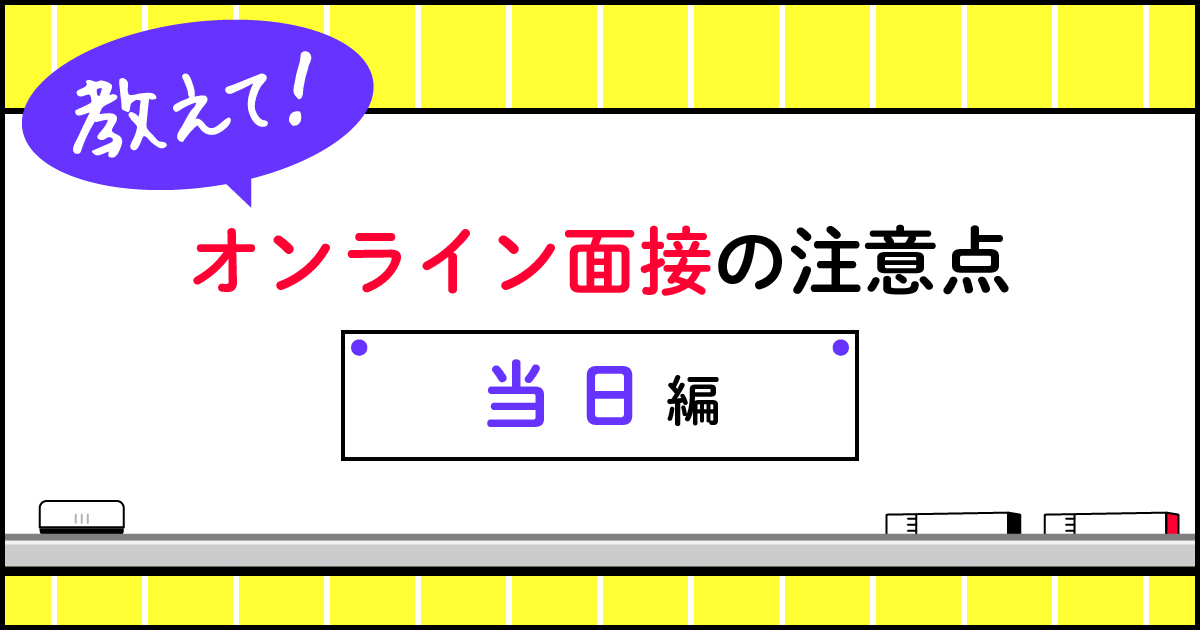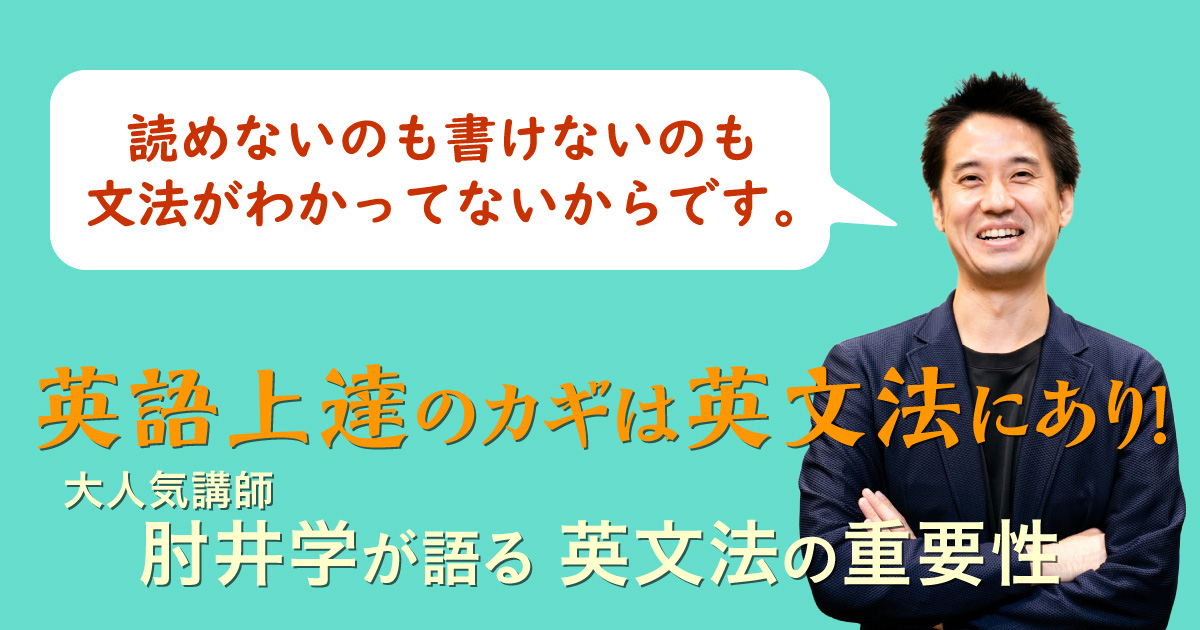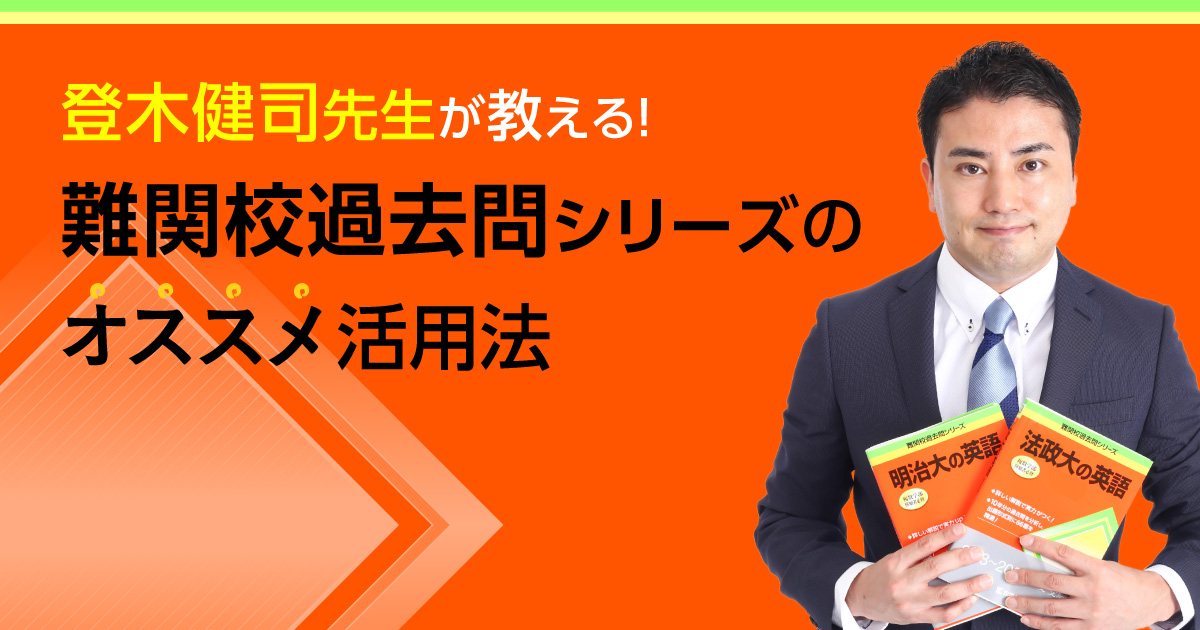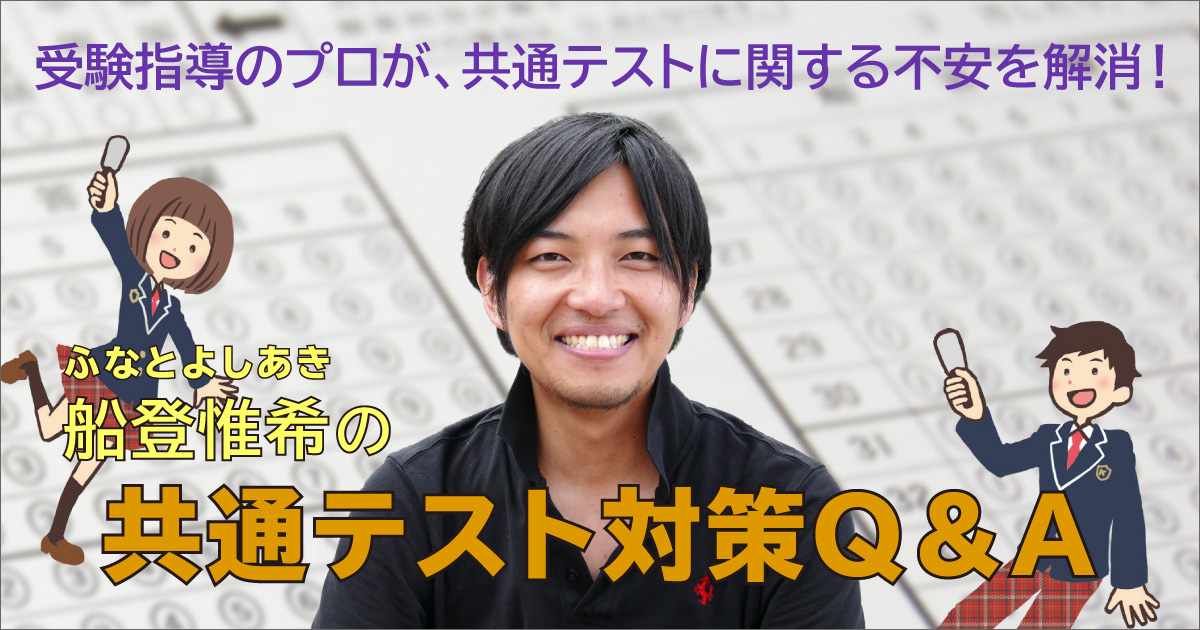
教材作家の船登惟希先生に、共通テスト対策に関する受験生のお悩みに答えていただきました。受験指導のプロならではの、具体的なアドバイスが満載です。
みんなと同じように、王道の対策をすれば大丈夫!
 はじめて実施される共通テスト、過去問がないので不安です…。
はじめて実施される共通テスト、過去問がないので不安です…。
船登 心配しなくても大丈夫です。なぜなら、センター試験から多少形式が変わるにせよ、受験は相対評価だからです。この点に関してはみんな平等ですので、他の人がやっていることを自分もやればOKです。具体的には、基本的な知識をつけた上で、学校で実施される共通テスト模試を受験する、センター試験の過去問を解く、各出版社が作る予想問題を解く、の3つです。「出し抜こう」と考えるのではなく、「みんながやっていることを自分もやればいい」と考えてください。
 何から手をつけたらいいですか?
何から手をつけたらいいですか?
船登 まずは、教科書準拠問題集で基本的な知識をつけることです。共通テストはセンター試験同様、教科書に載っている知識からしか出題されません。よって、教科書準拠問題集で知識を固めるという本質的な勉強方法に変わりはないのです。
 基本的な知識がついたら、つぎに何をすればいいのか教えてください!
基本的な知識がついたら、つぎに何をすればいいのか教えてください!
船登 個別試験で必要な科目は、11月までは個別試験対策をメインで行ってください。11月になったら、センター試験の過去問と共通テストの予想問題を1週間に1回のペースで解いていきましょう。出題形式に慣れ、実戦感覚をつかむことが目標です。
共通テストのみの科目は、教科書準拠問題集や参考書を1冊仕上げた後、センター試験の過去問を5年分を目安として解き、目標とする点数が取れるか確認しましょう。必要な点数に届かない場合は、教科書や参考書に戻って知識の穴を埋めるようにしてください。その後、予想問題を解きます。
センター過去問の活用がカギ!
 センター試験の過去問を解くことに、意味はあるんでしょうか…?
センター試験の過去問を解くことに、意味はあるんでしょうか…?
船登 あります。センター試験の過去問を解かずに、共通テストの予想問題をたくさん解こうと考えるのは危険です。なぜなら、大学入試センターが試行調査を2回行いましたが、必ず試行調査の形式で出題されると言っているわけではないからです。つまり、試行調査をもとに予備校や各出版社が作った予想問題は、予想の域を超えないのです。
大学入試センターが出した問題作成の方針では、「センター試験における良問の蓄積を受け継ぐ」とされています。共通テストというまったく新しい試験が行われるわけではなく、センター試験のよいところを踏襲した試験になるので、センター試験の過去問と共通テストの予想問題は同じ回数くらいは解くとよいでしょう。
 そうは言っても、センター試験とまったく同じではないですよね?
そうは言っても、センター試験とまったく同じではないですよね?
船登 そうですね。共通テストでは、センター試験を解くために必要な知識にプラスして思考力が要求されると考えてください。まずはセンター試験の過去問を解き、どれくらいの点数が取れる知識の下地があるのかを確認するとよいでしょう。センター試験が解けるだけの知識の下地がなければ、試行調査や共通テストの予想問題のような「ひねった問題」が出されても思ったような点数は取れないです。
ちなみに、すでに出題されないことがわかっている英語の発音・アクセント問題も、リスニング力アップに役立ちます。時間に余裕があれば、解いても損はないですよ。
 センター過去問や共通テストの予想問題は、何回分やったらいいですか?
センター過去問や共通テストの予想問題は、何回分やったらいいですか?
船登 センター試験は過去5年分、共通テストの予想問題は5回分やれば、人より少ないという状態にはならないでしょう。ここに、共通テスト模試を3~5回受けることを加える形になると思います。科目によって適宜回数を増やし、目標点に近づけるようにしましょう。
 本番に向けて、気をつけておいたほうがいいことはありますか?
本番に向けて、気をつけておいたほうがいいことはありますか?
船登 時間配分です。どんな出題になるかわからないので、あらかじめ時間配分を決めておくことができません。少なくとも、1つの問題で止まって大きく失点するという最悪の事態だけは、避けなければなりません。ただ、どんな出題になるかわからないと言っても、準備しておくにこしたことはありませんので、共通テストの予想問題やセンター過去問で時間配分の練習をしたり、解ける問題だけを先に確実に解く練習をしたりするようにしましょう。
|
船登惟希(ふなと・よしあき)

- 1987年、新潟県佐渡島生まれ。教材作家。新潟高校理数科から現役で東京大学理科二類に合格。東京大学理学部化学科卒業、東京大学大学院理学系研究科化学専攻中退。IT企業大手のDeNAを経て教材作家として独立。
- 学習参考書の執筆活動は大学時代にさかのぼり、現在までに20冊以上の教材や一般書を出版している。「本質を突き詰めれば、勉強は自然とおもしろくなる」をモットーに、エデュケーション(教育)とエンターテイメントを融合した「エデュテイメント」を志向。
- 「宇宙一わかりやすい高校化学」シリーズ、『宇宙一わかりやすい高校生物基礎』(学研プラス)、『高校一冊目の参考書』、『中学一冊目の参考書』(KADOKAWA)などの著書がある。
関連ページ