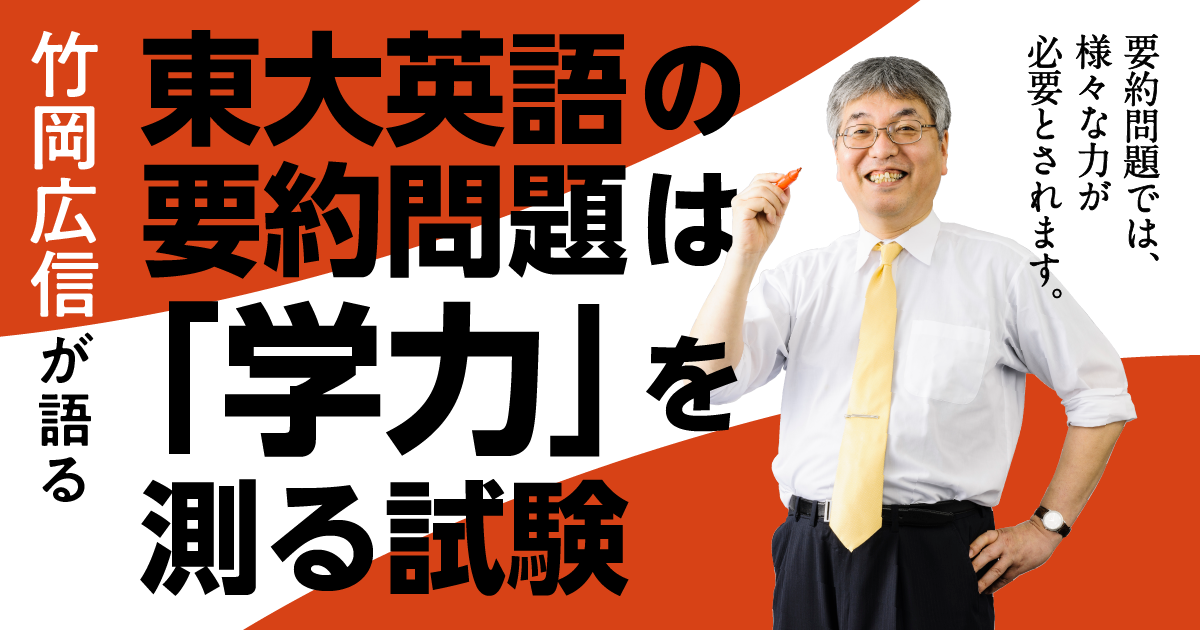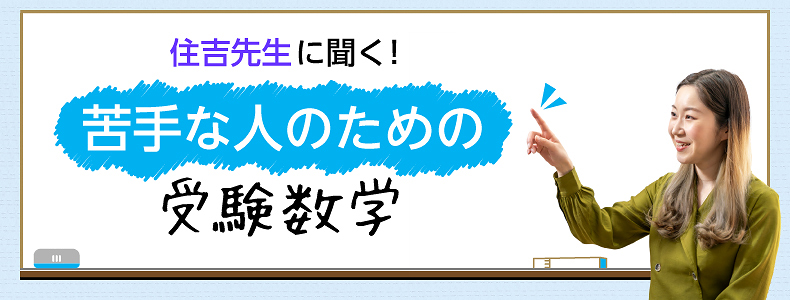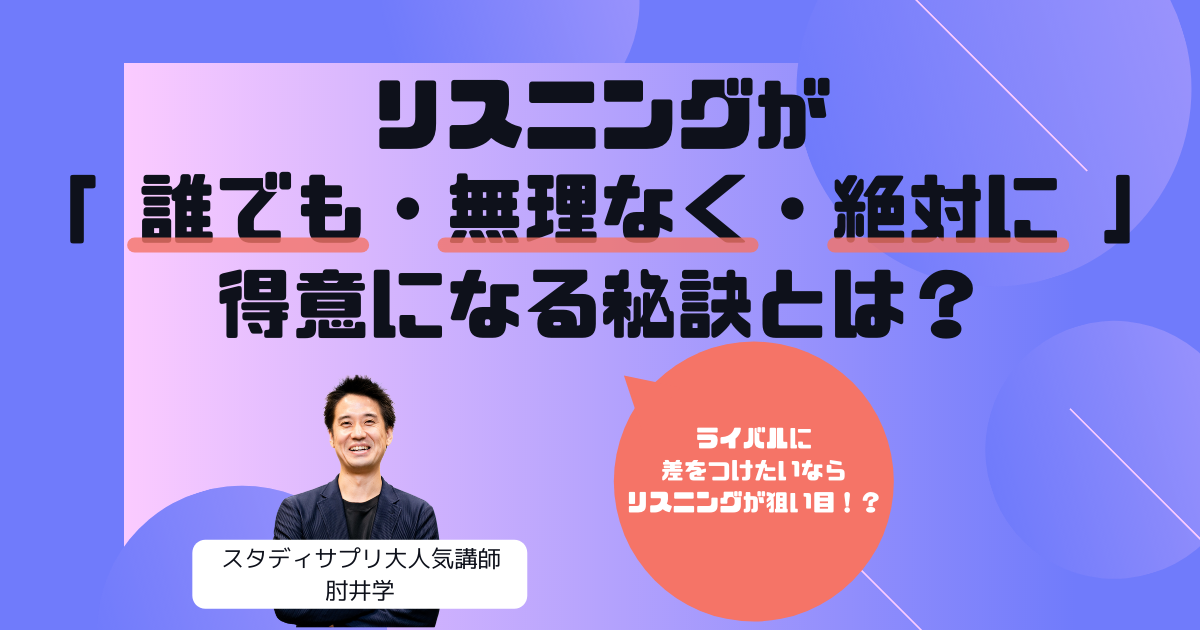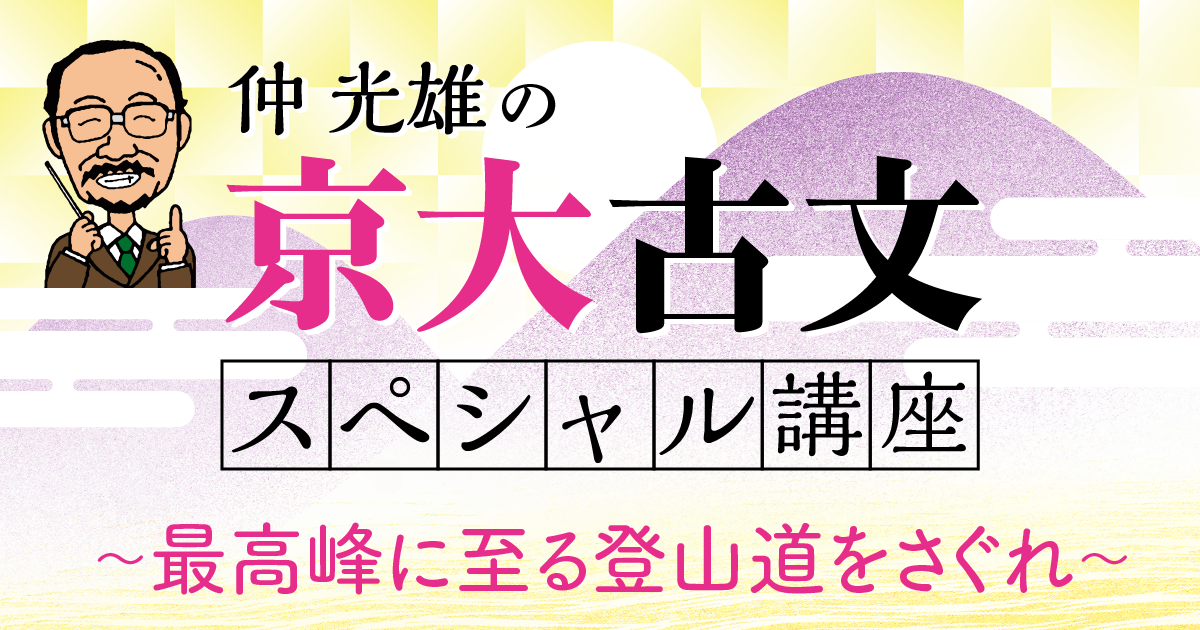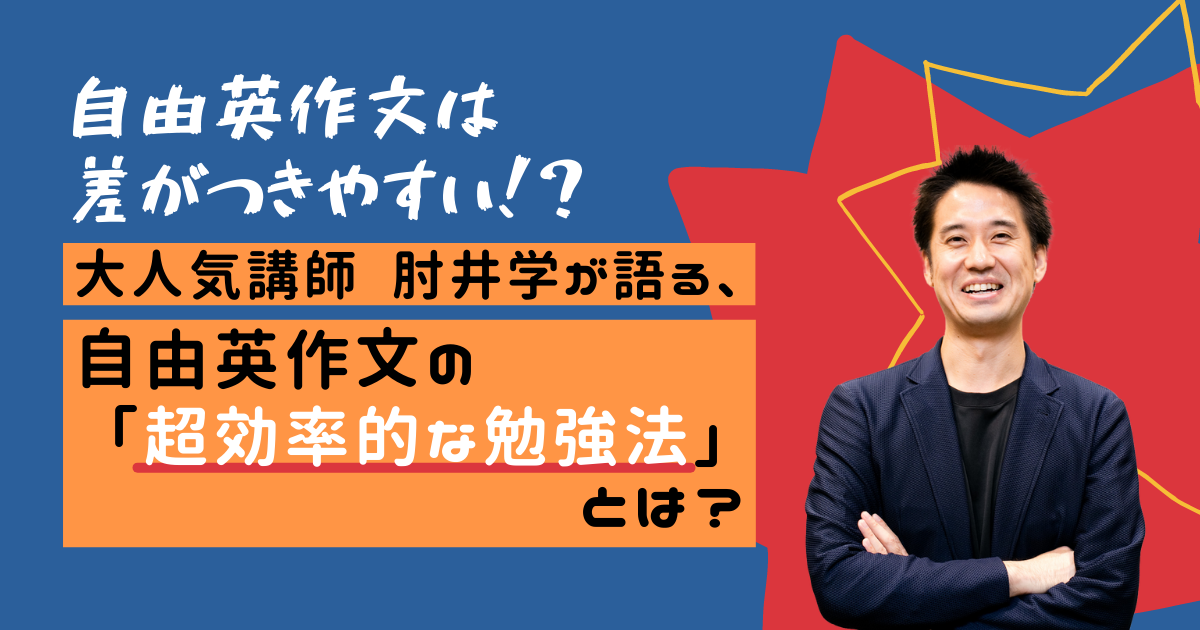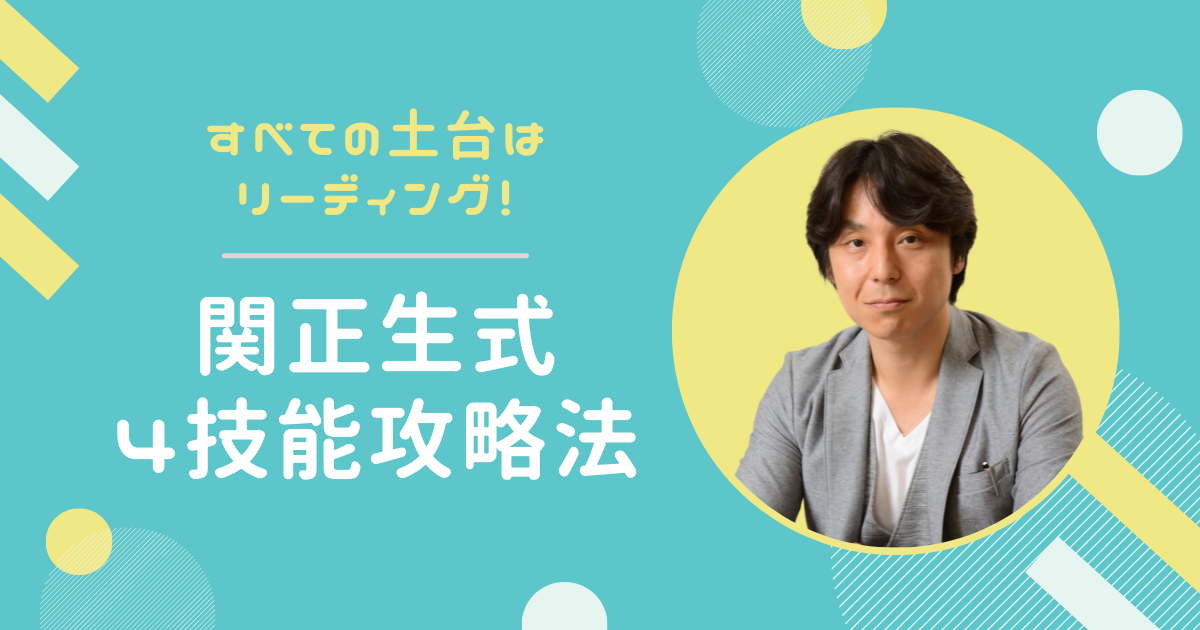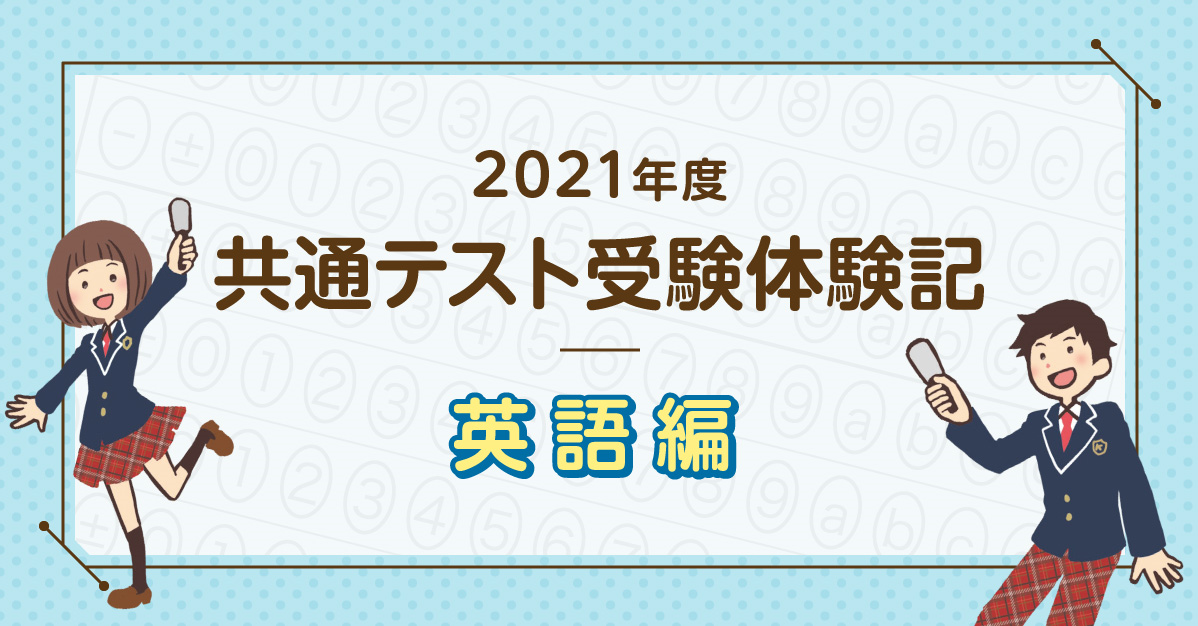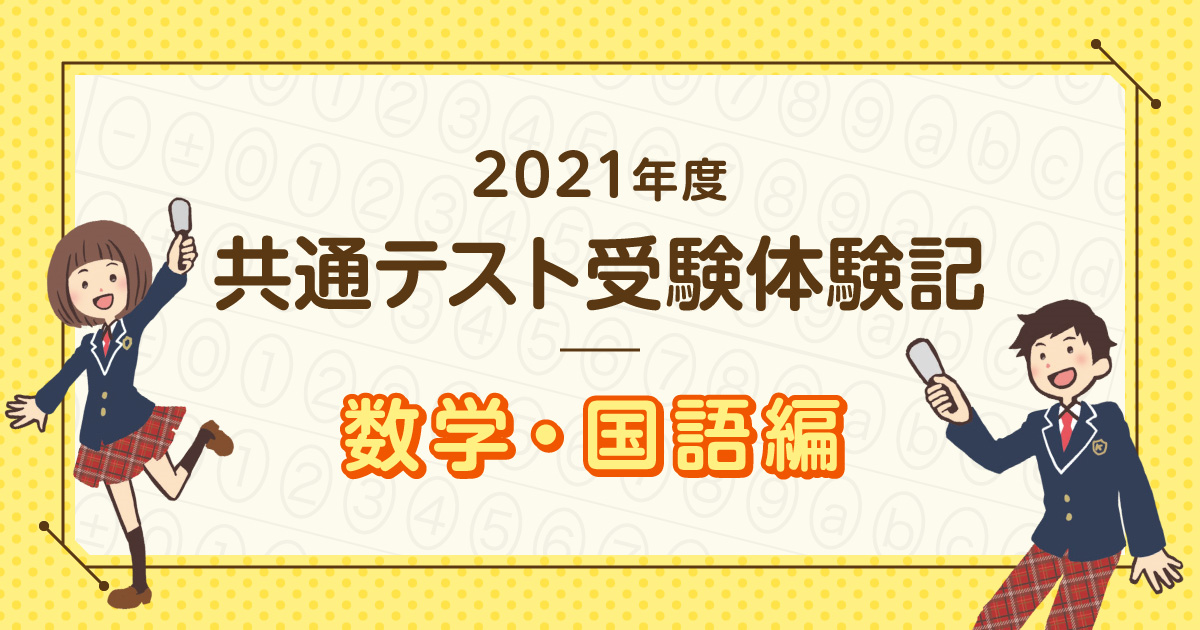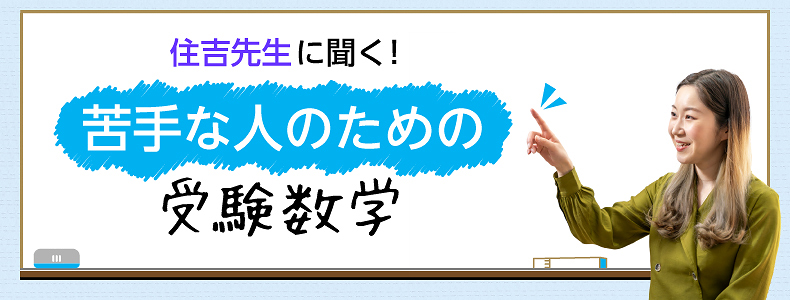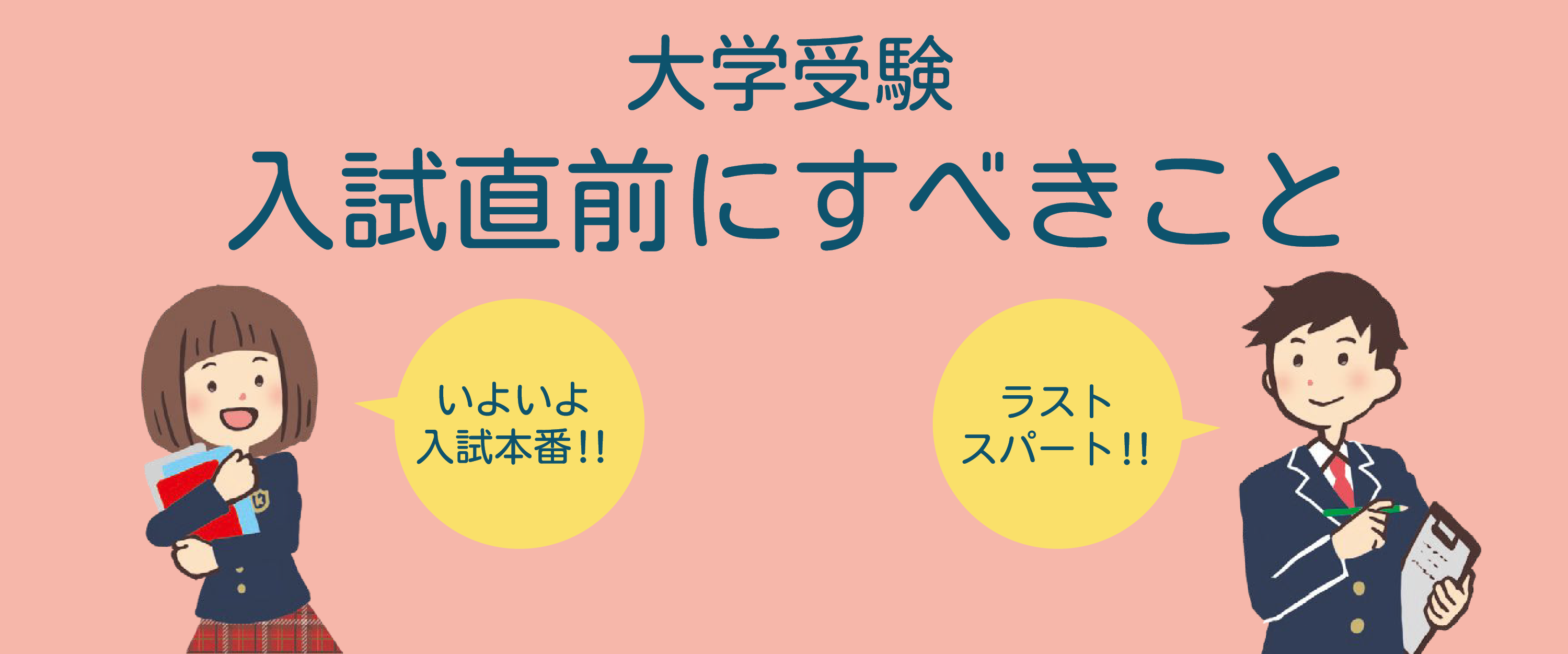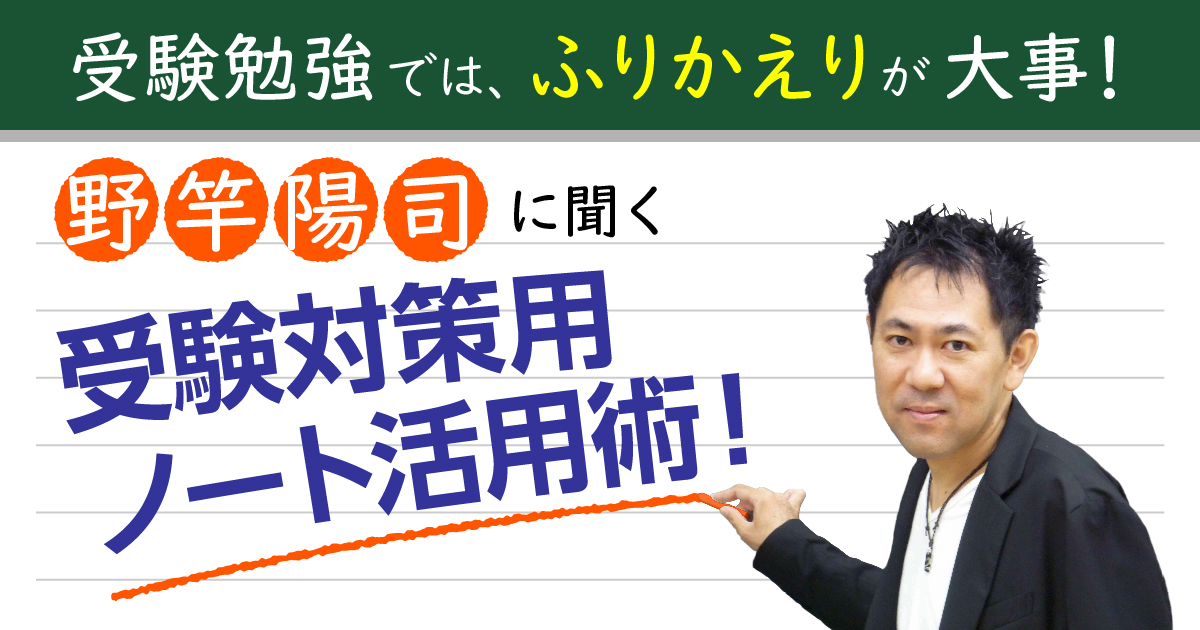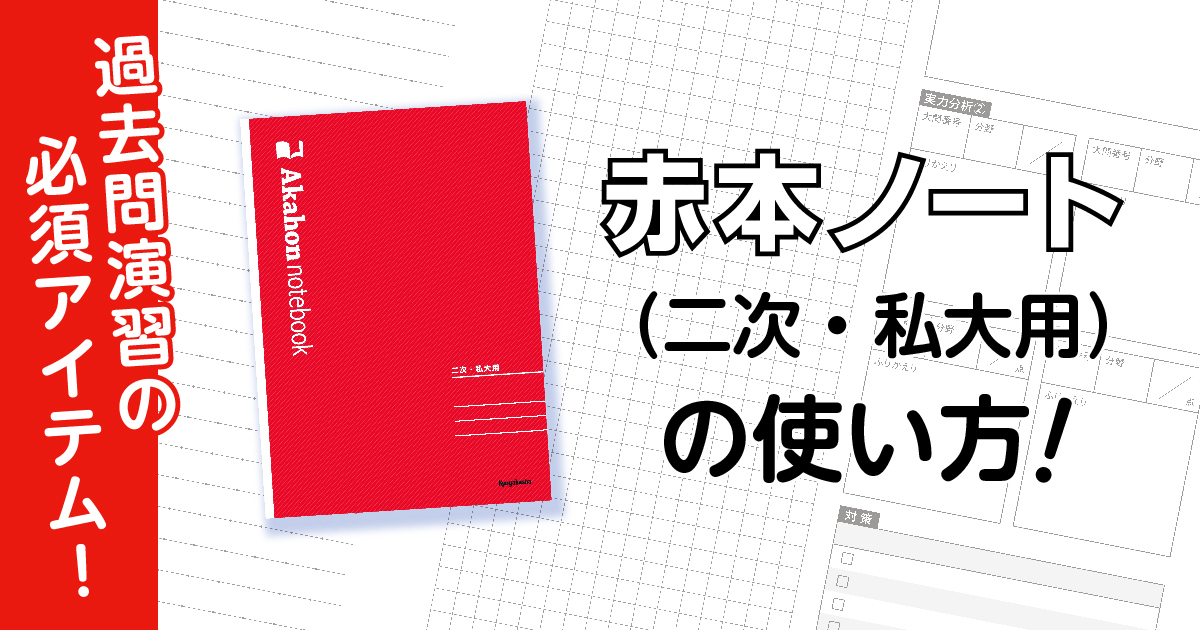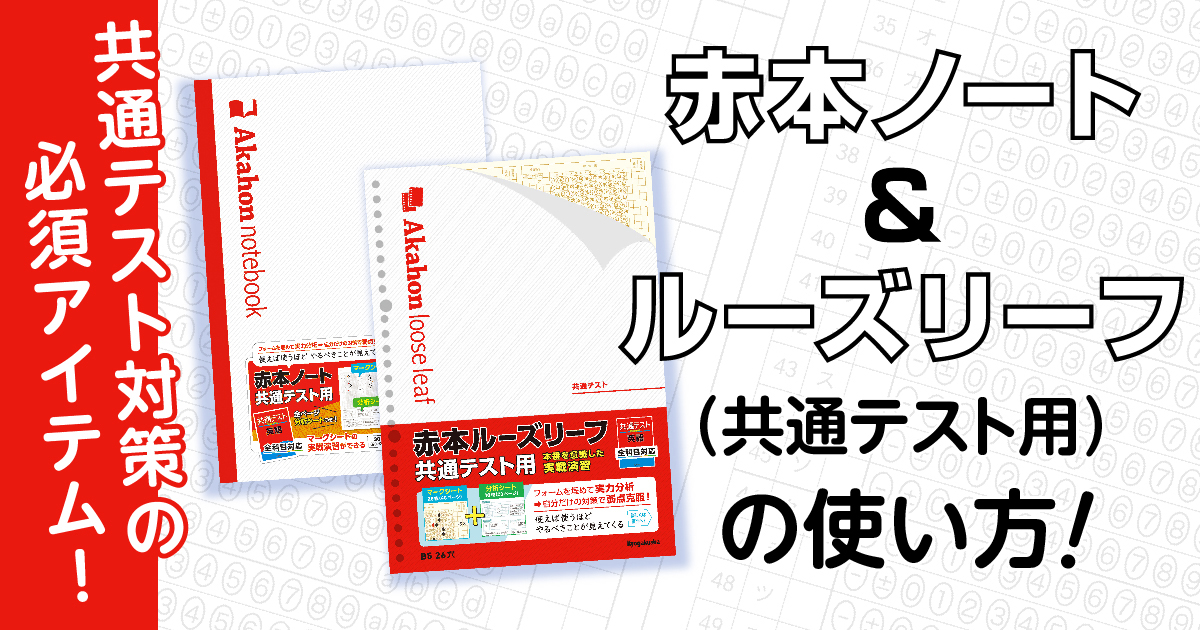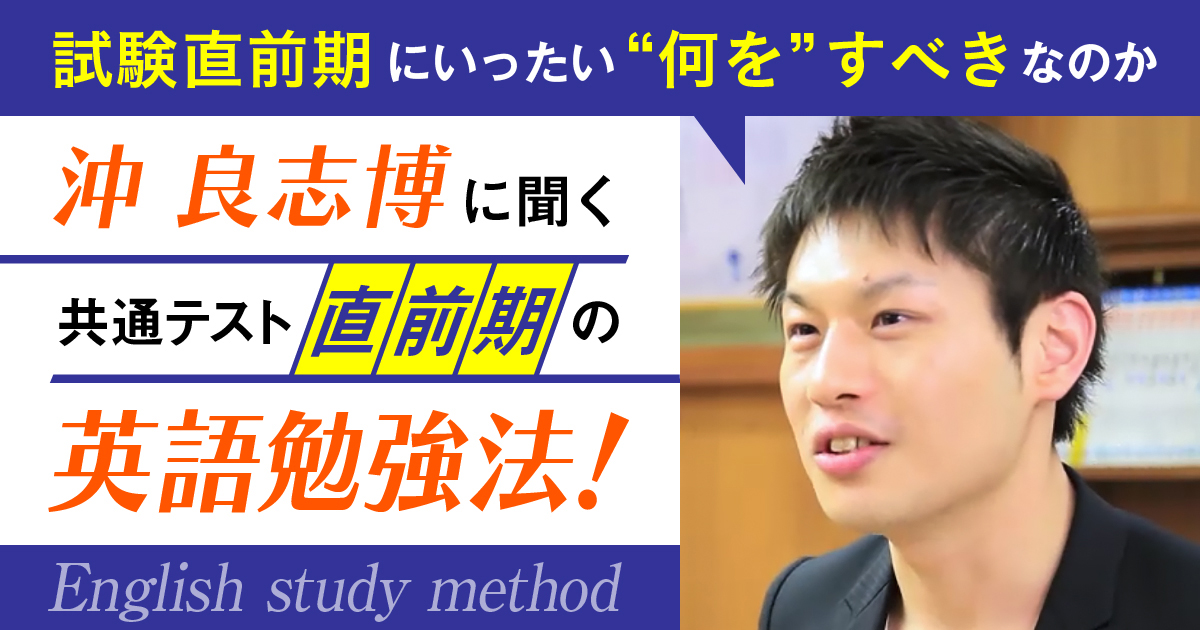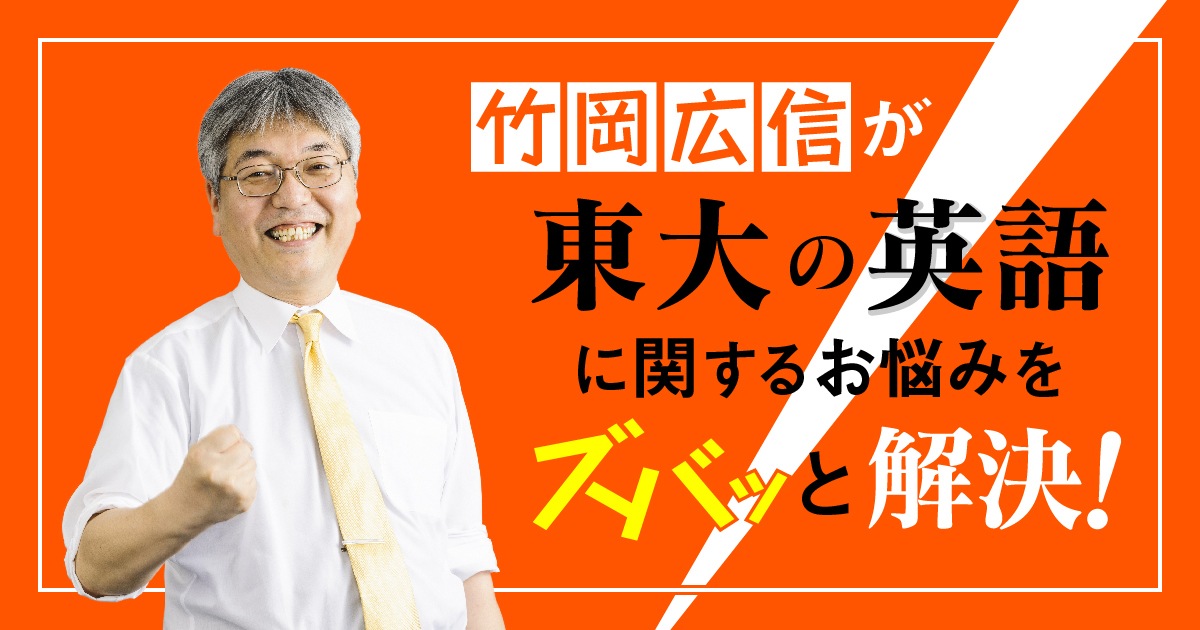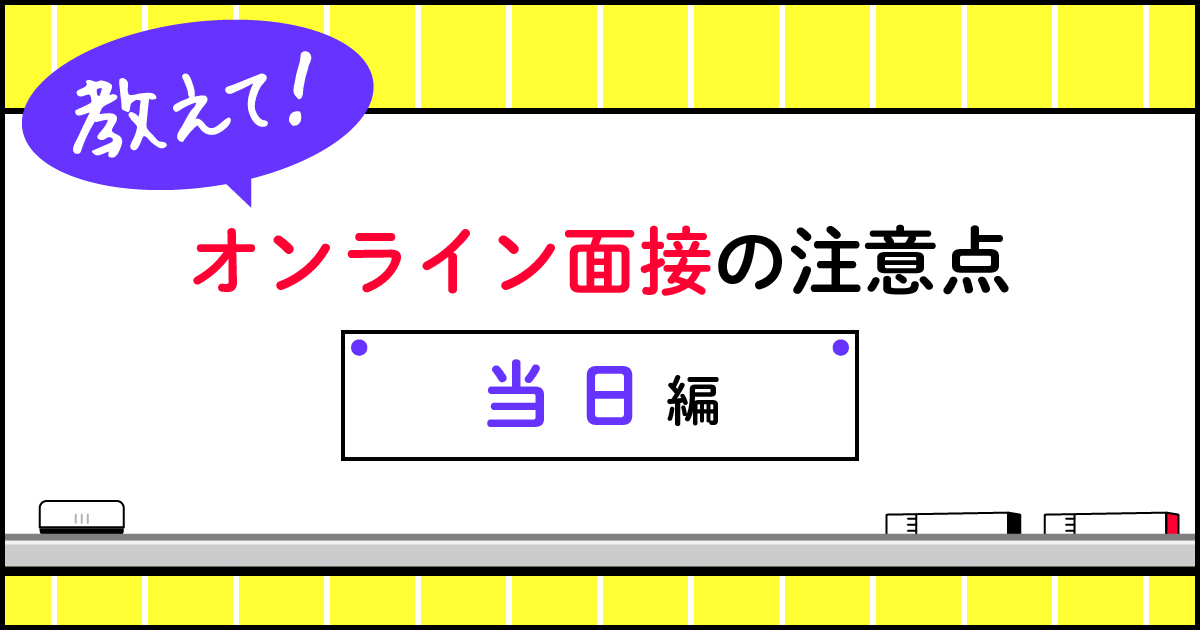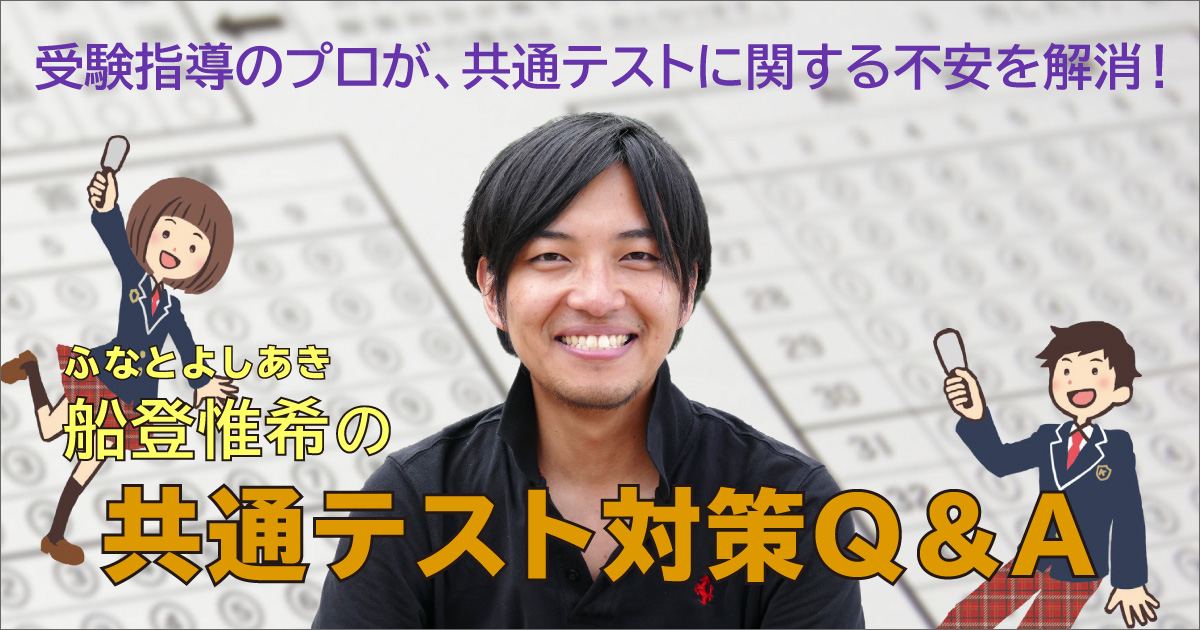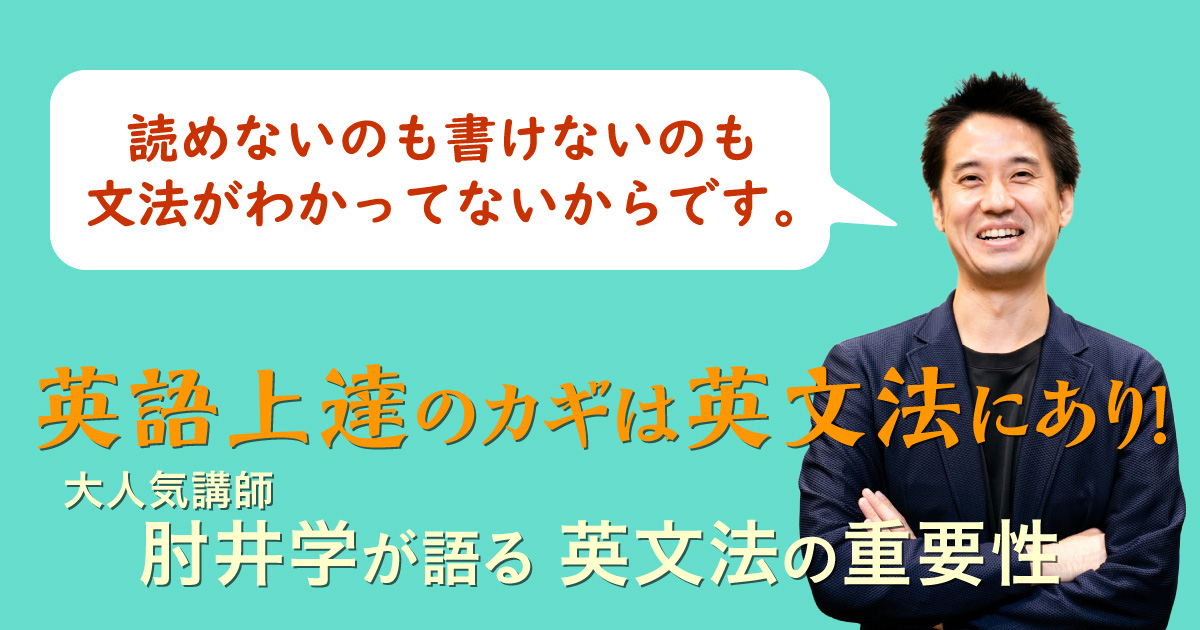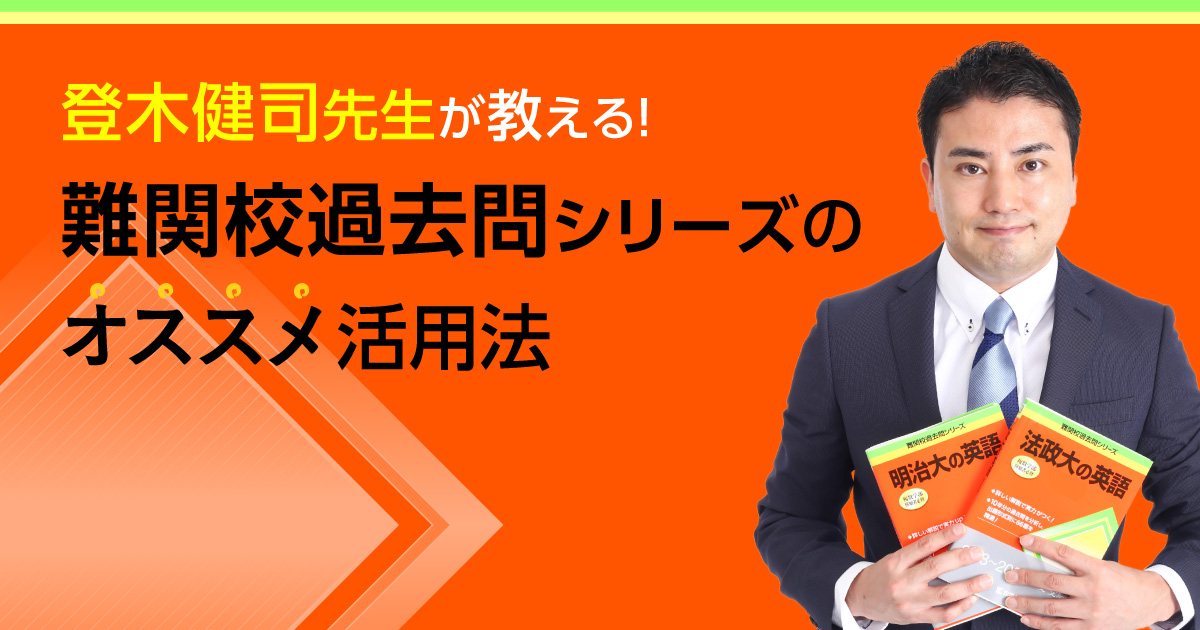.jpg)
悩める受験生に贈る連載企画、『苦手な人のための受験数学』。前回は「受験数学の始め方」ということで、新学期が始まる4月に何をすればよいかを紹介しました。
今回のテーマはいよいよ迫ってきた「受験の天王山」、夏休みです。どのように学習計画を立て、どう進めるかがとても大切です。そこで住吉千波先生には、夏休み中の学習について受験生からよく聞かれる質問に答えていただきました。
長いようで短い夏休み、うまく使って合格に近づきましょう!
|
目次
Q1 夏休み中に使うおすすめの問題集はありますか?また問題集を最後までやり切るコツは何ですか?
Q2 夏休み中に基礎固めをしたいのですが、問題集は何周ぐらい演習するのが効果的ですか?
Q3 数学の苦手な人が夏休み中の勉強で注意すべき点は何ですか?
|
|
Q1 |
夏休み中に使うおすすめの問題集はありますか?また問題集を最後までやり切るコツは何ですか? |
夏休み中の勉強において、自分に適した問題集や参考書を選ぶことはとても大切です。
自習時間のたっぷりとれる夏休みは、引き続き基礎を押さえる「インプット」を続けつつ、入試レベルに準ずる問題で演習を積む「アウトプット」も少しずつ始めて、並行して進めるのが理想です。
インプットは、これまで学校で使ってきた問題集や、予備校で基礎を学んだテキストなどで何度も繰り返し行います。
アウトプットは、初見の問題に対処する力を養うために、入試レベルの問題集や実際の過去問を使って演習を重ねてください。
基礎をある程度固めてから演習に移ってほしいところですが、100%完璧にするのは、少なくとも、入試本番まであと数ヵ月という限られた時間内ではほぼ不可能です。ですから、基礎がある程度できるようになったら、今度は演習を積みつつ、穴を見つけ次第、インプットに使ったテキストや問題集に戻って確認するようにしましょう。
おすすめの問題集が知りたいということですが、残念ながら、万人におすすめとして紹介できる魔法のような本はありません。これさえやっていれば完璧、という問題集があるならば、書店の学習参考書コーナーにはその本しか並ばないはずです。しかし、実際には何十冊もの参考書や問題集があり、対象もレベル設定も様々です。
ここでは、選ぶときに注意すべき3つのポイントを紹介しましょう。
|
① |
あなたのレベルに合ったものであること |
|
② |
解答解説が充実していること |
|
③ |
あなたが読みやすいと思えること |
友達の口コミなどを参考にしてみるのもいいですが、あなたとその友達は今の学力も志望校も同じですか?
自学自習には、あなた自身が一人で取り組みやすいことがとにかく大事です。選ぶときはなるべく書店で手に取り、実際に中を覗いてみましょう。対象となるレベルは表紙や「はじめに」などに書いてあることが多いです。
気に入った問題集を選んだら、いよいよ学習計画を立てます。その際、問題数が多すぎると感じたら奇数番目だけやる、など勉強の効率を上げる工夫をしましょう。最初の方だけやって頓挫するよりは、少し間引いてでも全体をざっと終わらせた方がよいからです。
買ったときは皆やる気に満ちあふれているものですが、そのままのノリで計画を立ててはいけません。やる気がある日もあれば、ない日もある。体調が悪い日や、どうしても眠い日だってある。計画を立てる上で忘れてはいけない最も重要なことは、自分は機械でなく人間である、ということです。予備日を設けたり、頑張ってみても無理だと感じたら、随時計画を調整していくことが大切です。
| Q2 |
夏休み中に基礎固めをしたいのですが、問題集は何周ぐらい演習するのが効果的ですか? |
時間がある長期休みには、問題演習を何度も繰り返し、苦手を克服していくのが理想です。しかし、問題集に「何周すれば安心」という基準はありません。何の制約もなければ 、2周よりは3周、3周よりは4周…と言い始めてキリがないので、残念ながら明確な答えは存在しないのです。
ですが、「少なくとも」という意味で、特にインプット用の問題集について言えば1冊につき2周はしてください。つまり、ひとつの問題を一度解いただけで終わることは避けましょう。問題集に載っている問題は、答えを出すためのものではなく、概念や解法のエッセンスを学ぶためのものです。完璧に理解した上で解けた問題に限っては一度で終わってもいいですが、それ以外に関してはエッセンスを吸い尽くすまで、何度も取り組みましょう。
逆に、多くの問題集に浮気したところで、得られる効果は薄いです。数学の基盤となるエッセンスは共通しているので、問題集の冊数だけ増やしても効率が悪いです。できる同じような問題だけを何度も解き、苦手なタイプの問題は、似たようなものが多すぎて圧倒されてしまう、といった事態に陥ってしまいがちです。
実際に予備校でも、数学の苦手な人が、学んだ直後にはしっかり理解した上で解けていた問題でも、月日が経ってもう一度やってみると忘れてできなくなっているのを、非常によく見かけます。 学んだ直後でなくても自分で考えて解ける問題以外は、要注意です。
|
Q3 |
数学の苦手な人が夏休み中の勉強で注意すべき点は何ですか? |
数学は『手を動かしてなんぼ』の教科です。確かに、授業を聞いたり、参考書や模試の解答・解説を読んだりして、まず「理解すること」は必要です。ただし、理解したからといって「できる」ようになった、とは限りません。
私は中学、高校とずっとバスケットボール部だったのですが、よく夜中にテレビでNBA(アメリカのプロバスケットボール)の試合を観ていました。そこで選手たちの美しいプレーを見て、「いまの動き方なら私にもできそう! 明日試してみよう!」などと思うことも数え切れないほどありました。しかし、次の日学校に行っていざコートに立ってみると、思うようには動けません。なぜでしょうか。
言わずもがな、練習をしていないからです。当たり前ですね。
プロでもない私が、練習もせずに同じようにできるわけがありません。理屈がわからないと動けませんが、わかったところで動けるとは限らないのです。
数学も、十分に熟練した人であれば、読んでわかったことがすぐ実行できるようになるかもしれませんが、ほとんどの人はそうではありません。特に数学は、得た知識をそのまま書けばいい、なんて問題は皆無といっても過言ではなく、たとえ似たような問題であっても数値や条件のちょっとした違いだけで解き方や計算が変わったりします。
つまり、「理解し、覚える」ことと「できる」ことがかなり乖離している教科なのです。
だから『数学は手を動かしてなんぼ』。必ず、実際にやってみることが大切です。聞いたり読んだりして「いけそう!」と思っても、しっかり手を動かしてください。手を動かせば、本当はわかっていなかったところが浮き彫りになってくるでしょう。
あ、もちろん、写経せよと言っているわけではありませんのでご注意を。同時に脳も動かしてくださいね。
ちなみに、声に出して説明してみると、もっと、「わかっているかどうか」がはっきりします。学校で友達に、家で家族に、あるいは自室でペットや架空の後輩に対してでもいいので、勉強したことを声に出して説明するのはとってもおすすめです。
|
★ポイント★
|

住吉千波(すみよし・ちなみ)
河合塾講師、東進ハイスクール・東進衛星予備校講師などとして高校生や大学受験生に、個人では小学生から大人まで、幅広い層に数学を教えている。京都生まれ京都育ち。神戸大学大学院理学研究科数学専攻修了。河合文化教育研究所研究員。
| 連載予定 |
| 第1回『受験数学の始め方』(2021年4月2日にアップ済み) |
| 第3回『過去問の使い方』(2021年10月15日にアップ済み) |
| 第4回『共通テストへの備え方』(2021年12月1日にアップ済み) |
| 第5回『2次試験への備え方』(2022年1月17日にアップ済み) |
お楽しみに!