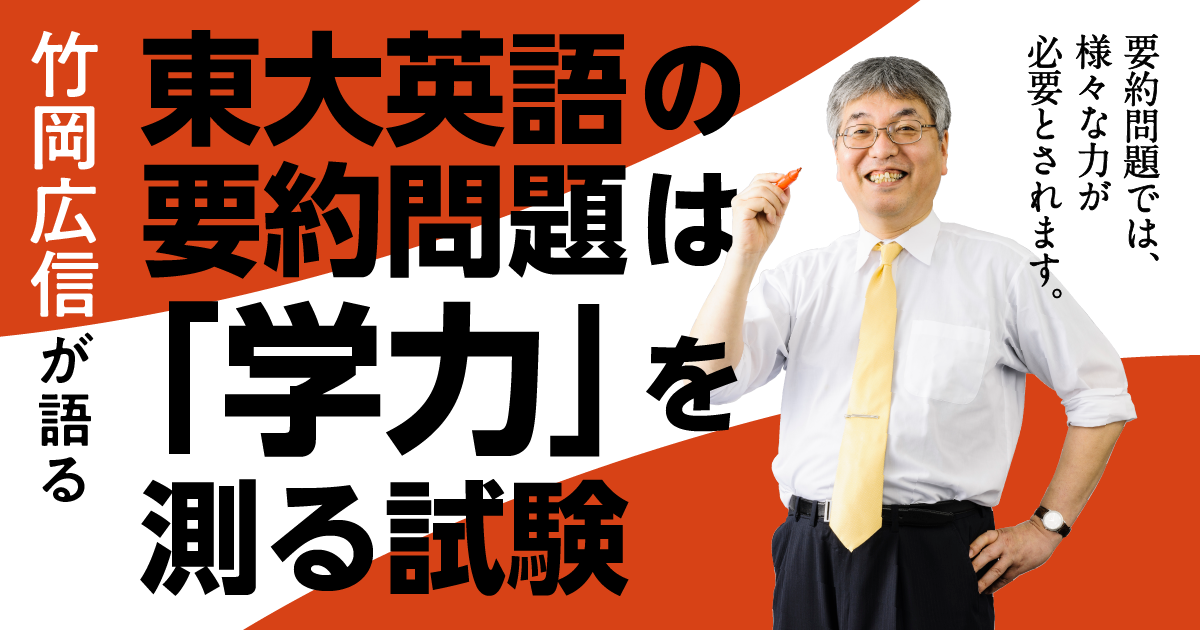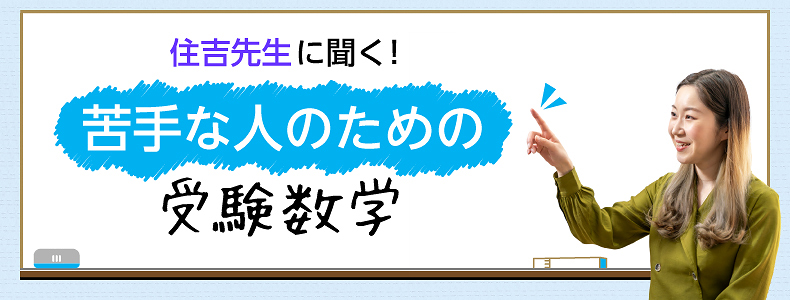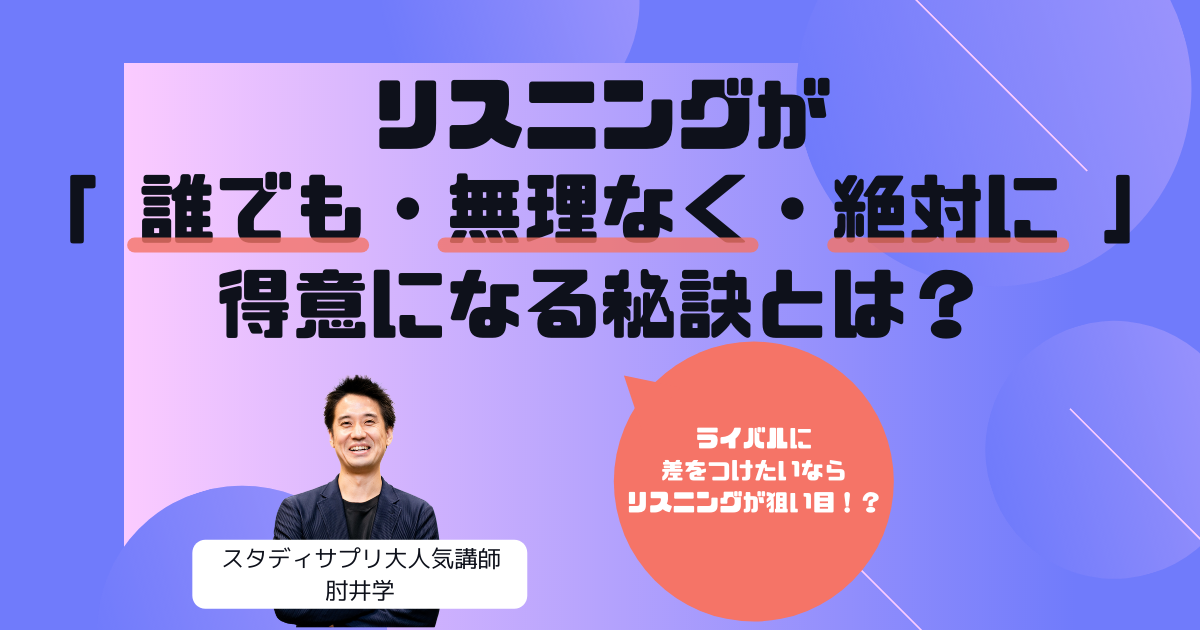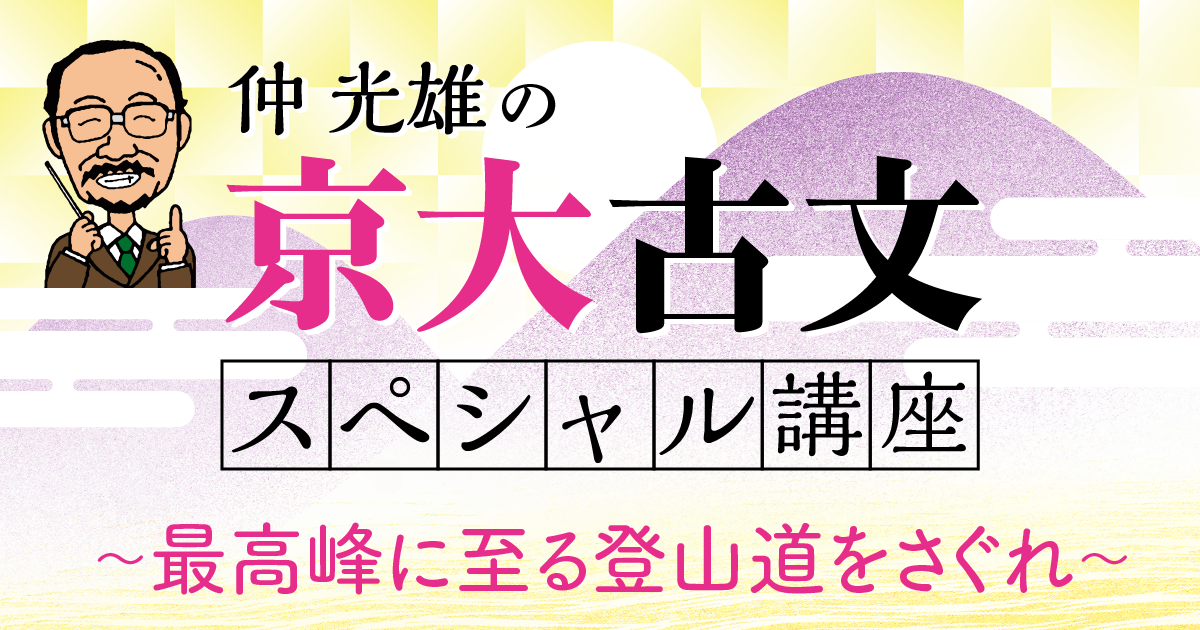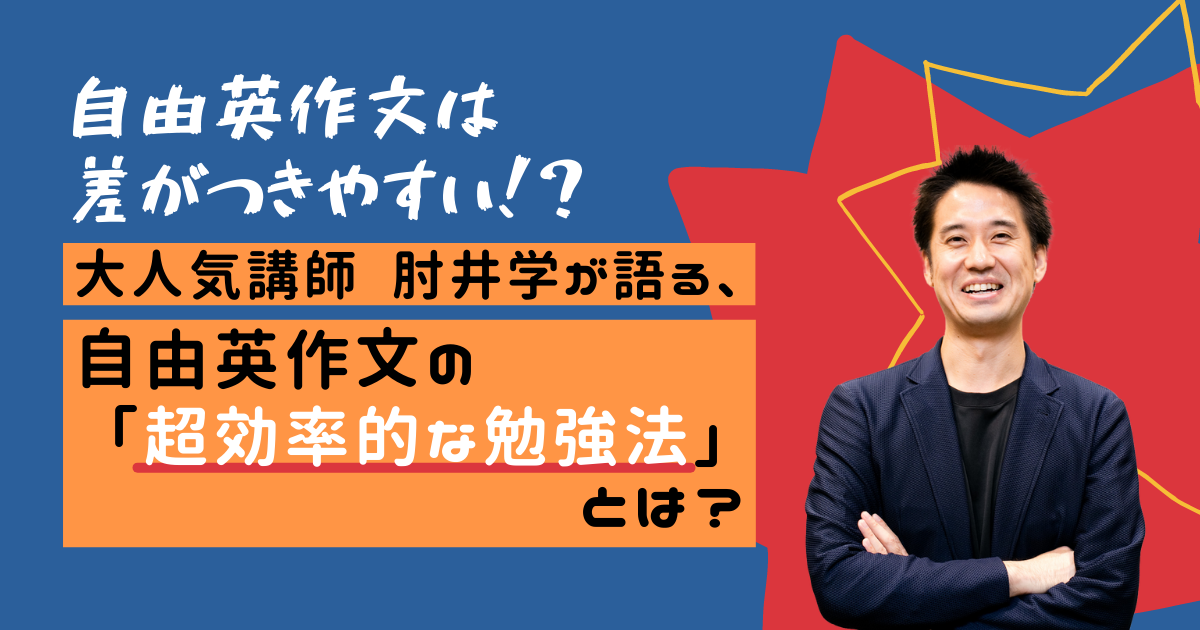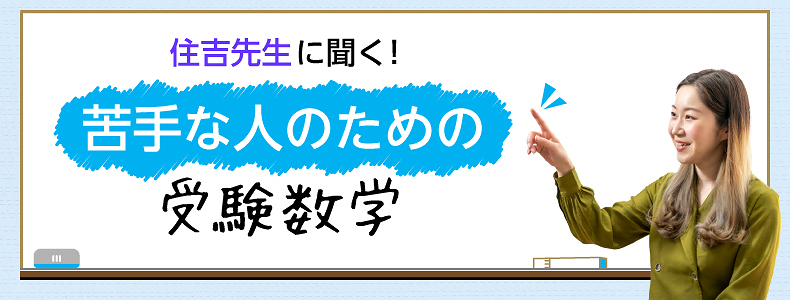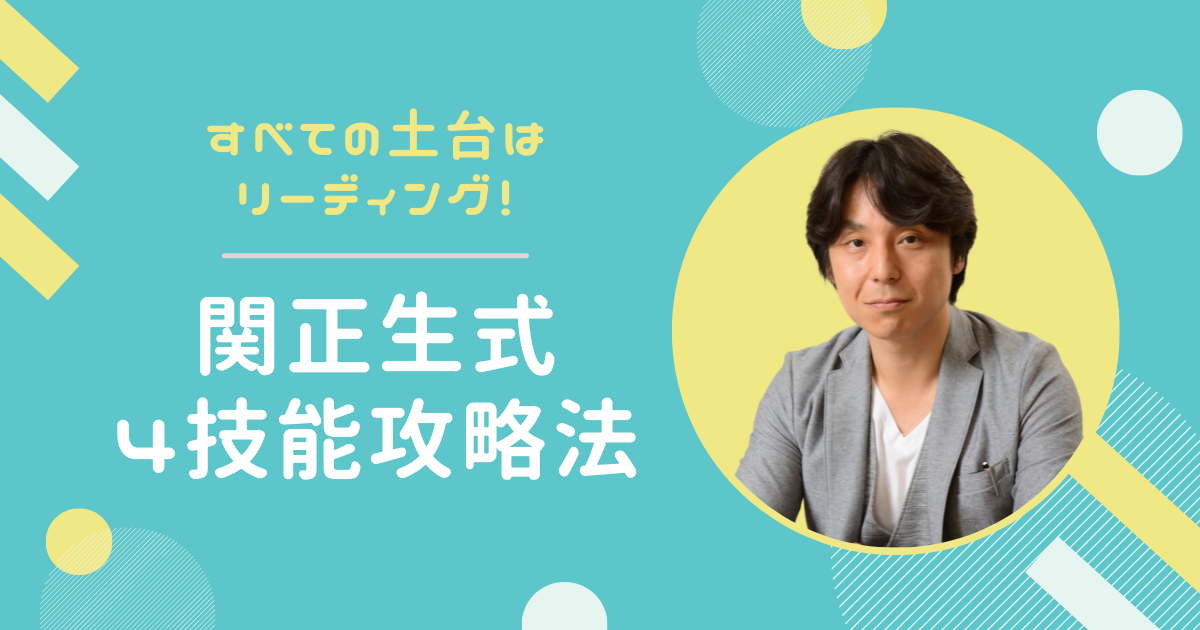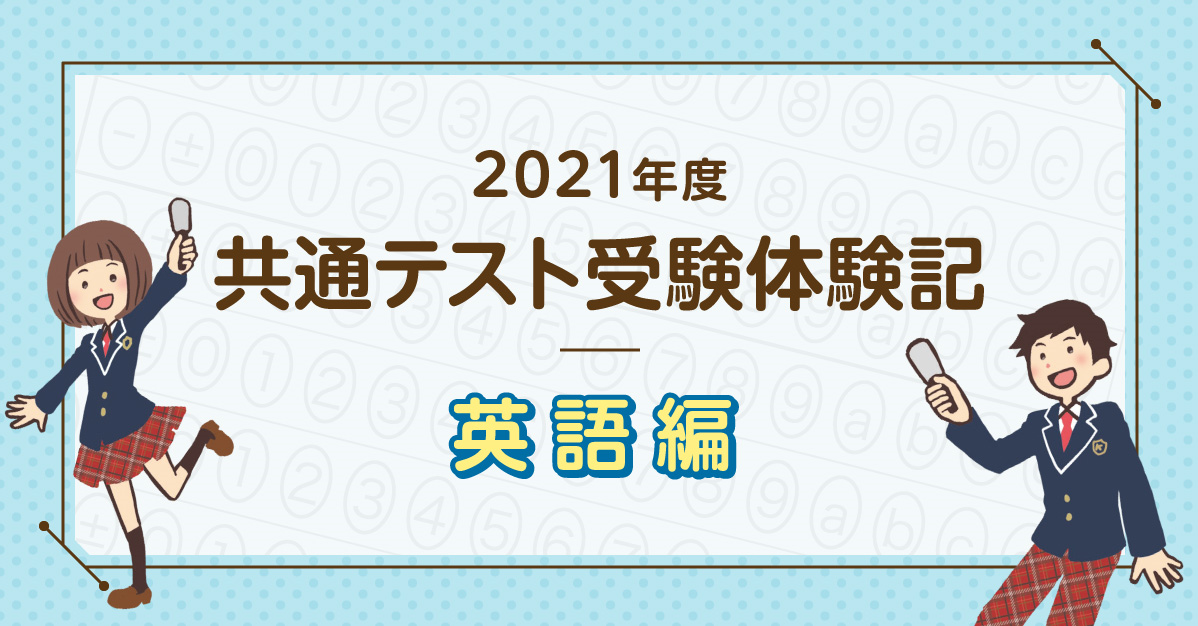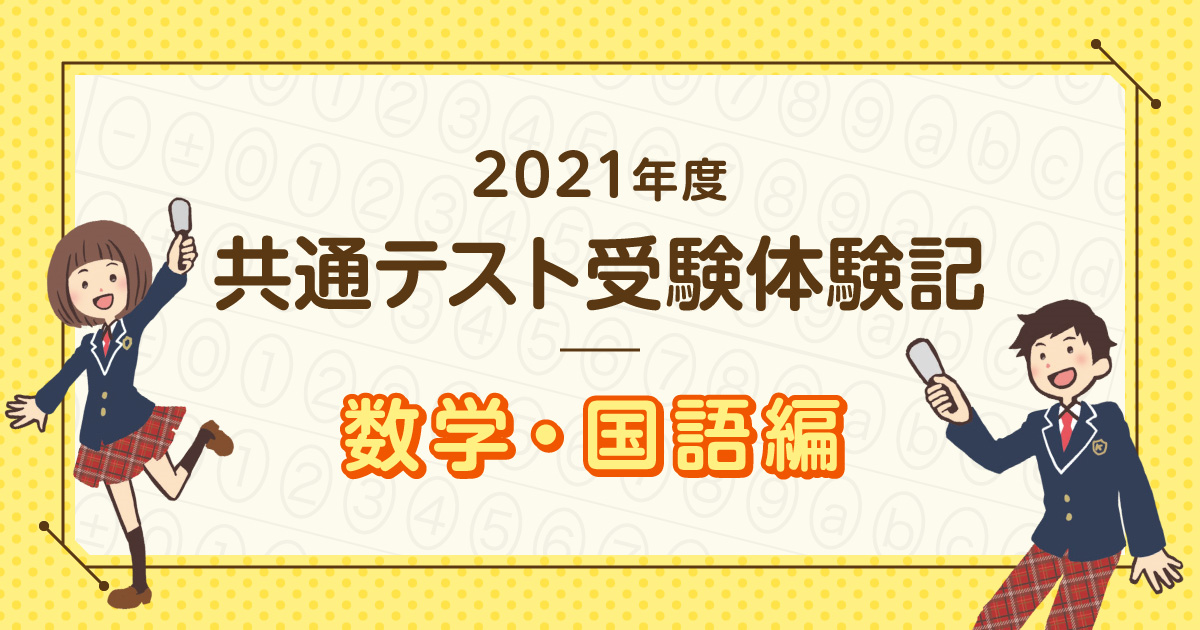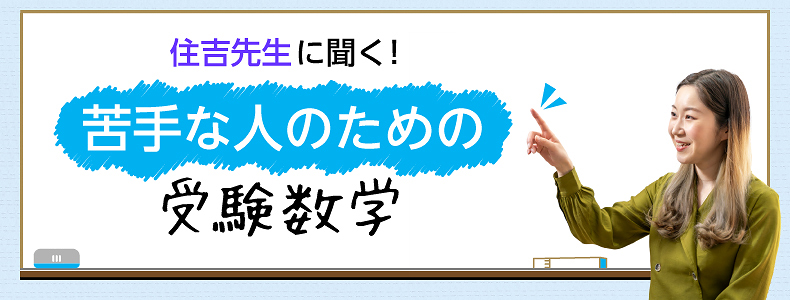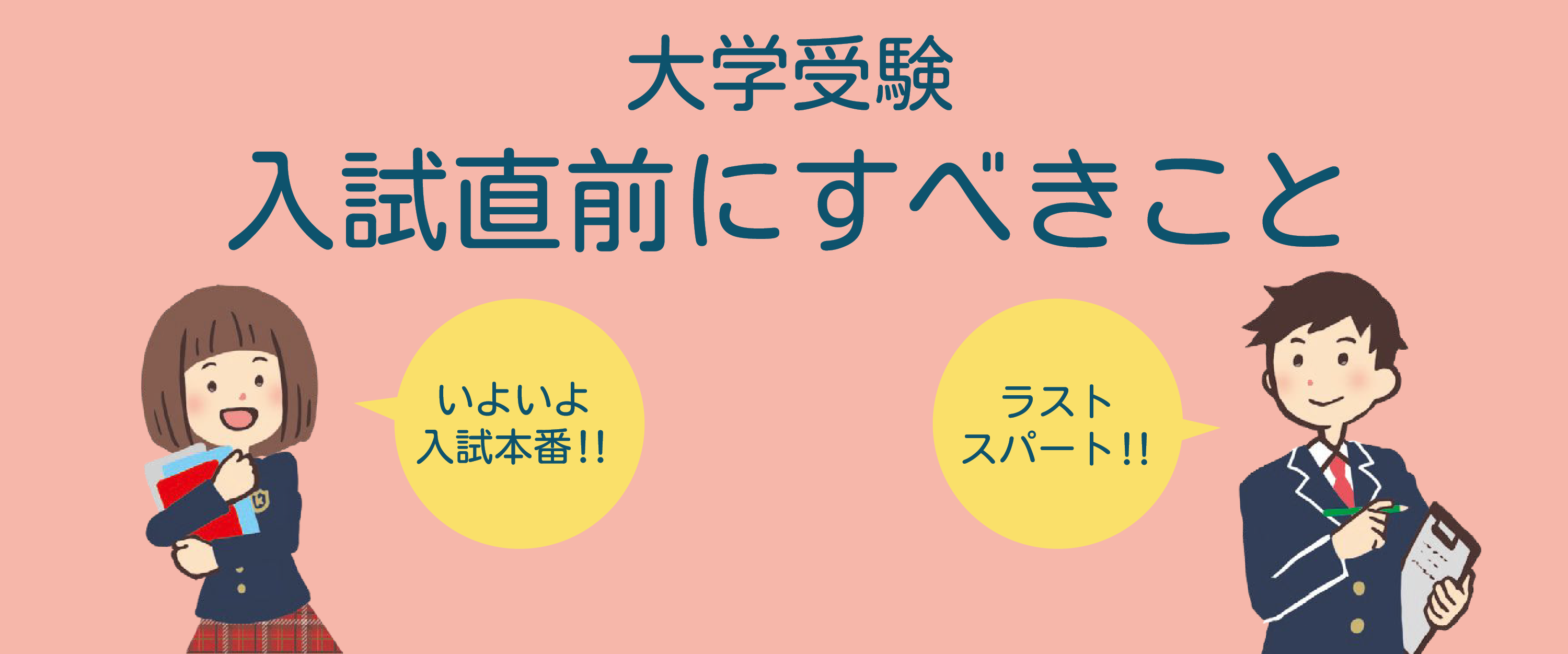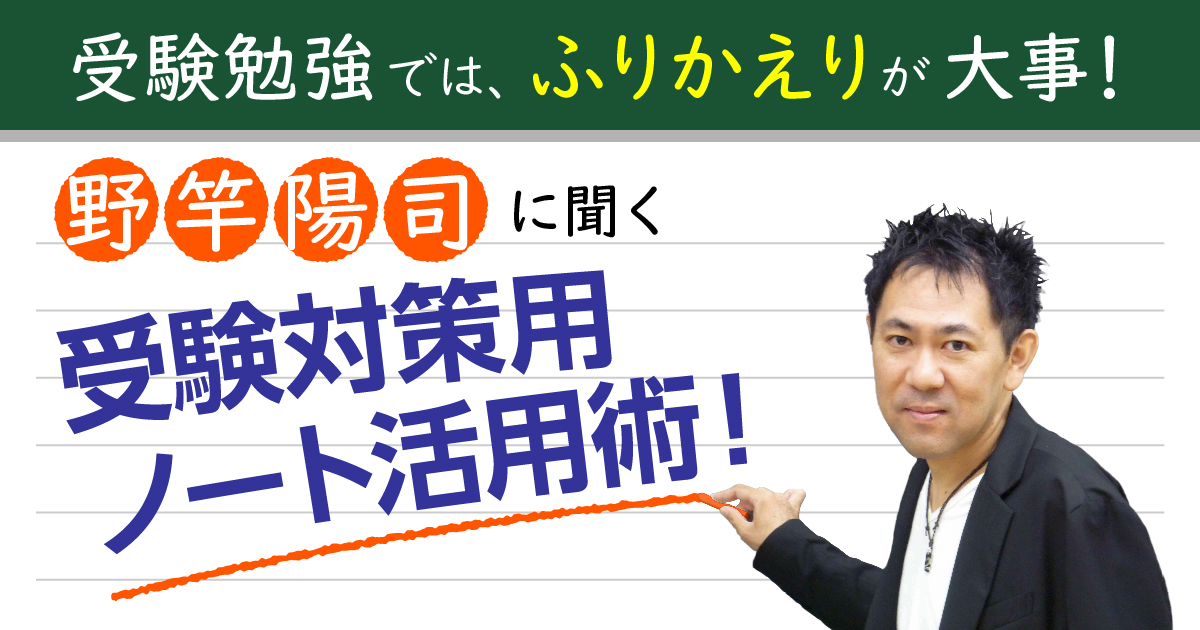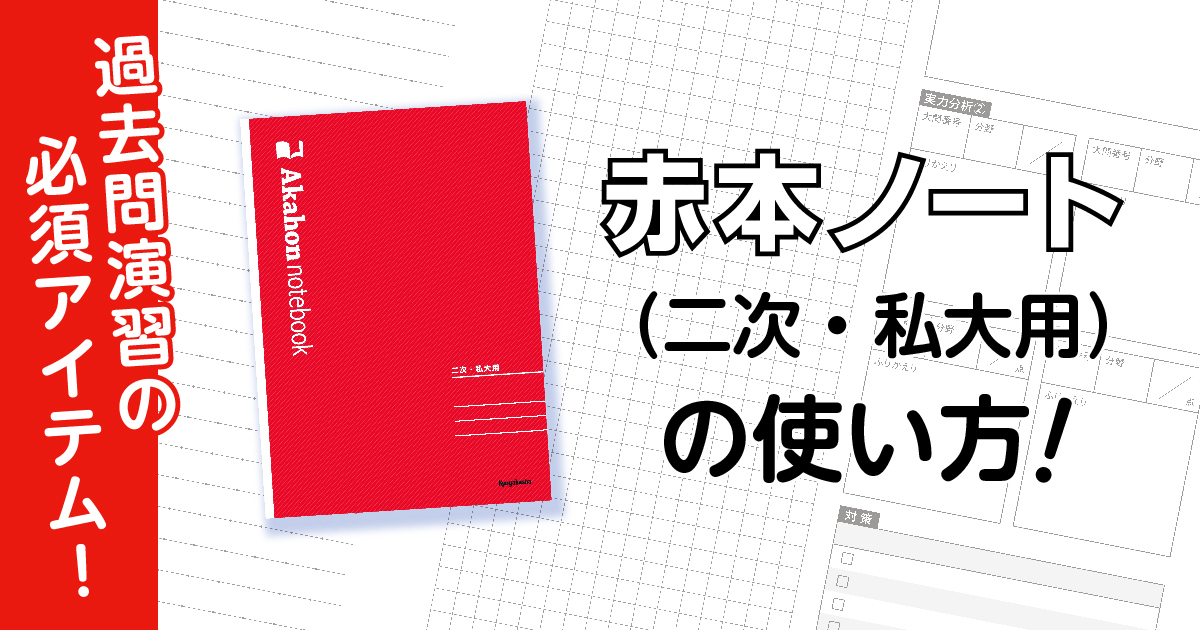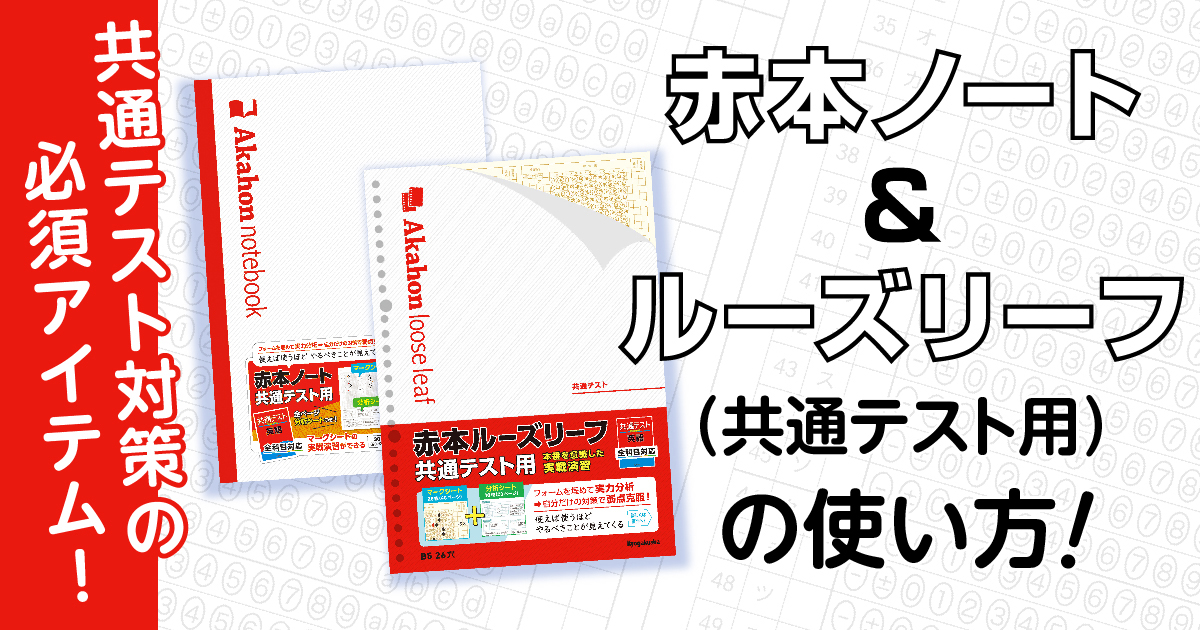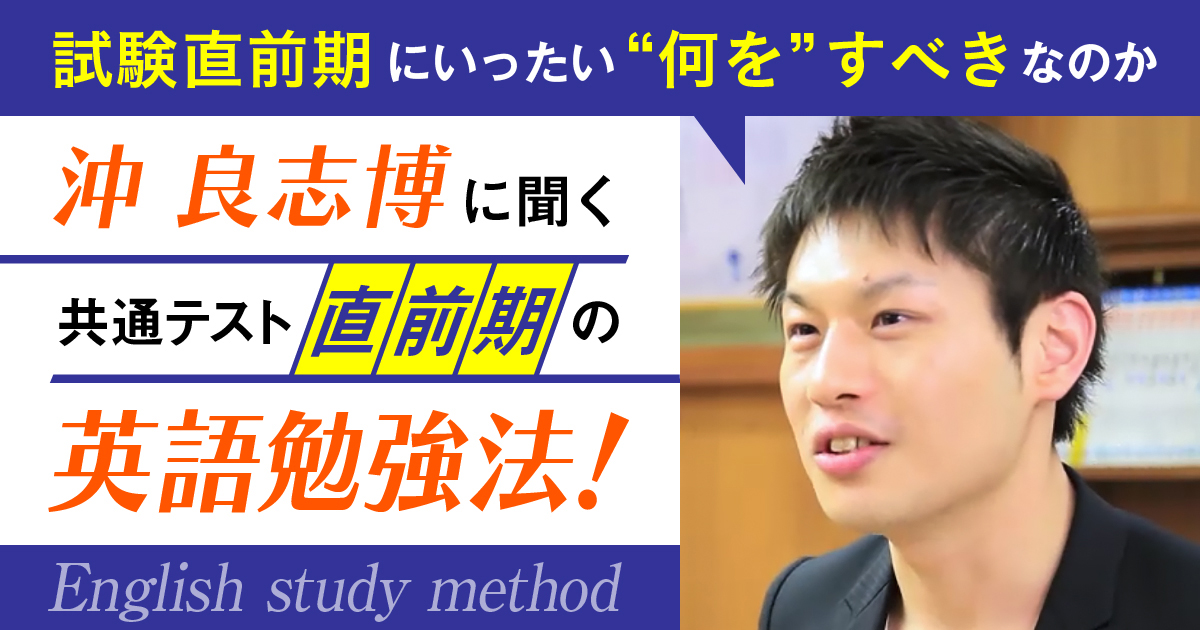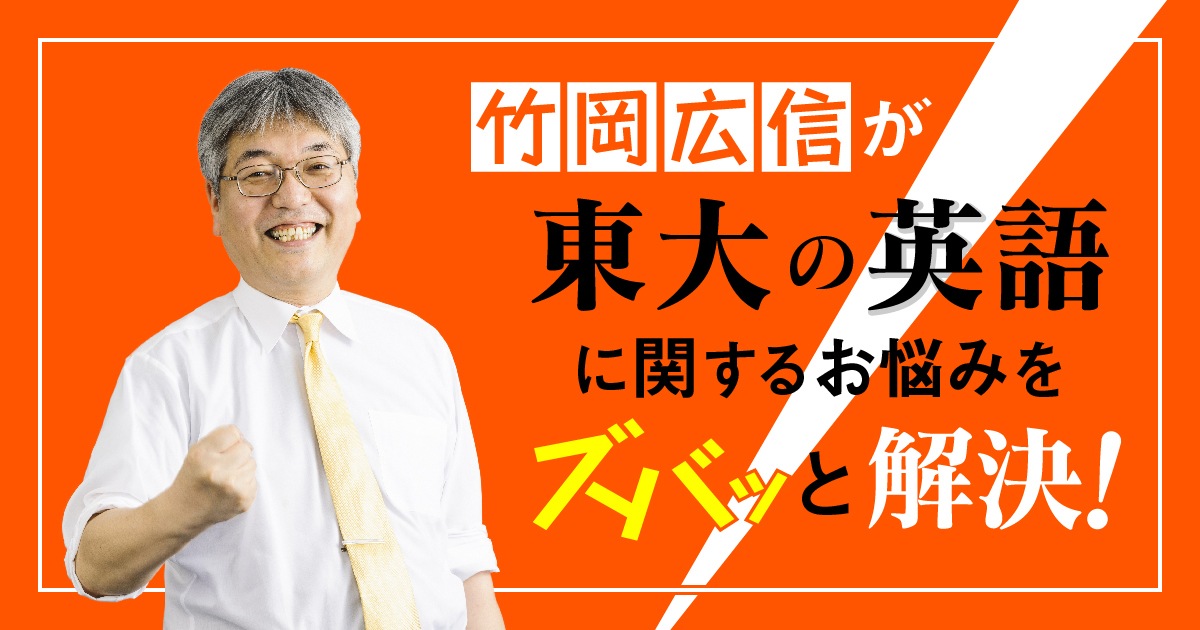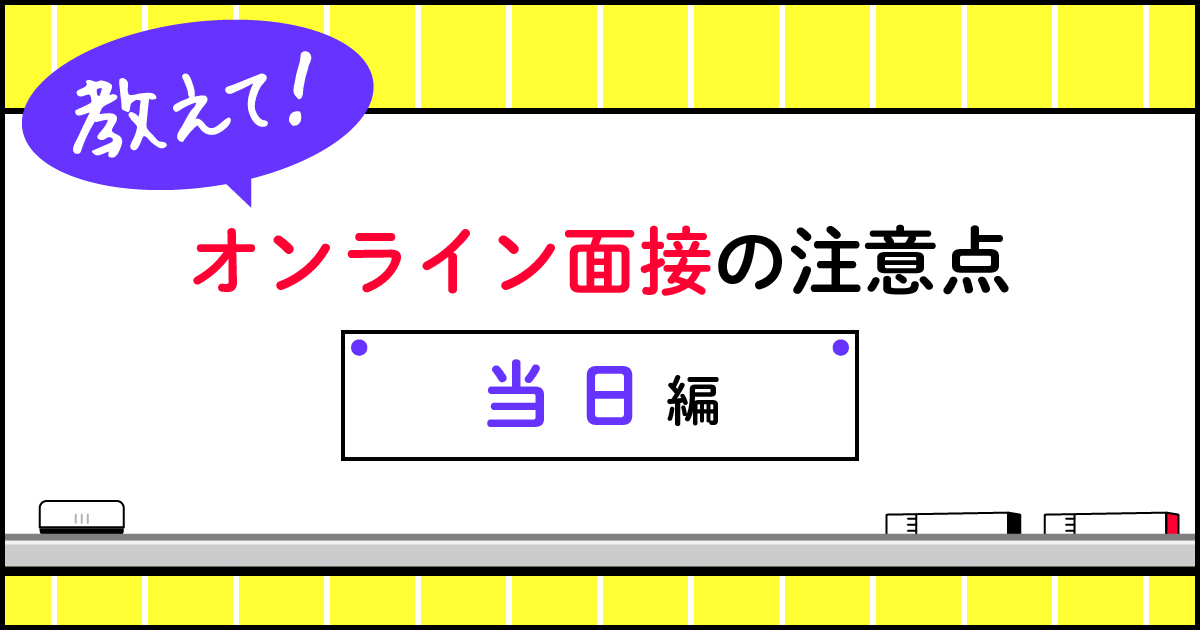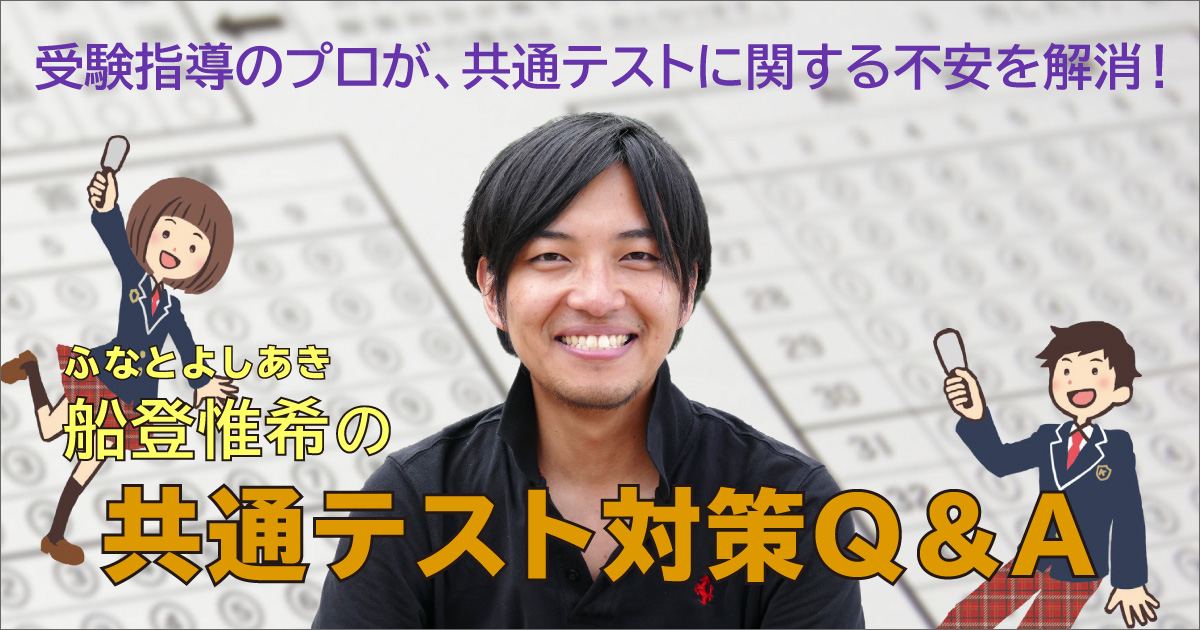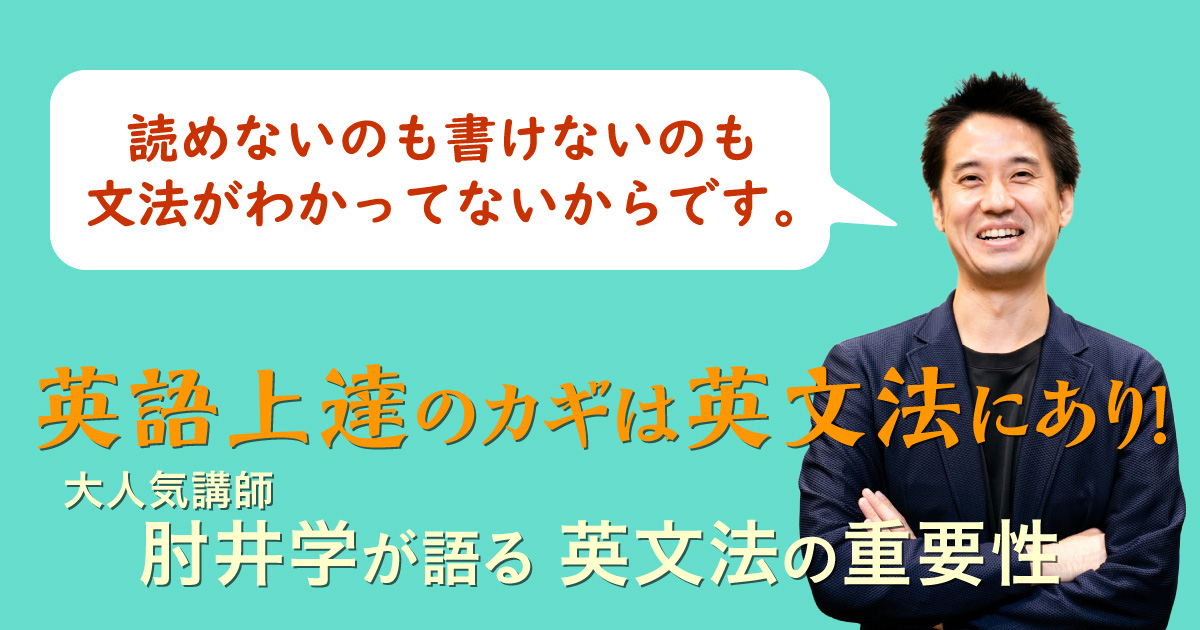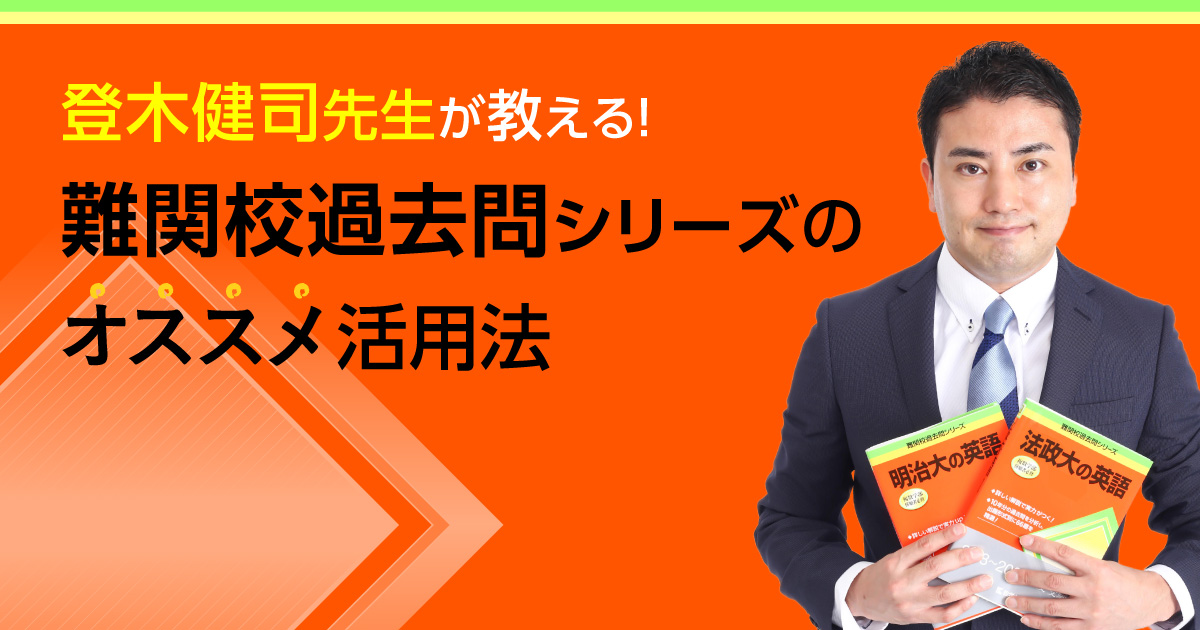
難関大英語指導のエキスパート・登木健司先生に、難関校過去問シリーズを使用するのに効果的な時期や、オススメの活用法を伺いました。受験生必読の内容です。
志望大学・学部にあった良問に取り組むことが、合格への近道
――先生と難関校過去問シリーズとの出会いについて教えてください!
登木 久米芳之先生が執筆されている『法政大の英語』『立教大の英語』※の存在を知り、私の講座に通っていた現役生にすすめたのが最初でした。現役生は、一度受験を経験している高卒生に比べて、受験に対する情報も少なく、問題のチョイスが上手ではありません。志望大学・学部では通常出されないような、超難問が解けなくて落ち込んだり、逆に、重要な知識や視点を学べるような普遍的な問題を、「自分の志望大学・学部の問題ではない」という理由だけで解かなかったり、といった残念なことが多かったのです。 ※『立教大の英語』は、入試制度の変更のため現在刊行しておりません。
――なるほど。入試まで時間が限られているなかで、「どの問題を解くか」はとても重要ですね。
登木 その点、難関校過去問シリーズは、合格圏内に入るために必要かつ十分な量とレベルの良問ばかり。小手先のテクニックではない、併願校や共通テスト対策にも役立つような、本質的学力の養成を意図した解説も、大きな特徴でしょう。このシリーズの登場によって、非効率的な勉強をする学生が減ったのではないかと思います。利用した生徒の多くが大幅な学力アップを達成し、みごと合格の栄冠を勝ち取っていきました。その後、同シリーズの『明治大の英語』や、全国の難関国立大学のものもすすめるようになりました。
夏は赤本、秋は難関校過去問シリーズで段階的な学習を
――難関校過去問シリーズは、難関大学の入試問題を科目別・出題形式別に収載した過去問題集ですが、入試までのスケジュールのなかで、いつどのように使うのがオススメですか?
登木 まず、7月頃までに、第一志望の大学の問題と自分の現状の学力との差を測っておく必要があります。その際には、通常の赤本を使えばよいでしょう。最新の問題を解いて、傾向をノートにメモします。問題数は、読解英文の長さは、記述式問題の解答字数は、といった表面的な分析だけではダメ。英文のテーマ、ジャンル(論説文・事実説明文・随筆・物語など)なども必ずチェックしましょう。
それだけでなく、記述式問題の解答の根拠が、本文中の複数の箇所に散らばっているのか、あるいは、下線部の周囲や最終パラグラフなど特定の箇所にあるのか。さらに、それらを自分の言葉でまとめ直す(抽象化する)必要があるのか、それとも、本文の言い回しをそのまま使って解答すればよいのか。このようなレベルまでしっかり検討します。赤本の全訳や解答・解説をこういった視点で活用してみてください。この時点では、問題を解けなくてもかまいません。
最新の傾向と求められる学力レベル(目標レベル)がわかったら、学校や予備校・塾の授業を通じて、土台をしっかり作りましょう。SVOCの文構造や、英文法、単語や熟語の知識といった、英語の基本をおろそかにしないように。
――いきなり難関校過去問シリーズを使うよりも、段階を踏んでから取り組むほうが効果的なのですね。
登木 ある程度土台ができたところで、秋ぐらいに、難関校過去問シリーズを使って、目標レベルを目指して問題演習をつんでいきます。出題形式別の章立てになっているので、読解や英作文の集中講座を受けるような感覚で、自分の弱点や強みに的を絞って対策をすすめることができます。
オススメの取り組み方は、赤本分析からわかった、最新の傾向に近い形式の問題を、難関校過去問シリーズに掲載されている問題のなかからピックアップして、優先的に解いていくことです。このとき、私立大なら、似た問題が他学部でも出されていることに気づくでしょうし、国立大なら、古い問題にも最新の問題との共通点を発見するはずです。
|
難関校過去問シリーズの問題に、あなただけのオリジナルの書き込みが入った英文を、本番まで何度も音読します。気づいたことは、そのつど余白に書き込んでいけばよいでしょう。余白に書かれたポイントも確認していくことによって、本番で落ち着いて問題に取り組むことができるはずです。
――一度解いて終わりではなく、とことん活用することが肝心だということがよくわかりました。最後に、受験生への応援メッセージをお願いいたします!
登木 新型コロナウイルスの流行と共通テストのスタートで大変な年になってしまいましたが、それでも、日々明るく、前向きに努力を続ける現役生・高卒生諸君を見ていると、「私も頑張らなければ!」と逆に勇気と元気をもらっています。つらいときは休息も必要! 休むことに罪悪感を持たないこと。しかし、最後の最後に頼りになるのは自分だけですので、明るいほうへ、自分で自分を引っ張っていってほしいと思います。
|
登木健司(とき・けんじ)
|
関連ページ
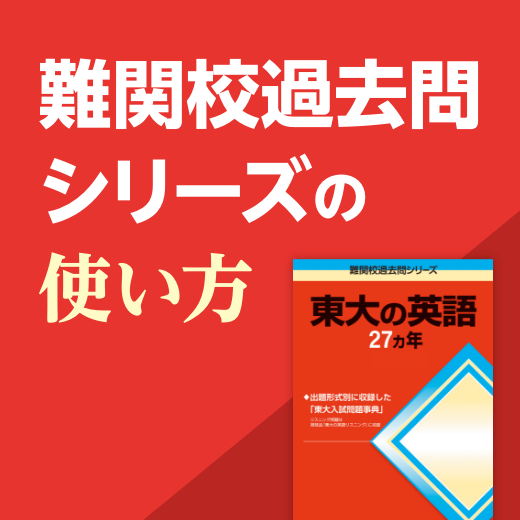
.png)