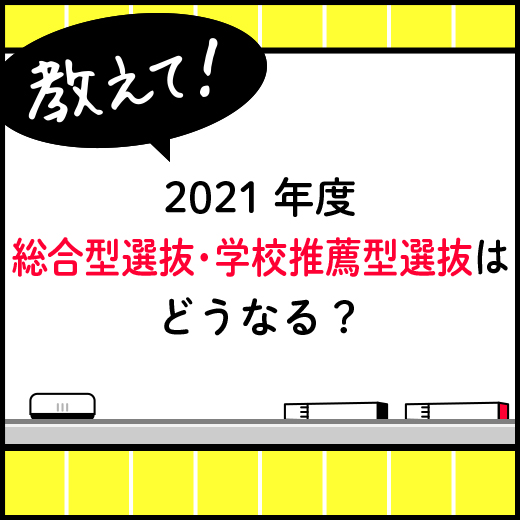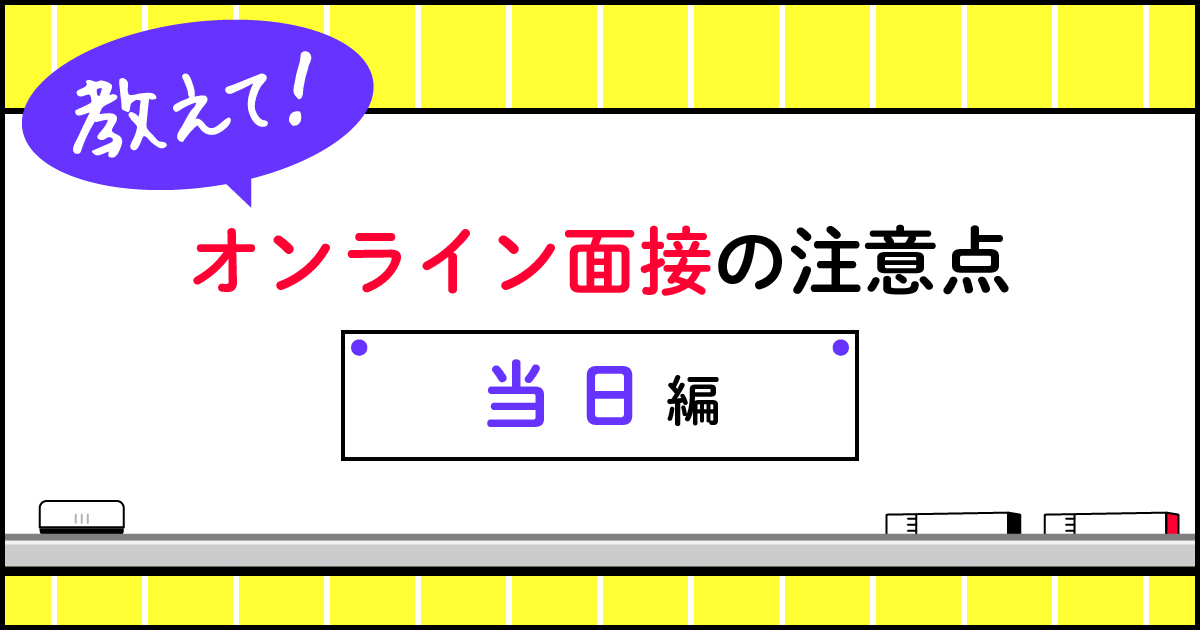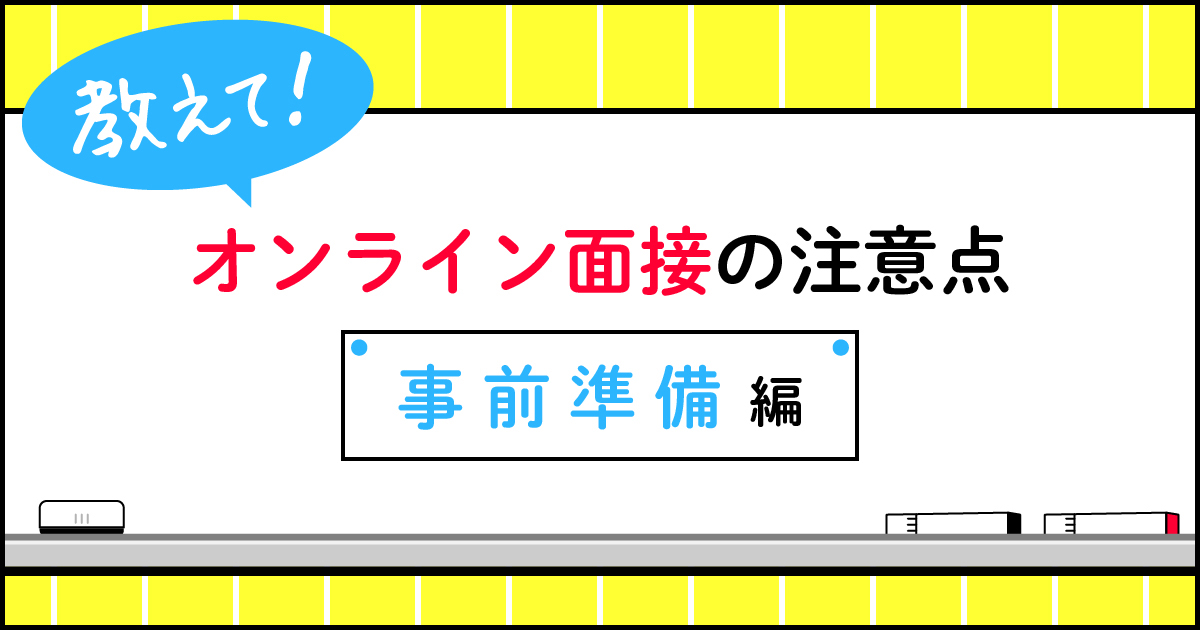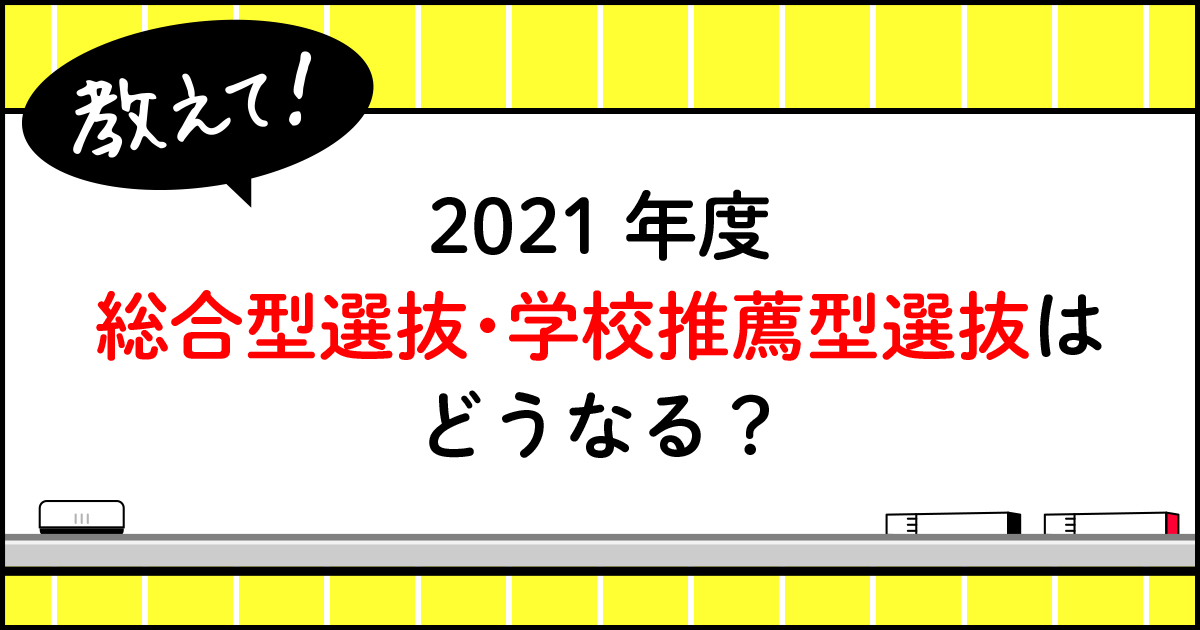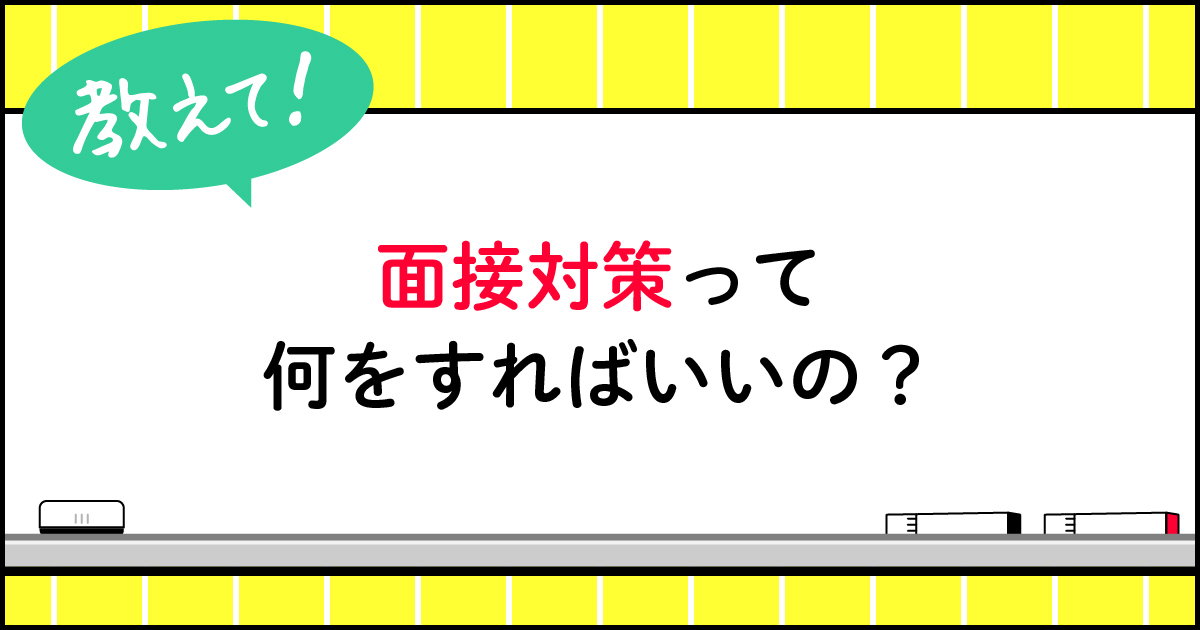
大学入試のなかでも、面接試験はどのように対策をしたらよいかわからないという受験生は多いかと思います。面接試験は、総合型選抜と学校推薦型選抜だけではなく、医療系学部や教育系学部などの一般選抜でも課されることがあり、受験する人は多くなってきています。今回は、そもそも面接試験では何を見られるのかを押さえつつ、対策を考えていきたいと思います。
何のための面接?
面接の対策をするためには、まず面接試験が「何を見るための試験か」を考える必要があります。よく言われるのは「人柄」や「コミュニケーション能力」です。もちろん、それは間違いではありません。ですが、場面は大学入試です。重要となるのは、人柄やコミュニケーション能力の奥にある「大学・学部とのマッチング」であると考えましょう。
ここを見ている① 志望分野への関心の強さ
大学は、ただ成績がよい人を入学させようとしているわけではありません。例えば、過疎地域の医療を担う意志のある人、様々な家庭環境で育った生徒たちと学ぶために先生を目指す人など、本気で学ぶ人に入学してほしいと思っています。そのため、志望する学部に強い関心を持っているかどうかを見ています。
ここを見ている② 志望分野への適性があるか
どんなに強く志望していても、あまりに向いていない人を入学させるのはためらわれます。例えば、「将来は、芸術家になりたいと思っています! 尊敬するのはパブロ・ピカソです。ゲルニカに感銘を受け、これまでに5回スペインに行きました。背景となったスペイン内戦について調べたいので、第二外国語はスペイン語をとりたいと思っています」と話す受験生がいたとします。芸術学部の面接をしている先生は、熱心さに心を打たれるでしょう。ところが「絵は美術の時間にしか描いていません」と続けたらどうでしょうか。実技が必要な油絵の学科ではよい評価はもらえないでしょう。でも美術史系の学科では実際に絵を描いていないことは特に問題ではなく、合格するかもしれません。このように、情熱の有無だけではなく、学科の特性とマッチしているかが重要なポイントなのです。
関心と適性はどのように計られるか
志望分野とのマッチングといっても、受験生が「私は適性を持っています」と言うだけで、適性アリの判定をもらえるわけではありません。過去の経験や将来のビジョンなど、話す内容から、適性や本気度を見極めているのです。そして当然、適性というのは分野によって異なります。冷静な判断ができる、人情味をもって接することができる、粘り強く努力しつづけることができるなど、どれも素晴らしい能力ですが、必要とされる度合いは学部や専攻によってさまざまです。学部・学科の特性をよく知った面接官の先生方は、必要な資質が何かを念頭に置いたうえで、目の前の受験生がそれを持っているかを見ているのです。そのとき判断する物差しになるのが、以下のような項目です。
【志望度】
|
【適性】
|
上記は一般的な項目ですが、面接で何を評価するのかは、選抜要項に記されていることもあります。例えば大阪大学の「令和3年度 総合型選抜・学校推薦型選抜 学生募集要項」には、学部ごとに選抜方法が書かれています。歯学部は以下のように記されています。
面接は、医療人になるための適性や明確な目的意識を持っている者を積極的に受け入れることを目的に行い、①全般的態度 ②受験の動機、目的、意識 ③意欲、積極性 ④協調性、柔軟性 ⑤生命科学の勉学・研究に必要な適性と能力を評価します。
また、アドミッション・ポリシーにも求める人材像が記されており、歯学部では、このうち面接試験及び推薦書によって下記の1、2、3、6、7に関する能力を評価すると明示されています。
大阪大学のアドミッション・ポリシーのもとに、歯学部では健康科学に貢献できる創造力を備え、歯学研究、歯科医療分野における次世代のリーダーを目指す意欲に満ちた、以下のような能力・資質を備えた人を受け入れます。
|
(出典:「令和3年度大阪大学 総合型選抜・学校推薦型選抜 学生募集要項」)
選抜要項をよく読むことはもちろん、志望する分野でどのような適性が求められているのかを自分でも考えておくとよいでしょう。
面接対策は、自身のことを考えるチャンス
面接の対策をするとき、受験生のみなさんは「なんとか突破したい」と考えると思います。しかし、付け焼刃の知識に、どこかからコピーしたような志望動機では、本当の面接にはなりません。そのような「薄さ」は相手にも伝わりますし、自分で将来のことを考えるチャンスを逃すことになるのです。面接対策でするべきなのは、「攻略」といった概念をいったん捨てて、しっかり志望分野・大学・自分について調べることです。
これだけはしておきたい面接対策
前節で書いたように、面接対策は、ただ「切り抜ける」ためではなく、「自分のことを正しく知ってもらう」ためにするものです。想定問答だけ準備しておけばいい、ということではありません。納得できるまで自身を見つめ、志望学科のことを考えてみてください。そのために、以下のような項目から考えてみましょう。
- 選抜要項を読み、面接で何を見られるのかを把握する(書かれていないこともある。自分でも考える)
- アドミッション・ポリシーを理解し、自分の長所と結びつける
- 志望動機をもう一度考えてみる
- 志望動機につながる過去の経験を人に話せるようにする
- 将来のビジョンを描く
- どのような適性が必要とされているかを考える
- 想定される質問への回答を考える
最後の想定問答は、「質問」→「回答」で終わらせないでください。人と話をするときには、回答を掘り下げるような質問が続くことが普通です。そのため、「1つ目の質問」→「回答」→「さらなる質問」→「回答」→…というように、つなげて考えていきましょう。そうすることで、動機や自己分析をさらに一段深めることができます。
模擬面接をすることで、本番も落ち着いて話せる
ひとりできちんと考えを深めたうえで、先生や友人、家族などに模擬面接をしてもらうと安心です。みんなはじめての面接は緊張してしまうもの。模擬でも、経験をしておくことで、すこしリラックスして臨むことができます。
面接は緊張しそう…と不安に思う人もいるかもしれませんが、準備をして自信を持って臨むことが一番の対策です。これを機会に、志望分野・大学・自分自身をよく見つめてください。
2021年度の面接試験の特徴は、「オンライン面接」。次のブログで解説します。お楽しみに!
関連ページ